2016/09/20(火)「怒り」 今年のベストを争う作品
東京・八王子の夫婦が自宅で惨殺され、現場に大きな血文字の「怒」が残されていた。という発端から映画は東京、千葉、沖縄に現れた殺人犯かもしれない3人の男とその周辺の人々のドラマを描く。映画の主眼はだれが犯人かということではなく、周辺の人々の心の揺れ動きの方にある。
これは吉田修一の原作でもそうだ。個人的に深い感銘を受けた原作を同じ吉田修一原作の「悪人」に続いて李相日監督が映画化すると聞いて大いに期待した。期待はまったく裏切られなかった。見ながら、いくつかの場面で胸が熱くなる。登場人物たちの慟哭、後悔、悲しみ、やりきれなさが胸に迫ってくるのだ。多くの登場人物たちのさまざまな感情の渦に巻き込まれたよう。見事な脚本と編集とリアルな絵づくりと俳優のリアルな演技に坂本龍一の美しい音楽が加わって、ケタ違いに充実した映画になった。今年のベストを争う作品であることは間違いない。
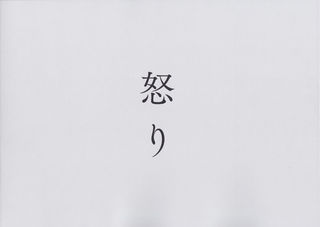
八王子の事件から1年後、沖縄の無人島に現れた男(森山未來)は田中と名乗る。高校生の小宮山泉(広瀬すず)は同級生の知念辰哉(佐久本宝)のボートで島に遊びに行き、田中と出会う。どこか田中のことが気になった泉は交流を深めるようになる。東京で藤田優馬(妻夫木聡)はゲイのパーティーで大西直人(綾野剛)と出会い、お互いに惹かれ合って一緒に暮らすようになる。直人は自分のことを一切語らなかった。千葉の漁港で働く槙洋平(渡辺謙)は娘の愛子(宮崎あおい)を歌舞伎町の風俗店から連れ戻す。槙の下では3カ月前にやってきた田代哲也(松山ケンイチ)が働いていた。コンビニ弁当を食べている田代を見て、愛子は弁当を作るようになる。やがて愛子は田代と一緒に住みたいと言い出す。
3つの場所で進行する物語が交錯することはない。素性不明の3人の男と関わる人々の姿がそれぞれに描かれていく。凡庸な監督が撮ったら、エピソードの羅列に終わっただろうが、李相日監督は沖縄から東京、東京から千葉へと転換する場面でフラッシュフォワードを使ったり、エピソードに軽い関連を持たせ、エモーションをうまく持続させている。
渡辺謙も宮崎あおいも松山ケンイチも妻夫木聡も綾野剛も広瀬すずも森山未來も、それぞれが1人で主演を張れる俳優。それが束になって出てくるのだから、画面の厚みがただごとではない。松山ケンイチと綾野剛に関しては受けの役柄のため演技の見せ場がないのだけれど、それでもこの2人が演じることによる効果は大きい。最も儲け役なのは宮崎あおいで、予告編を見た時からうまいと思ったが、「少し人とは違う」女を演じきっている。これで女優として大きく成長したのではないか。それはアイドル女優だったらやらないような難しい役を演じる広瀬すずにも言えることで、試写を見た事務所の社長が「いい映画になって良かった」と涙ぐんだ(キネ旬2016年9月下旬号)というのもよく分かる。
空撮を交えた笠松則通の撮影も見事。どの場面もないがしろにしないという強い意志が伝わってくる。隙がない映画というのはなかなかないし、原作を無茶苦茶にする映画も多いのだが、李相日が書いた脚本は原作のエピソードを削りながら、そのエッセンスは少しも損なわれていず、驚くほど原作に忠実なイメージになっている。ストーリーを知っていても圧倒されるのは画面と脚本の構成、出演者の演技が高いレベルにあるからだろう。上映時間2時間22分。それでも短い。3時間でも4時間でも見ていたくなる。
2016/09/08(木)「文庫X」とは何か
岩手県盛岡市の書店がタイトルや著者名、出版元などを隠し、「文庫X」として販売した文庫本が売れているそうだ。この書店では既に1000冊を販売した。日経の記事(配信は共同通信)によると、「試みは全国12都道府県に拡散し、さらに広がる勢いをみせている」という。
とても気になるので何の本か調べてみた。中身をバラしたサイトは見つけられなかったが、手がかりは「文庫で価格は810円」「発売は5月」「小説ではない」「500ページを超える」「単行本の発売は3年前」など十分にある。
amazonで「文庫 810円」で検索すると、いきなり清水潔「殺人犯はそこにいる」が出てくる。いや、こんな有名な本をタイトル隠して売るわけがないと思ったが、単行本が出たのは2013年だし、ページ数は509ページ、発売は5月28日と条件に一致している。何よりも「心が動かされない人はいない、と固く信じています」と書店員さんが言うだけの内容を持つ本であることは確かだ。
念のためにHonya Clubで検索してみた。ここの詳細検索は発売時期の指定ができる。「5~7月に出た文庫で価格は810円」を指定して検索した。出てきたのは36冊。「殺人犯はそこにいる」以外のノンフィクションは「日本軍の知られざる秘密兵器」「読書脳」「それでも、日本人は戦争を選んだ」の3冊。「殺人犯…」以外で該当しそうなのは「それでも、日本人は…」だが、この本、単行本が出たのは2009年なのだ。やはり、文庫Xは「殺人犯はそこにいる」で間違いないらしい。
「隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件」というサブタイトルがついた「殺人犯はそこにいる」はノンフィクション書評サイトのHONZが単行本発売当時に猛プッシュしたので読んだ。あまりに面白かったので同じ清水潔の「桶川ストーカー殺人事件」も読んだ。これがもう、「殺人犯…」よりも面白い。いや、面白いという表現は適切ではない。怒りで頭がクラクラしてくるような強烈な本である。感想をどこかに書いたよなと思って探したら、ブクログに書いていた。
「今ごろ読んだなんて書くのが恥ずかしくなるような名著。いや、名著という冷静な形容はこの本にはふさわしくない。読みながら驚き、怒り、哀しみ、恐怖、賛嘆などさまざまな感情がわき起こり、胸を揺さぶられ続ける圧倒的なノンフィクションだ…(中略)とにかくこんな読書体験はめったにない。必読中の必読」。
文庫Xを読んで感動した人はこの本も読んでほしい。
さて、日経の記事で気になったのは版元の担当者の言葉として「本への思い入れが強い書店員さんがいて、それに耳を傾ける読者がいることがうれしい。この信頼関係に感動し、ありがたく思います」と書いてあること。文庫Xは信頼関係で売れているのだろうか。
文庫Xと同じ推薦の言葉を表紙をさらして書いていたら、売れなかったのだろうか。比較できないので分からないが、もし書店と客の間に本当に信頼関係があるのなら、表紙をさらしていても売れるのではないか。では書店員が中身を隠して売ろうとしたのはなぜなのか。表紙が悪いのか、タイトルが悪いのか。記事には「タイトルを見て手に取らない人がいるかもしれないと考えた」とある。しかしそれ以上にノンフィクションが売れない現実があるからかもしれない。
元時事通信記者で作家の相場英雄は東日本大震災をテーマにした小説「共震」のあとがきで「ノンフィクションでは売れないから小説にした」という趣旨のことを書いていた。僕には意外だったが、ノンフィクションは小説以上に売れないらしい。
文庫Xが売れたのは信頼関係があるからではなく、売り方がこれまでになかったものだからだろう。イベント的な売り方が功を奏したと言うべきか。同じ売り方が全国に広がり、ニュースでも取り上げられている以上、今度は話題性が加わって売れていくことになると思う。出版不況の中、どんな形であれ、本が売れるのは良いことなのかもしれないが、少し複雑な気分も残ってしまう。

