2008/11/17(月)「ハッピーフライト」
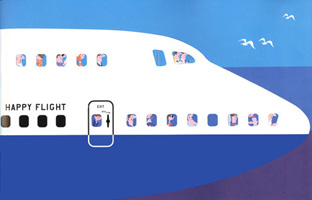
「クライマーズ・ハイ」は落ちた飛行機を巡る群像劇だったが、この映画は飛行機を落とさないために頑張る人たちを描く群像劇。といってもユーモアを散りばめて、笑って感動してそれこそハッピーな気分になれるエンタテインメントに仕上がっている。隅々まで取材が行き届いているなというのが第一印象で、矢口史靖監督、相当に調べたようだ。キネマ旬報によれば、監督は2年間で内外の航空関係者100人以上にインタビューしたという。飛行機がホノルルに向かって飛び立ち、計器に異常が発生し、引き返すまでの数時間の間に新米の副操縦士と客室乗務員(CA)、グランドスタッフ、整備士、管制官などなどさまざまな人間を登場させ、それぞれにドラマを形成している。こんなにいろんな現場にドラマが持ち込めたのは詳しい取材の成果だろう。
憎まれ役で登場した寺島しのぶがクライマックスにきっちりした演技を見せる。その正々堂々とした正論によって客の不当な要求を収めさせ、場面をさらうところなど、とてもうまいと思う。ドラマの構成は見事と言ってよく、これだけ多くの人物を登場させながら、脚本には少しも混乱がない。ANAが全面協力しているので批判が少ないのは惜しいところだが、それでもCAの実態などカリカチュアライズした部分はあり、全面的な宣伝映画などにはなっていない。軽飛行機がぶつかったり、海に沈没したりなどハリウッドのエアポートシリーズのような大事件は起こらなくても航空映画は作れることを示した佳作。というより事故そのものではなく、人間ドラマが映画の成否のかぎを握っていることが分かっているからこそ、こういうスケールで十分なのだ。見て損はない。監督からの要求が凄かったというミッキー吉野の正攻法の音楽にも感心した。
フライトシミュレーションで失敗する副操縦士(田辺誠一)を描く冒頭を見れば、これがクライマックスにつながることは容易に想像できる。国内線から初の国際線に勤務することになった新米CA(綾瀬はるか)と、グランドスタッフを辞めようと思っている田畑智子、コンピュータが操作できずに時代に乗り遅れているオペレーション・ディレクター(岸部一徳)、若手の整備士(森岡優)などなどをさらりと描いた後、飛行機は本筋のホノルルへと旅立つことになる。バードパトロールのベンガルがマスコミを装って近づいた鳥類保護団体から妨害されたために、飛行機にはカモメが衝突、重要な機器を傷めてしまう。折しも台風が関東に近づいており、飛行機は困難な中、成田へそして羽田へと引き返すことになる。
誰が主人公というわけではない。それぞれに見せ場がある。矢口監督に言わせると、素の綾瀬はるかはスーパー・ナチュラルで、これは普通、超自然現象のことを指すが、「超天然」の意味で矢口監督は使っている。「僕の彼女はサイボーグ」に比べると、きれいなところが強調されていないのが難なのだけれど、前半のおかしさはいかにもスーパー・ナチュラルなのだった。クレイマーに泣かされる同じくCAの吹石一恵や偶然の出会いが待っている田畑智子やその他映画に登場する端役に至るまで矢口監督は気を配っていて、細部の描き方の綿密さがこの映画を成功に導いたのだなと思う。「ウォーターボーイズ」よりも「スウィングガールズ」よりもよくまとまった映画なのである。
2008/11/02(日)「闇の子供たち」
原作を読んでると、映画を見ながら物語を反芻する感じにしかならないが、阪本順治流のアレンジが何カ所かあった。エイズにかかった少女を音羽恵子(宮崎あおい)がゴミ運搬車から助ける場面と主人公を新聞記者の南部(江口洋介)に変えて、ラストにその過去をフラッシュバックさせる場面。どちらも阪本順治のエンタテインメント気質が表れた場面で、原作にはない。このラストはサイコな映画によくあるもので、それはないだろうと思ったが、トークショーでの監督の話によれば、物語を遠い国で起こったことと思って欲しくなかったための措置だとか。それにしても、これがあることで社会派作品から一瞬、サイコドラマに変わってしまった印象がある。
阪本順治の映画としては「KT」の系譜に属する作品だが、題材の重たさに比べて出来の方は水準作にとどまった。重たいといっても原作よりはるかに軽いのはペドファイルたちの子供に対する性行為が具体的に描かれないからだ。これは仕方がない。粘膜が割け、肉がきしむような過激な描写が映画でできるわけがない。その代わりに映画は白ブタのような白人男性やオタクのような日本人を出すことで、醜悪さと嫌悪感を表現している。
映画を撮るに当たって、監督は現地で児童買春と臓器移植について取材したそうだ。原作に書かれたことは10年から15年前のもので、今は子供に足かせをはめて暗い地下室に閉じ込めるようなことはやっていないという。だから映画には取材で分かったことも取り入れられている。それならば、取材を元に映画を構成しても良かったような気がする。なぜドキュメンタリーを撮らなかったのかという点について、監督は「自分はフィクションしか撮ったことはないし、ノンフィクションであっても監督の主観は入る。ドキュメンタリーだったら、少女が這いながら自宅に帰る場面は撮れない」と説明した。それと宮崎あおいや妻夫木聡のファンが映画を見に来て、この問題について知るという効果も確かにあるだろう。
ただし、原作を読んで映画を見ても僕は臓器移植については懐疑的だ。大きな災害の後に子供がいなくなることが多いそうで、そうやって連れ去られた子供たちは売春と移植組に分けられる、と監督は言ったけれども、そこを具体的に映画の中で明らかにしてくれないと、信用できないのである。こういう部分はノンフィクションじゃないと説得力がない。まあ、原作にも臓器移植の具体的な描写はないので、これは現地の警察の捜査を待たないと、無理なのだろう。
原作には出てこない心臓移植を受ける少年の父親役を佐藤浩市がさらりと好演。ゴミ運搬車から少女を助ける場面で宮崎あおいが殴られて倒れても反撃に転じる場面はいかにも阪本順治のタッチになっていた。
2008/10/26(日)「パコと魔法の絵本」

やっぱり中島哲也の映画は見逃せないと思い直し、キネ旬でも褒めてあったので見に行く。もう公開も終わり間近にしてはまずまずの入りだった。映画は「嫌われ松子の一生」ほどではないが、まあ面白かったというのが率直な感想。まるで舞台のような展開だなと思ったら、原作は舞台劇なのだそうだ。ディズニー風の音楽とともに始まるにもかかわらず、過剰なメイクと極彩色の色遣い、乱暴な言葉遣い、過激な描写、脱ドラマとユーモアが混ざり合って、いかにも中島哲也らしいポップさだ。でも本筋は真っ当で、ほろりときそうなラストをひっくり返し、さらにほろりとさせるように持って行くのがうまい。もっともこれは元の舞台の台本通りなのだろう。前半をコンパクトにして「松子」のように歌を散りばめてくれたら言うことはなかった。「松子」のようなミュージカルを期待していたのだ。
原作は後藤ひろひとの「MIDSUMMER CAROL ~ガマ王子VSザリガニ魔人~」。CAROLで分かるようにこれは「クリスマス・キャロル」にインスパイアされた物語だ。主人公の大貫(役所広司)は一人で会社を興し、仕事一筋に生きて会社を大きくしたが、発作で倒れて入院。「お前が私を知ってるってだけで腹が立つ」と周囲に当たり散らしているスクルージのような男で、周囲からはクソジジイと呼ばれている。ある日、大貫は病院の庭で「ガマ王子とザリガニ魔人」という絵本を読んでいる女の子パコ(アヤカ・ウィルソン)に出会う。
パコは交通事故の後遺症で1日しか記憶が持たなかった。だから大貫の大事なライターを持っていて、大貫からぶたれても翌日は天使のような笑顔を見せる。パコの1日は誕生日で、ママから「毎日読んでね」とプレゼントされた絵本を毎日読んでいるのだった。両親は事故で死んだが、パコはそれを知らず「ママ、会いに来てくれないかな」と願っている。パコの頬に手を触れた大貫に対してパコは「おじさん、昨日もパコに触ったわね」と言う。大貫はパコに思い出を残してやりたいと病院の人たちにパコの絵本を演じてくれるように頼む。
「先生、俺は子供時代から泣いたことがないから涙の止め方が分からない。どうやったら止まるんだ」
「簡単ですよ。いっぱい泣けばいいんです」
パコの身の上に涙した大貫に病院の院長(上川隆也)が言う。いっぱい泣いて、涙が涸れるまで泣いたら、涙は自然に止まる。泣きたいときには泣けばいいという当たり前のことをさらりと言うセリフが心に残る。そのほか、ユーモアの中での真実みのあるセリフが詰まっていて、これまた中島哲也らしいなと思わせる。
「ざけんじゃねえよ」と言いつつ、子供時代の不幸と唯一の希望だった思い出を、その希望を与えてくれた当事者で今は薬物依存症の入院患者(妻夫木聡)に語る土屋アンナのまるで「下妻物語」の延長のような弾けた役柄が良い。小池栄子の歯がギザギザですぐにかみつく凶暴な看護師も良い。残念なのは何回も見せられた予告編で物語の大筋が分かり、本編にはそれを大きく超える感動がなかったことか。パコのために病院全体をセットにして絵本の扮装をした登場人物が所々で3DCGに変わるクライマックスもこちらのイメージ以上のものはなかった。
出演者は唯一過剰なメイクのない劇団ひとりや過剰だらけの阿部サダヲ、加瀬亮、國村隼などいずれも好演していた。
2008/10/12(日)「容疑者Xの献身」
原作の映画化としては成功の部類だと思う。といっても僕は原作にはそんなに思い入れはない。トリックの部分で感心しただけである。
原作にほぼ忠実な映画化で、「県庁の星」の西谷弘は今回も手堅い演出を見せている。これ、原作ファンにも不満はないのではないか。なんと言っても松雪泰子と堤真一がよろしい。ラストの慟哭の場面は切実さが足りない感じはあるが、我慢できる範囲内。原作もそうだが、この話は湯川(福山雅治)がメインではなく、この2人が中心なので、それ相応の演技力がいるのだ。大学時代は数学の天才と言われたのに今は冴えない中年の高校教師に堤真一はリアリティーを与えている。松雪泰子はどんどん良くなる感じ。
問題は容疑者Xの動機の部分の弱さか。これは原作にも感じたが、もっともっとキャラクターを描き込むべきだった。なぜ自殺しようとしたのか、隣に住む親子のどこが生きる希望を持たせてくれたのかを詳細に描かないと、殺人の動機に説得力がないのだ。原作の感想について、どう書いたか調べたら、こう書いていた。
「よくできた本格ミステリで1位にも異論はないが、ぜいたくを言えば、もっと石神のキャラクターを掘り下げた方が良かったと思う。キャラクターよりもまだトリックの方が浮いて見えるのだ。社会に認められなかった天才数学者の悲哀をもっと掘り下げれば、小説としての完成度をさらに高めることができたのではないかと思う。これの倍ぐらいの長さになってもかまわないから、そうした部分を詳細に描いた方が良かった。一気に読まされてある程度満足したにもかかわらず、そんな思いが残った」。
映画もこうした部分の弱さを克服できていなかったわけである。
柴咲コウは相変わらず目の演技に細かさがある。所轄の刑事の描写に「踊る大捜査線」っぽい部分があるのはフジテレビが絡んでいるからか。福山雅治の演技も僕はありだと思う。脚本と音楽も手堅くまとまった佳作。見て損はないです。というか、ほとんど失敗する本格ミステリの映画化としては褒めていい出来だと思う。
2008/09/15(月)「おくりびと」
 モントリオール世界映画祭でグランプリ、アカデミー外国語映画賞の日本代表作品、中国最大の映画賞である金鶏百花賞の観客賞で作品、監督、主演男優賞を受賞した。モントリオールに関しては海外の評価なんて分からんぞ、と思っていたのだが、実際に映画を見て、これは海外でも評価されるのも当然だと思った。死者の尊厳を大事にする納棺師の仕事はどこの国でも共感を得るのに違いない。家族を亡くして悲しみに沈む遺族の気持ちを損なわないように、慎重な振る舞いでてきぱきと死体の身繕いと化粧を施す本木雅弘が素晴らしい。その所作の中にさまざまな思いが交錯するから素晴らしいのだ。「5分遅れたぞ。あんたら死体で食ってんだろう」と遅刻を怒っていた妻を亡くした男(山田辰夫)は納棺師2人の仕事ぶりを見て、「家内は一番きれいだった。ありがとう」と礼を言うことになる。それが納得できるほど死者への敬意に満ちた仕事なのである。そして納棺師の仕事に気が進まなかった主人公はこれをきっかけに仕事に誇りを持つようになる。
モントリオール世界映画祭でグランプリ、アカデミー外国語映画賞の日本代表作品、中国最大の映画賞である金鶏百花賞の観客賞で作品、監督、主演男優賞を受賞した。モントリオールに関しては海外の評価なんて分からんぞ、と思っていたのだが、実際に映画を見て、これは海外でも評価されるのも当然だと思った。死者の尊厳を大事にする納棺師の仕事はどこの国でも共感を得るのに違いない。家族を亡くして悲しみに沈む遺族の気持ちを損なわないように、慎重な振る舞いでてきぱきと死体の身繕いと化粧を施す本木雅弘が素晴らしい。その所作の中にさまざまな思いが交錯するから素晴らしいのだ。「5分遅れたぞ。あんたら死体で食ってんだろう」と遅刻を怒っていた妻を亡くした男(山田辰夫)は納棺師2人の仕事ぶりを見て、「家内は一番きれいだった。ありがとう」と礼を言うことになる。それが納得できるほど死者への敬意に満ちた仕事なのである。そして納棺師の仕事に気が進まなかった主人公はこれをきっかけに仕事に誇りを持つようになる。
チェロ奏者だった主人公が楽団の解散に伴って、妻(広末涼子)と一緒に故郷の山形に帰る。「旅のお手伝い」と書かれた広告でNKエージェントという小さな会社に就職面接に行くと、社長の山崎努は一発で採用を決める。ところが、広告は「旅立ちのお手伝い」の誤植で、NKは納棺の略ということが分かる。高い給与もあって、主人公は妻には仕事の内容を伏せて納棺師として働くことになる。というこの出だしはいかにも滝田洋二郎の映画らしいユーモアだ。映画はその後もユーモアを散りばめ、納棺師の仕事とそれに理解のない周辺を描写しながら、成長する主人公の姿を描いていく。
題材のユニークさを除けば、これが初の映画という放送作家・小山薫堂の脚本はオーソドックスなまとめ方で特に際だった部分はないように思う。クライマックスがこうなるのはほぼ想像がついた。優れているのはまとめ方ではなく、具体的なエピソード。主人公が6歳のころに家を出た父親が主人公と交わした石文(いしぶみ)を大事に持っているのを見せる場面は、ここだけで家を出た後の父親の孤独な生き方が浮き彫りになる名シーンだ。同時にここには父親と息子の届かなかったお互いの思いが凝縮されている。
何よりの成功は出演者たちの充実した演技にあるだろう。山崎努のさすがの演技をはじめ、事務所の余貴美子、銭湯のおばちゃんの吉行和子、そこに通う笹野高史、幼なじみの杉本哲多などなどがそれぞれに場面を背負って、映画を際だたせている。もちろん、本木雅弘は主演男優賞候補の筆頭だろう。チェロの演奏も納棺師としての仕事もプロでやっていけそうなぐらいにリアルだ。真剣に役柄に取り組む俳優だなと改めて思った。端役かと思われた余貴美子にはちゃんとクライマックス前に見せ場が用意されており、これがまた泣かせる。「行ってあげて!」というセリフが自身の生き方と重なって泣かせるのだ。唯一、あまり評価の高くない広末涼子も僕は悪くないと思った。チェロを中心にした久石譲の音楽も久石作品の中でベストではないかと思える出来栄えである。
こうした要素のどれが欠けても映画はこれほどの作品にはならなかっただろう。地味な題材でありながら、笑って泣いてというエンタテインメント映画の王道として仕上げられており、多くの人に感動を与え、愛される作品だと思う。「陰陽師」のころはどうなることかと思ったが、滝田洋二郎は昨年の「バッテリー」に続いて絶好調と言うほかない。大作ではなく、身近な題材の方が素質を発揮する監督なのだと思う。