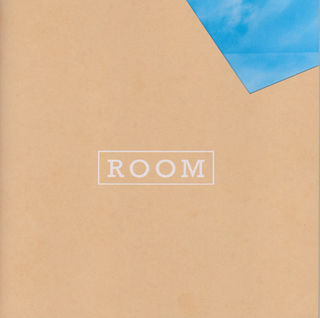2016/05/28(土)「ルーム」
狭い部屋に7年間監禁された母親ジョイ(ブリー・ラーソン)とその子どもジャック(ジェイコブ・トレンブレイ)。ジャックは5歳になったばかりだ。ジョイはこの部屋でジャックを産んだ。ジャックの父親はジョイを拉致した犯人でオールド・ニック(ショーン・ブリジャース)と呼ばれる(本名は分からない)。部屋の中で物語が進行する前半を見ながら思ったのは、この状況は暴力的な夫から支配され、逃れられない母子と容易に置き換えられるということ。そして、部屋の中が世界のすべてと思っている子どもはSFにありそうな存在だということだ。
エマ・ドナヒューの原作は部屋の中を描く「インサイド」と脱出後を描く「アウトサイド」の構成になっているそうだ(この原作、2014年に文庫が出たが、現在絶版で読めない。映画公開に合わせて復刊できないのは出版不況のためか)。ブッカー賞の候補になったという原作が面白いのだろうが、この構成を踏襲した映画も見ていて前のめりになるぐらい面白い。前半と後半で面白さの質も異なる。
部屋は3.3平方メートルしかないらしい。トイレと浴槽、台所設備はあるが、窓は空しか見えない天窓だけ。ドアは暗証番号を入れないと開かない。閉所恐怖症の人には耐えられないような狭さだ(ジョイが大声で叫ぶ場面がある)。外の世界を知らないジャックはテレビの内容を本物ではないと思っている(そう教えられている)。本物なのは自分と母親だけ。ジョイはそんなジャックを頼みにして「モンテ・クリスト伯」を参考に脱出計画を立てる。
この中盤の場面がとてもスリリングで感動的だ。高熱を出した(ふりをした)後、オールド・ニックに死んだと思わせたジャックは絨毯にぐるぐる巻きにされてピックアップトラックに乗せられる。走り始めて3回目に一時停止したところでトラックを飛び降りるが、オールド・ニックに気づかれ、捕まってしまう。そこに通報を受けた警官がやって来る。女性警官パーカー(アマンダ・ブルーゲル)はジャックの話を根気よく聞いて、母親が監禁されているらしい場所の手がかりを得るのだ。
ここから映画は社会に復帰した母子を描く。ジョイの両親(ウィリアム・H・メイシー、ジョーン・アレン)は離婚し、母親は別の男と暮らしていた。17歳で拉致され、社会と隔絶された7年間を過ごしたジョイは徐々に精神的にまいっていく。ジャックは初めて知る世界の大きさを少しずつ理解し始める。ジョイの父親は犯人の子どもであるジャックをまともに見られない。ジョイは7年間を耐えられたのはジャックがいたからこそで、ジャックに父親はいないと思っている。映画がキワモノにならず、心を揺さぶる作品に仕上がったのは母子を見つめ続ける視点に揺るぎがないからだ。
「ショート・ターム」(2013年)で注目されたブリー・ラーソンはこの映画でアカデミー主演女優賞を受賞した。確かに好演しているが、同賞にノミネートされた「キャロル」のケイト・ブランシェットや「さざなみ」のシャーロット・ランプリングに比べて演技的に際立って優れたところはないように思う。映画の出来がとても良かったことが受賞につながったのではないか。ラーソンよりもジャックを演じたジェイコブ・トレンブレイの方が映画を支えている感じだ。監督はこれが長編5作目のレニー・アブラハムソン。脚本に原作者が加わったことも功を奏したのだろう。
2016/05/27(金)創刊60周年
ミステリ・マガジンのこと。創刊は1956年7月号だそうで、2016年7月号で創刊60年になった。ミステリ・マガジンを毎号欠かさずに買うようになったのは1983年ごろからだから33年。半分強は読んでいることになる。といっても掲載されている短編はほとんど読まない。コラムと書評目的で毎号買っている。
今号には過去に掲載したコラムが再録されていて、都筑道夫さんの「読ホリデイ」とか青木雨彦さんの「共犯関係」とか瀬戸川猛さんの「夢想の研究」とか懐かしくてたまらない。「読ホリデイ」はディーン・クーンツの「十二月の扉」を取り上げていて、クーンツとスティーブン・キングの比較に関しては今読んでもそのまま通じる。年月がたったからといって、通用しなくなるような批評は批評とは言えないのだ。
懐かしいのはいいのだが、初掲載がいつなのか書かれていないのは残念。これはしっかり書いておいてくださいよ、早川書房さん。
僕が購読し始めて間もないころ、ミステリ・マガジンは長編分載を始めた。その頃に読んで、文庫になってまた読んで、昨年新訳で再刊されてまたまた読んだのがマーガレット・ミラーの「まるで天使のような (創元推理文庫)」。ミステリ・マガジン掲載時に「パトリック、パトリック、オー・マイ・ゴッド、パトリック!」の場面で言いようのない感動を覚えた。昨年読み返した時にはこの場面の衝撃は分かっていたが、そこに至るまでの小説のうまさに感心させられた。この1作でミラーは夫のロス・マクドナルドの業績に匹敵すると思う。
それにしても、ミステリ・マガジンが隔月刊なのは物足りない。そろそろ月刊に戻してはどうでしょうかね。
2016/05/24(火)ドラマ「深夜食堂」
amazonプライムビデオに「深夜食堂」の第2シーズンまでが入ったので、毎日1、2話ずつ見ている。ほとんど見たと思い込んでいたが、それは第2シーズンと第3シーズンの方で第1シーズンはあまり見ていなかった。第5話「バターライス」とか、第6話「カツ丼」とか、しみじみといい話だなと思う。
「バターライス」はグルメ評論家(岩松了)にまつわる話。「めしや」に連れてこられた評論家が、流しの歌手ゴローさん(あがた森魚)がバターライスを食べるのを見て、自分も食べる。それ以来、「めしや」によく来るようになる。実は評論家とゴローさんには貧しい頃にあるつながりがあった。
バターライスはご飯にバターを乗せて、30秒待ち、醤油を少しだけかけたもの。料理と言うには簡単すぎるのだけれど、そういう食べ方、つましい食事が思い出につながるものなのだ。幼い頃によく食べた料理は郷愁を呼び起こす。韓国や台湾でも人気を集め、独自にドラマ化もされているのは、食に関する思いがどの国でも共通するからなのだろう。
去年の映画も良かったが、好評を受けて「続・深夜食堂」が11月に公開されるそうだ。これは楽しみ。ドラマの方はNetflixで10月から始まるとのこと。できれば、地上波でやってほしかったけど、これだけでNetflixに入ろうかという気になる。
【amazonビデオ】深夜食堂
2016/05/21(土)「アイアムアヒーロー」
漫画家アシスタントの主人公・鈴木英雄(大泉洋)が同棲していた恋人てっこ(片瀬那奈)から追い出されたアパートに行き、郵便受けから中を覗くと、ベッドに寝ていたてっこが体をくねらせたありえない動きで玄関まで這ってきて、鍵のかかったドアをぶち破って襲ってくる。ここから漫画家(マキタスポーツ)の家での惨劇→通りのあちこちでゾンビに襲われる人々のパニック→タクシーで逃げたら同乗の男がゾンビ化→噛まれた運転手もゾンビ化→高速道路を暴走するタクシーが横転と、すごい疾走感で映画は進む。前半は快調そのものだ。
ゾンビはZQN(ゾキュン)と呼ばれ、そのウイルスは風邪のように感染するらしい。空気の薄い所では感染しないと聞いた英雄はタクシーに同乗した女子高生の比呂美(有村架純)と富士へ向かう。比呂美は近所の赤ちゃんに噛まれており、半分ZQNになってしまう。この半分というのはウェズリー・スナイプス主演「ブレイド」(1998年)など他の作品にもよくある設定で、他の例に漏れず比呂美は超人的な力を発揮する。富士の裾野のショッピングモールに行くと、そこには元看護士の藪(長澤まさみ)らZQNを逃れてモールの屋上に住む集団がいた。リーダーの伊浦(吉沢悠)に統率された集団かと思えたが、仲間割れが始まる。
韓国の閉鎖されたショッピングモールでロケしたという後半は、よくあるゾンビもののパターンになっていくのだが、それでもゾンビの描写はオリジナリティーにあふれる。クモのような動きのゾンビがいたり、走り高跳び選手で頭を凹ませたゾンビがいたりする。動作も素早いものからゆっくりふらふらしたものまでさまざまだ。もちろん、噛まれて感染するのはゾンビ映画のお約束。頭を砕けば、絶命するのもお約束だ。そうしたゾンビ映画のルーティンを守りながら、これだけのオリジナリティーを出したのは大したものだと思う。
従来のゾンビ映画やテレビドラマ「ウォーキング・デッド」などではゾンビの造型に関しては同工異曲で、違いは動くのが速いか遅いかぐらいしかなかった。海外の3つの映画祭で評価されたのは、ゾンビのオリジナリティーと前半のスピード感のためだろう。大量に作られてやり尽くした観のあるゾンビ物のジャンルでもまだやれることはあるのだなと感心した。
花沢健吾の原作は家に1巻だけあったので見る前に読んだ。アシスタントの日常の中に異変が2つほどあり、英雄がアパートに行くところまでが描かれる。その先を読まなかったのは映画を見る上では正解だったかもしれない。ZQN化したてっこの変貌ぶりと動きは想像を超えていた。
佐藤信介監督の「GANTZ」(2011年)では容赦ない血みどろ残虐描写にびっくりしたが、この映画の後半はそれが延々と続く。それだけでなく、ユーモアも随所にあるのは主演を大泉洋にした効果だろう。話があまり進まないのが残念だが、原作もまだ完結していないのだから、仕方がない。このスタッフ、キャストで続きを撮ってほしいものだ。
2016/05/17(火)「64 ロクヨン 前編」
単行本で647ページの原作を前・後編として映画化するのは、最近の流行に乗っただけのようでどうかと思ったが、忠実に映画化しようとすれば、これぐらいの長さが必要ではある。前編は原作の3分の2あたりまでを映画化してある。ここまでに描かれるのは刑事部から警務部広報官に異動した主人公・三上義信(佐藤浩市)の記者クラブや上層部との確執と、ロクヨンに関わった人間たちの現在の姿だ。
原作が大きく動くのはこの後なので、1本の映画としてまとめるのは難しいところだが、交通重体事故の匿名発表をめぐる記者クラブとの対立をメインに持って来て、三上の独断でその解決を図る場面が前編のクライマックスとなっている。脚本にして9ページ、約9分間のこのシーンを支えるのは佐藤浩市の入魂の演技だ。原作以上に迫力と情感にあふれ、クライマックスとして有効に機能している。瀬々敬久監督の演出はこの場面に限らず、情感を込めたもので、他の出演者たちの好演も相まって感動的な映画に仕上がった。
原作はD県警シリーズだが、映画でこの名前はあり得ないから群馬県警になっている。ロクヨンとは昭和64年1月5日に発生した少女誘拐殺人事件。7歳の少女が誘拐され、身代金2000万円を奪われ、少女の死体が車のトランクから見つかった。事件の経過を冒頭で見せた後、映画は14年後に飛び、三上が雪の中、妻の美那子(夏川結衣)と死体の確認に行く場面となる。三上の一人娘あゆみ(芳根京子)は父親にそっくりな自分の容姿を嫌い、家出して行方が分からなくなっているのだ。
三上は家庭でも職場でも難題を抱えている。匿名発表をめぐって記者クラブは強く反発し、県警本部長あてに抗議文を出そうとする。ロクヨンの情報提供を呼びかけるという名目で警察庁長官の事件現場視察と、被害者の父親・雨宮(永瀬正敏)との面会の計画が持ち上がり、三上は雨宮と交渉するが断られてしまう。三上の同期で警務部調査官の二渡(仲村トオル)はロクヨンをめぐって不審な動きをしている。二渡の狙いは幸田メモと呼ばれるロクヨン捜査の重大な失敗を記したメモにあるらしい。さらに長官視察の本当の理由も明らかになってくる。記者たちは長官取材のボイコットを通告する。
瀬々監督はキネマ旬報のインタビューで「広報官の三上がいろんな敵と闘う『真吾十番勝負』みたいな話ですから、これは」と話しているが、まさにその通りの展開だ。ほとんど出ずっぱりの佐藤浩市は部分的にやや過剰な演技も目に付くが、映画を支える熱演を見せる。クライマックス、三上は独断で事故の第1当事者(加害者)の実名を発表した後、部下が調べた被害者・銘川老人の境遇について読み上げる。孤独な老人の境遇だけで胸を詰まらせるものがある。原作ではこう書かれている。
「これまでで一番の幸運は女房と出逢ったことだと言っていた。ずっと安月給で、二度も大病を患い、苦労を掛けっぱなしだったが文句一つ言わずに尽くしてくれた。温泉巡りはしたが、とうとう海外旅行には連れて行ってやれなかった。墓は立派なものを建てた。人生で家の次に大きな買物だったと言っていた。女房が死んでからはテレビばかり観ている。たいていはバラエティーをかけている。別に面白いわけではないが、賑やかなのがいいんだと言っていた」
不覚にも声が裏返った。
匿名発表と被害者の境遇にあまり関係はないと思えるが、三上は「生涯でたった一度、新聞に名前が載る機会を、それを目にした誰かが彼の死を悼む機会を、匿名問題の争いが奪った」と考える。
雨宮の自宅を二度目に訪れる場面もいい。三上は仏壇の遺影を見て、なぜか涙を流してしまう。涙の理由は原作にも明確には書かれていない。難しい場面だが、佐藤浩市は難なく乗り切っていて不自然さはなかった。
広報室勤務の綾野剛、榮倉奈々、金井勇太のほか、県警本部長の椎名桔平、警務部長の滝藤賢一、刑事部長の奥田瑛二など必死だったり、憎々しかったりする役柄をそれぞれが好演している。数多くの登場人物が織りなす人間ドラマとして見応えがあった。後編は一転してサスペンス調になり、原作とは変えた部分もあるという。公開を楽しみに待ちたい。