2005/11/26(土)「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」
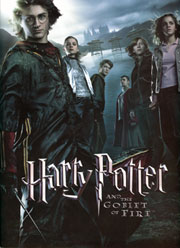 ハリー・ポッターシリーズの第4作。今回は「フォー・ウェディング」のマイク・ニューウェルが監督を務めた。毎度のことながら、2時間37分の上映時間は長すぎると思う(エンドクレジットが10分ほどあるのにもまいった)。毎回2時間を大幅に超える映画になるのはプロデューサーに「長くなければ大作ではない」という意識でもあるのだろう。この4作目も内容からすれば、2時間程度にまとめられる話である。ニューウェルの演出はとりあえず、字面を映像化してみました、といったレベル。VFXは水準的だし、演技力云々を別にすれば、主役の3人も僕は好きなのだが、映画にはエモーションが欠落している。ハリーの初恋もハリーとロンの仲違いも、ハーマイオニーとの関係もただたださらりと何の思い入れもなく描いただけ。心がこもっていない。ニューウェル、こういうファンタジーが本気で好きではないのに違いない。監督の人選を間違ったのが今回の敗因なのだと思う。
ハリー・ポッターシリーズの第4作。今回は「フォー・ウェディング」のマイク・ニューウェルが監督を務めた。毎度のことながら、2時間37分の上映時間は長すぎると思う(エンドクレジットが10分ほどあるのにもまいった)。毎回2時間を大幅に超える映画になるのはプロデューサーに「長くなければ大作ではない」という意識でもあるのだろう。この4作目も内容からすれば、2時間程度にまとめられる話である。ニューウェルの演出はとりあえず、字面を映像化してみました、といったレベル。VFXは水準的だし、演技力云々を別にすれば、主役の3人も僕は好きなのだが、映画にはエモーションが欠落している。ハリーの初恋もハリーとロンの仲違いも、ハーマイオニーとの関係もただたださらりと何の思い入れもなく描いただけ。心がこもっていない。ニューウェル、こういうファンタジーが本気で好きではないのに違いない。監督の人選を間違ったのが今回の敗因なのだと思う。
メインの話、というよりも、長い時間をかけて描かれるのは三大魔法学校対抗試合(トライウィザード・トーナメント)。危険を伴うために100年以上も禁止されていた試合が開催されることになり、17歳以上が出場するという条件にもかかわらず、炎のゴブレットに選ばれて14歳のハリー・ポッター(ダニエル・ラドクリフ)もホグワーツ魔法魔術学校を代表して出場することになる。ホグワーツのほか、対抗試合に出るのはボーバトン魔法アカデミーとダームストラング学院の代表。試合はドラゴン、水魔、迷路での戦いの3つである(どうでもいいが、日本語吹き替え版では水魔がスイマーに聞こえた)。出場者は魔法の杖と実力を頼りに勝ち抜いていかなければならない。
これに合わせて1作目から続く悪の権化ヴォルデモートとの確執が描かれる。シリーズ全体を眺めれば、ハリーの両親を殺したヴォルデモートとの対決が話の軸になっていくのはよく分かる。この映画の冒頭にヴォルデモートは登場し、クライマックスもヴォルデモートの復活になっており、この部分に関しては大変面白かった。ただし、こういう構成ではそれまでの対抗試合の話が結局のところ、刺身のツマみたいになってしまうのだ。映画を見終わってみれば、対抗試合がどのような結果になろうと、大した問題じゃなくなる。困るのは、このツマがメインの刺身よりも大きいこと。本筋に導くための脇筋なのに、これでは本末転倒としか思えない。
これは脚本が悪いのだろうと思って、脚本家の名前を見たら、なんと「恋のゆくえ ファビュラス・ベイカー・ボーイズ」(1989年)のスティーブ・クローブスではないか。というか、クローブス、1作目からずっとこのシリーズの脚本を書いている。知らなかった(ではなく、忘れていた。1作目の映画評を読み返してみたら、言及していた)。個人的には大好きなあの佳作を撮った監督がなぜ、この程度の脚本しか書けないのか。オリジナルではない脚色の難しさというのは確かにあるのだろうが、あまりと言えばあまりな出来である。対抗試合はあっさりすませてハリーとヴォルデモートの対決をあくまでもメインに置いて書くべきだった。
ヴォルデモートを演じるのはレイフ・ファインズ。鼻のつぶれたメイクでハンサムなファインズにはとても見えない。次作以降、出番も多くなるのだろうからこその演技派のキャスティングなのだろう。その次作「不死鳥の騎士団」を成功させたいなら、まず脚本をじっくり書かせたうえで、ファンタジーに理解のある監督を選んで欲しいものだ。上映時間も2時間以内に収めることを切に望む。その方が絶対に引き締まった印象になる。そうしないと、このシリーズは所詮子供向けの大味なシリーズということになってしまうだろう。
2005/11/25(金)「仄暗い水の底から」
タイムリーに放映してくれた。「ダーク・ウォーター」と比べてみると、こちらの方がやはり怖い。単に子供が赤いバッグを持っているだけで、どうしてあんなに不気味な演出ができるのか。中田秀夫はやはり恐怖の演出、不気味さの演出ではうまい。これを見ると、たかが子供の霊だから怖くないとは言えなくなる。たたみかけるようなクライマックス、あの緑色の手が首に巻き付く演出などは大したものだと思う。黒木瞳の神経症的な演技も悪くない。
僕はこの映画、全然見ていないと思っていたが、ラストシーンだけは覚えていた。いや、ラストシーンだけ見ていたのを思い出した。ここは怖さと母娘の愛情が絶妙にブレンドした場面で、「ダーク・ウォーター」のそれより優れている。
ウォルター・サレスはホラーの演出が苦手だったのだろうなと思う。俳優の演技とか、映画の丁寧さとか、映画の格とかすべて勝っているのに、怖さと面白さでは中田版に負けてしまった。クライマックスを分かりやすく変えたのも敗因なのだろう。
2005/11/23(水)「キングダム・オブ・ヘブン」
 今年前半に見逃した映画をDVDで追いかけることにした。これは何となく、史劇に食指が動かなかったので見なかったのだが、映画館で見るべきでした。
今年前半に見逃した映画をDVDで追いかけることにした。これは何となく、史劇に食指が動かなかったので見なかったのだが、映画館で見るべきでした。
キリスト教徒とイスラム教徒の軍事的抑制で危ういバランスが取れていた12世紀のエルサレムを舞台にしたドラマ。キリスト教徒の王・ボードワン4世の死で、バランスが崩れ、戦闘が始まる。テレビの画面で見ていると、美術やセットなどがいかに素晴らしくても、主人公がエルサレムへ行くまでの前半は何ということもない映画に感じられるが、クライマックスのエルサレム攻防の戦闘シーンが凄かった。「ロード・オブ・ザ・リング」に匹敵するスペクタクル。CGで描いたと思われる兵士の数の多さにはもう驚かないけれど、投石の迫力が凄いし、画面の構図や映像の撮り方がオリジナリティに富んでいる。
さすがにリドリー・スコットは映像派の監督だなと再認識した。個人的にはベストテンに入れてもいいかと思ったほど。中盤の戦闘シーンを省略したのは、見ている間は「影武者」を参考にしたのかと思ったが、クライマックスの迫力を減じないためではないかと思い直した。
主演は「ロード・オブ・ザ・リング」のレゴラスことオーランド・ブルーム。こうした超大作の主演にはちょっと線の細さを感じるが、無難に演じている。聖地を守るためではなく、そこに住む民を守るために戦うという主人公の設定がいい。
2005/11/22(火)「ダーク・ウォーター」
 鈴木光司原作、中田秀夫監督の「仄暗い水の底から」(2002年)のリメイク。監督は「セントラル・ステーション」「モーターサイクル・ダイアリーズ」のウォルター・サレス。原版を見ていないので比較しようがないが、これはホラーというよりも母娘の絆を描いた映画と言える。ホラーとしては理に落ちた分、怖くなくなっている。物語に納得してしまえるホラーは怖くないのである。不条理の怖さ、理由のない怖さ、問答無用の怖さ、といったものはこの映画にはない。子供の頃に母親から憎まれ、捨てられたヒロインの精神状態の不安定さを利用すれば、そうした怖さが表現できたと思うが、サレスはそういう演出をしていない。睡眠薬で丸一日眠ってしまったヒロインが見る悪夢のシーンなどはもっと怖くできるのに、と思う。黒い水(ダーク・ウォーター)が部屋を浸食するようにヒロインの精神も浸食されていくような演出がもっと欲しいところではある。だから、この映画を見ると、たかが子供の霊だから怖くないんだよなということになってしまう。同じくハリウッド進出監督のホラーということで、見ていて連想したのはアレハンドロ・アメナーバルの「アザーズ」だが、あの映画で怖さ以上に魅力的だった情緒的な悲劇性もまた、この映画には薄い。映画の丁寧な作りとジェニファー・コネリーの好演に感心はしたが、映画としては水準以上のものにはなっていない。
鈴木光司原作、中田秀夫監督の「仄暗い水の底から」(2002年)のリメイク。監督は「セントラル・ステーション」「モーターサイクル・ダイアリーズ」のウォルター・サレス。原版を見ていないので比較しようがないが、これはホラーというよりも母娘の絆を描いた映画と言える。ホラーとしては理に落ちた分、怖くなくなっている。物語に納得してしまえるホラーは怖くないのである。不条理の怖さ、理由のない怖さ、問答無用の怖さ、といったものはこの映画にはない。子供の頃に母親から憎まれ、捨てられたヒロインの精神状態の不安定さを利用すれば、そうした怖さが表現できたと思うが、サレスはそういう演出をしていない。睡眠薬で丸一日眠ってしまったヒロインが見る悪夢のシーンなどはもっと怖くできるのに、と思う。黒い水(ダーク・ウォーター)が部屋を浸食するようにヒロインの精神も浸食されていくような演出がもっと欲しいところではある。だから、この映画を見ると、たかが子供の霊だから怖くないんだよなということになってしまう。同じくハリウッド進出監督のホラーということで、見ていて連想したのはアレハンドロ・アメナーバルの「アザーズ」だが、あの映画で怖さ以上に魅力的だった情緒的な悲劇性もまた、この映画には薄い。映画の丁寧な作りとジェニファー・コネリーの好演に感心はしたが、映画としては水準以上のものにはなっていない。
離婚調停中のダリア(ジェニファー・コネリー)は一人娘のセシリア(アリエル・ゲイド)とルーズベルト島のアパートに引っ越してくる。ダリアは夫のカイル(ダグレイ・スコット)とセシリアの親権を争っているが、ニューヨークのアパートは家賃が高すぎてダリアには手が届かなかった。アパートは古ぼけており、管理人のヴェック(ピート・ポスルスウェイト)は愛想が良くない。親子はアパートに入った途端、気味の悪さを感じるが、家賃が安かったこともあって入居を決めた。部屋は9階。ダリアは天井には黒いシミがあるのを見つける。上の階から水が漏れているらしい。上の物音も響いてくるが、10階の部屋は空き部屋だという。いったん修理した天井のシミからは再び黒い水がしたたってくる。10階の部屋に行ってみたダリアは部屋が一面、黒い水で水浸しになっているのを見る。そしてセシリアは見えない友人ナターシャと話をするようになる。地下のコインランドリー室では洗濯機から黒い水が噴き出す。不思議な出来事と夫との親権争いが徐々にダリアを精神的に追いつめていく。
雨がしとしとと降り続く場面が象徴するように映画には湿っぽい雰囲気が充満している。それはダリアの幼少期からの不幸な境遇にも通じており、ダリアは今の娘との幸せを守ろうと必死になっている。コネリーは実際に2人の子供の母親だけあって、そのあたりの母親の愛情についてはうまく表現している。映画で惜しいのは語り口がやや一本調子になってしまったこと。これはストーリーと関係するが、途中で大きな転換の場面が欲しくなってくる。丁寧に撮った作品が必ずしも傑作になるわけではないのである。物語自体の面白さがやはり必要なのだろう。ラファエル・イグレシアスの脚本は原作(短編)を膨らまし切れていないように思う。
いい加減な不動産屋のジョン・C・ライリーといつも車の中で仕事をしている弁護士のティム・ロスのキャラクターは面白かった。ピート・ポスルスウェイトも含めて、この映画、役者の演技に関しては文句を付ける部分はない。
2005/11/21(月)「大停電の夜に」
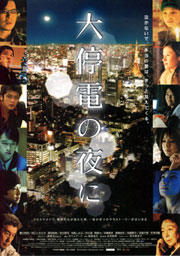 クリスマス・イブ、停電となった東京で語られる6組の男女の物語。もっともクリスマスらしいのは吉川晃司と寺島しのぶのエピソードで、これは終盤に吉川晃司がサンタクロースの格好をするためでもあるが、海外の小説にはよくあるクリスマス・ストーリーっぽい話になっている。寺島しのぶの語らない言葉(視線)で吉川晃司にすべてが分かるという場面も良かった。この2人の出番は少ないが、12人の出演者の中では一歩抜けている演技だと思う。路地裏にある流行らないジャズバーの豊川悦司とロウソク店の田畑智子が絡む話もいい。これにクライマックスに意外な人間関係が明らかになる原田知世の素敵な雰囲気までが、この映画の優れた部分と感じた。
クリスマス・イブ、停電となった東京で語られる6組の男女の物語。もっともクリスマスらしいのは吉川晃司と寺島しのぶのエピソードで、これは終盤に吉川晃司がサンタクロースの格好をするためでもあるが、海外の小説にはよくあるクリスマス・ストーリーっぽい話になっている。寺島しのぶの語らない言葉(視線)で吉川晃司にすべてが分かるという場面も良かった。この2人の出番は少ないが、12人の出演者の中では一歩抜けている演技だと思う。路地裏にある流行らないジャズバーの豊川悦司とロウソク店の田畑智子が絡む話もいい。これにクライマックスに意外な人間関係が明らかになる原田知世の素敵な雰囲気までが、この映画の優れた部分と感じた。
全体的には6つの話を2時間13分で語るのには少し無理があり、田口トモロヲが3つの話に絡むのは時間を節約するためではないかと思えてくる。田口トモロヲにそれほどの魅力はないし(普通にハンサムな役者の方が説得力があったと思う)、バラバラと思えた人間関係があまりに接近してくると、話自体のスケールが小さくなるのだ。それと関係するが、こういうエピソード集では最後に収斂させていくものが必要で、それがこの映画では豊川悦司のバーになっている。この場面はもっと簡単でも良かったと思う。この種の映画では成功作の「ラブ・アクチュアリー」が優れていたのは登場人物全員がそろうラストの空港の場面の前にそれぞれのクライマックスを用意していたからで、ラストはクリスマスの幸福感のみに集約されていた。脚本(相沢友子と共同)・監督の源孝志の都会的なセンスは買うけれど、こういう話をうまく映画化するにはさらに脚本を練り上げることが必要のようだ。
映画の基になったのは監督の源孝志が2年前に撮ったNHKテレビのドキュメンタリー「N.Y.大停電の夜に」だという。それを東京に置き換えて作ったのがこの話で、クリスマスに設定した意味はそれほど大きくない。一般的なクリスマスの光景が描かれないのはそのためだろう。6つのエピソードそれぞれにうまく考えてあるが、唯一、設定に無理があると感じたのはベテランの宇津井健と淡島千景夫婦の話。淡島千景は結婚前に不倫の恋をして子供を産んでいた。その子供から連絡があったことで、結婚45年目にして宇津井健に初めて告白するのだが、宇津井健が結婚当時にそれに気づかなかったというのはおかしい。ここは男女を入れ替えた方が自然だった。あるいは知っていて知らないふりをしていたとかにしておいた方が良かっただろう。
豊川悦司と田畑智子のエピソードでは豊川のキザさよりも田畑のうまさに感心した。ジャズバーとロウソク店は向かい合わせにあり、田畑が以前から豊川に秘かに思いを寄せていたことが徐々に明らかになる。この脚本、こういう部分がとてもうまいと思う。語らない言葉、秘めた思い、そういう部分をうまく表現している。それは原田知世のエピソードにも言える。原田知世は夫の不倫に悩んで秘かに離婚届を用意しているが、いったんは外食の約束をキャンセルした夫が早く帰ってきたことで、修復のきっかけが生まれる。せっかくクリスマスに設定したのだから、エピソードに少しはミラクルなあるいはファンタスティックな出来事も欲しいと僕は思うが、相沢友子・源孝志のコンビは人間の力による奇跡の方を選んだのだろう。このコンビ(筆名はカリュアード)の脚本で次作を見てみたいと思う。
それにしても久しぶりに見た原田知世は良かった。20代後半から現在まで映画出演が少ないのがもったいないと感じるほど。キネ旬で河原晶子が「『シェルブールの雨傘』のドヌーヴの気配がある」と評していたが、その通り。もっと映画に出すべきではないか。