2026/02/08(日)「トゥギャザー」ほか(2月第1週のレビュー)
「トゥギャザー」

ミュージシャン志望のティム(デイヴ・フランコ)と小学校教師のミリー(アリソン・ブリー)は、住み慣れた都会を離れ、田舎の一軒家に移り住む。森の中で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごす羽目に。その洞窟は教会の廃墟のようだった。2人は渇きに耐えられず、洞窟にたまっていた水を飲んだことで日常が暗転していく。シャワーを浴びていたティムは意識が混濁し、身体が勝手に暴走する。その異変はミリーにも発生。磁力に引き寄せられるように、2人の体は引き合うようになる。
キスすると下唇がくっつく。セックスで抜けなくなる。手が融合してしまう、と次第に現象がエスカレートしていきます。原因は洞窟にあった教会、新興宗教にあるらしいことが分かります。この宗教、プラトンの「饗宴」にあるアンドロギュニュス(両性具有)のように、かつて人間は手足が4つ、顔が2つある存在だったが、神の力で2つに引き裂かれたということを教義にしていて、男女がくっついた姿が正常とを信じています。
神のような超常的な存在は出てこないので、詳しい仕組みは説明されません(できませんよね)。2人には決着がつきますが、物語自体は何も解決しません。続編を作ってもおかしくない終わり方でした。主演の2人は実生活でも夫婦だそうです。
監督はオーストラリア出身で、俳優、作曲家、VFXアーティストでもあるマイケル・シャンクス。影響を受けた作品として「遊星からの物体X」「ザ・フライ」「エイリアン」のほか、黒沢清監督の「CURE」を挙げています。
IMDb6.7、メタスコア75点、ロッテントマト89%。
▼観客3人(公開初日の午前)1時間41分。
「グッドワン」

監督のインディア・ドナルドソンは「追いつめられて」(1987年)や「世界最速のインディアン」(2005年)などの傑作を撮ったロジャー・ドナルドソンの娘。父親とは違ったタイプの映画を目指しているようで、ケイリー・ライカートやセリーヌ・シアマ、マイク・リーの作品を指針としているそうです。
それが端的に表れているのがマットの不用意な言葉でサムが気分を害する終盤のシーン。マットにとっては冗談で済ませられる言葉でも、サムはその言葉自体が自分を侮辱するもの、とても許せない言葉であり、その後、口を利かなくなります。
クリスとマットの言動を見ていると、十代の少年と変わらないなと思える部分があり、「大人は私が思うより大人じゃない」という予告編でも流れたことをサムは知るわけです。だからといって、失礼な言動が許せるわけではありません。といっても、サムのちょっとした仕返しのためのいたずらも微笑ましいものではありました。
3人がキャンプに行く時に使う車はスバルのアウトバックのようです。
IMDb6.7、メタスコア87点、ロッテントマト98%。
▼観客5人(公開5日目の午後)1時間29分。
「HELP 復讐島」
男女が無人島に流れ着いて…というパターンの映画はたくさんありますが、男女の立場が逆転するというこの映画のプロットを聞いて最初に浮かんだのは「流されて…」(1974年、リナ・ウェルトミューラー監督)でした。これは金持ちの女性と召使いの男の立場が逆転しましたが、その逆パターンじゃないかと思いました。漂着の果ての立場の逆転に限れば、最近では「逆転のトライアングル」(2022年、リューベン・オストルンド監督)がありました。主人公のリンダを演じるのが今年48歳のレイチェル・マクアダムス。パワハラ気味の社長ブラッドリーは34歳のディラン・オブライエン。リンダは食べかけのツナサンドのツナを口の端に付けて、ブラッドリーと話し、ブラッドリーから嫌われます。本当なら自分が副社長になるはずだったのに、後輩の男がその地位を奪ったのもブラッドリーの差し金でした。そんな時、タイに出張に行く途中、プライベートジェットが海の上で墜落し、リンダとブラッドリーは無人島に漂着。リンダはサバイバル技術を持っていて、ブラッドリーより優位に立つ、という展開。
前半のリンダのおばさん風味が強烈で、婚約者もいるブラッドリーがいくら無人島に2人きりとはいえ、リンダを恋愛対象に考えるとは思えません。リンダが最初の捜索の船から隠れるのは立場の逆転をはっきりさせたかったからと受け取れますが、2度目のそれを拒否した上にあんなことするのは理解しにくいです。その後の展開も意外性はあるものの、褒めるほどではなかったです。
監督はサム・ライミ。脚本はダミアン・シャノンとマーク・スウィフト。この2人は「フレディVSジェイソン」(2003年、ロニー・ユー監督)、リメイク版の「13日の金曜日」(2009年、マーカス・ニスペル監督)でも組んでおり、この映画のホラー風味にも納得です。
IMDb7.3、メタスコア76点、ロッテントマト93%。
▼観客6人(公開6日目の午後)1時間52分。
「アグリーシスター 可愛いあのこは醜いわたし」
「国宝」と同じくアカデミー賞メイクアップ&ヘアスタイリング賞の候補となったノルウェー=デンマーク=ポーランド=スウェーデン合作。「シンデレラ」をモチーフにしたホラーで、一種のボディホラーと言えます。クライマックスの描写が目をつむりたくなるほど痛そうで苦手です。主人公のエルヴィラ(リア・メイレン)は義理の妹アグネス(テア・ソフィー・ロック・ネス)ほど美しくはなく、王子との結婚を夢みて鼻筋を手術で矯正、ふくよかな体形を整えるため、サナダムシの卵を呑んで痩せようとします(筒井康隆の「私説博物誌」には若い女性が痩せるためにサナダムシを飼っている場合があるという記述があったと記憶してます)。
まずまず面白いんですが、そういうグロいシーンもあるのでご注意です。監督はノルウェー出身のエミリア・ブリックフェルト。
IMDb7.0、メタスコア70点、ロッテントマト96%。
「禍禍女」
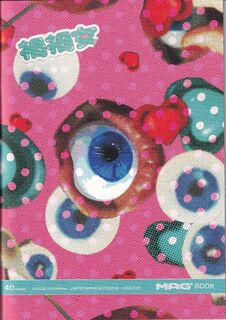
話は高校時代に好きな男に振られて自殺した太った女が「禍禍(まがまが)女」として化けて出てきて…というプロットにひねりを加えてあります。ゆりやんの話を脚本化したのは「ミスミソウ」「ヒグマ!!」の内藤瑛亮。
主演は南沙良。共演はアオイヤマダ、髙石あかり、田中麗奈、鈴木福、斎藤工ら。白石和彌監督と清水崇監督がカメオ出演しています。エンドクレジットに唐田えりか(ゆりやんと「極悪女王」で共演)の名前がありましたが、どこに出てきたのか気づきませんでした。パンフレットを読んだら、シェアハウスで見ているホラー映画に出てくる細身長髪女幽霊の役だそうです(顔がちゃんと映ってないので分かるわけない)。
ゆりやんが監督した経緯は、テレビのトーク番組で「映画監督をしたい」とのゆりやんの発言を聞いたプロデューサーからの誘いとのこと。
▼観客5人(公開初日の午後)1時間53分。
「あなたが帰ってこない部屋」
アカデミー短編ドキュメンタリー賞候補。原題は“All the Empty Rooms”。1997年から学校での銃撃事件(スクールシューティング)の取材を続けている放送記者のスティーヴ・ハートマンと写真家のルー・ボップが遺族の家で犠牲者の部屋を撮影する様子を描いています。Netflixが配信しています。犠牲となった子供たちの部屋はいずれも親が当時のままにしていて、子供を亡くした親の悲しみの深さに胸が痛みます。ただ、上映時間35分では食い足りない部分は残ります。
驚いたことに、アメリカではスクールシューティングが年間132件も起こっているそうです。マイケル・ムーア監督がコロンバイン高校銃乱射事件の原因を探った「ボウリング・フォー・コロンバイン」(2002年)の頃よりずっと増えていて、アメリカ政府がいまだに効果的な対策を打ち出せていないことにあきれます。根本的には銃規制しか対策はないのでしょう。
IMDb7.4。35分。
「名もなき反逆者 ロシア 愛国教育の現場で」
デンマーク=チェコ=ドイツ合作のアカデミー長編ドキュメンタリー賞候補。原題は“Mr. Nobody Against Putin ”。MHK-BSの「BS世界のドキュメンタリー」で「前編 追い込まれる教員たち」「後編 “軍事化"する学校」に分けて放送された、と映画.comにあったのでNHKオンデマンドで見ました。ロシアのウラル山脈東にある貧しい鉱山町のカラバシュ(人口1万人ほど)の学校で、授業や行事の撮影を任された教師パヴェル(パシャ)・タランキンが教え子を撮りつつ、ウクライナ戦争下で世論をコントロールしようとするプーチン政権の動向を記録しています。反戦の言動をして当局に監視されるようになったパシャはその後、ロシアを出国し、デヴィッド・ボレンスタインと共同監督を務めてこの映画を仕上げました。
ウクライナへの侵攻後、ロシアが愛国教育を徹底する様子がよく分かります。愛国というより軍国教育と言った方が良く、小学生の時から侵略戦争をねじ曲げて正当性を教え込むのはかつての日本と同じ、いや世界のどこでも戦争をしている国はこういう教育をするのでしょう。軍国教育の模範的な授業をする中年教師が表彰され、新築アパートを貸与されるなどあきれた描写が出てきます。
この映画で描かれたことはロシア国民なら誰でも知っていることでしょう。子供から大人までウクライナ戦争の嘘を教えられている現状を変えないと、戦争終結の道は遠いかもしれません。国家にとって無知な国民の増加は統治に極めて都合が良い状態ですが、政治家の言うことを鵜呑みにしてSNSしか読まない信じない無知蒙昧な人々が増えている日本も他国のことはとやかく言えないですね。
カラバシュという町は銅の精錬工場の有毒ガスで汚染され、ユネスコが「世界で最も汚染された町」と呼んだそうです。このため住民の平均寿命は38歳とのこと。こっちの問題も大きいんじゃないかと思いますが、序盤に触れるだけで追及はされていません。
IMDb7.6、メタスコア80点、ロッテントマト100%。1時間30分。
2026/01/25(日)「安楽死特区」ほか(1月第4週のレビュー)
「安楽死特区」

「安楽死法」が施行された近未来。余命半年の宣告を受けたラッパーの酒匂章太郎(毎熊克哉)とパートナーでジャーナリストの藤岡歩(大西礼芳)は安楽死反対の立場だった。2人は安楽死の実態を内部から取材するため「安楽死特区」への入居を決める。入居者たちの境遇と苦しみを知り、医師たちと対話することで章太郎の考えには変化が生まれる。
「痛くない死に方」は回復の見込みのない患者を点滴や人工呼吸装置につないで延命治療で苦しませることは間違いだという主張に説得力がありました。奥田瑛二扮する医師は延命治療の患者について「点滴で溺れ死んでいる」と指摘し、水分が抜けて枯れるように死んでいくのが望ましいという考えを持っていました。
この映画では平田満と余貴美子が安楽死を希望する患者として登場しますが、その描写と考え方に目新しさはありません。エンドクレジットの後に安楽死しようとしてスイスに行き、直前でやめた女性のインタビューがありますが、この人を描けば良かったんじゃないでしょうかね。フランソワ・オゾン監督は「すべてうまくいきますように」(2021年)で、スイスで安楽死する父親と悩んだ果てにそれに協力する家族の姿を描きました。ああいうドラマ性のある作品にした方が良かったと思います。「安楽死特区」は患者と家族のドラマ化が今一つうまくいっていません。
キャストは「痛くない死に方」の奥田瑛二、大西礼芳、余貴美子、「夜明けまでバス停で」(2022年)の板谷由夏、「桐島です。」(2025年)の毎熊克哉ら高橋監督の作品に出演経験のある俳優がそろっています。脚本は丸山昇一。
▼観客6人(公開初日の午後)2時間9分。
「CROSSING 心の交差点」
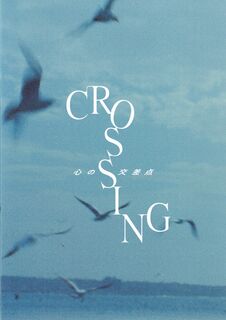
映画はジョージアに住む元教師リア(ムジア・アラブリ)が行方不明になったトランスジェンダーの姪テクラを捜すために、テクラの居所を知っているという青年アチ(ルーカス・カンカヴァ)とともに隣国トルコのイスタンブールに行く話。2人が住むジョージアのバトゥミからイスタンブールまでは黒海沿いの陸路で1400キロもあるそうです。言葉も違いますから、陸続きの隣国ではあるものの、心理的には遠い国なのかもしれません。2人はそこでトランスジェンダーの弁護士エヴリム(デニズ・ドゥマンリ)と出会い、一緒にテクラの行方を捜すことになります。
この3人の緩やかな心の接点の描き方が良いです。結局、テクラは既に死んだか、もっと遠い外国へ行ったのかもしれないということが分かるのですが、ジョージアに帰る途中でリアは偶然、テクラとすれ違います。テクラに呼び止められてリアは驚いてハグしますが、実は…という展開が秀逸でした。このあたりの文学的な表現も高い評価の理由なのでしょう。
映画の中でひどい差別が描かれるわけではありませんが、トランスジェンダーの女性たちがいずれも家族と縁を切っているという描写の普通さに差別の根深さが表れています。スウェーデン生まれのジョージア人であるレヴァン・アキン監督はゲイのダンサーを描いた前作「ダンサー そして私たちは踊った」(2019年)をジョージアで上映した際に激しい抗議活動に直面したそうです。監督自身もゲイであることを公表しています。
IMDb7.4、メタスコア83点、ロッテントマト97%。
▼観客3人(公開2日目の午後)1時間46分。
「ウォーフェア 戦地最前線」

驚いたのはIED(即席爆発装置)の威力と米軍戦闘機の威嚇飛行の迫力。IEDは日常品を流用して作られた手製爆弾のことですが、これによって米兵2人が重傷を負います。威嚇飛行は建物すれすれの低空飛行によりものすごい風圧を起こし、砂ぼこりを巻き上げます。これは効果あるでしょうね。
この映画について、ドラマがないじゃないかという言い方の批判がありますが、元々、関係者の記憶と写真を元に戦闘を再現しようという意図なのですから批判になっていません。共同監督のレイ・メンドーサはこの作戦に参加していたそうです。
パンフレットで押井守監督が「ホンモノのM2ブラッドレー(歩兵戦闘車)が登場した」と興奮しています。あれはイギリス陸軍の装甲兵員輸送車「FV432」ではないかという指摘がネットにありました。軍事オタクではないのでそのあたり分かりませんが、ああいう頑丈な車両があると、バズーカなどで狙われない限り、市街地の戦闘では有利でしょうね。
IMDb7.2、メタスコア78点、ロッテントマト92%。
▼観客10人ぐらい(公開4日目の午後)1時間35分。
「コート・スティーリング」
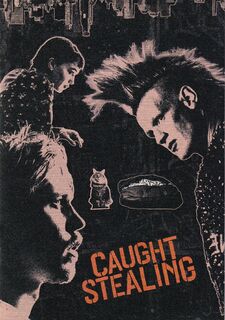
主人公のハンク(オースティン・バトラー)は高校時代、メジャーリーグのドラフト候補でしたが、自分が運転する車で自損事故を起こし、重傷を負ってプロの夢を断たれたほか、同乗していた親友を亡くした苦い過去を持つ男。今はニューヨークでバーテンダーをしています。ある夜、アパートの隣人ラス(マット・スミス)から猫の世話を頼まれたのが発端で謎の男たちから暴行を受けて腎臓が破裂、手術で摘出されてしまいます。以降、ハンクは訳が分からないまま酷い目に遭いますが、やがて裏社会の大金が絡んだ事件に巻き込まれたことが分かってきます。
原作・脚本はチャーリー・ヒューストン。アロノフスキーは18年前からこの原作が好きで映画化したいと思っていたそうです。分かりやすい原作があったことが作風を違えた要因なのでしょう。原作はハンクを主人公にした2編の続編が出ているそうです。タイトルは「窃盗で捕まる」「野球で盗塁を阻止する」という意味。
ハンクの恋人イヴィンヌを演じるゾーイ・クラヴィッツが良いです。女刑事役のレジーナ・キングやハンクを狙うならず者リーブ・シュレイバー、ヴィンセント・ドノフリオらも的確な好演でした。
IMDb6.9、メタスコア65点、ロッテントマト85%。
▼観客5人(公開13日目の午後)1時間47分。
「ペンギン・レッスン」
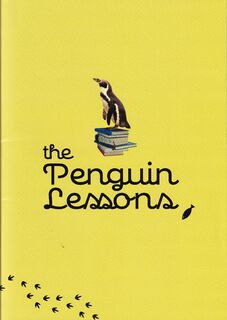
英国人の英語教師トム(スティーヴ・クーガン)がブエノスアイレスの名門寄宿学校に赴任する。混乱する社会と手強い生徒たちに直面する中、旅先で出会った女性と共に重油まみれの瀕死のペンギンを救う。海に戻そうとしたものの、不思議と彼の元に戻ってきてしまう。仕方なく、宿舎に持ち帰り、“サルバトール”と名付けたそのペンギンと、不器用ながらも少しずつ心を通わせていく。そんな時、宿舎のメイド・マリア(ヴィヴィアン・エル・ジャバー)の孫娘ソフィア(アルフォンシーナ・カロシオ)が軍事政権に拉致される事件が起きる。
トムはソフィアが拉致される現場を目撃しましたが、何もできなかった自分を責めます。悪くない出来と思いましたが、アメリカではあまり評価がないですね。
IMDb7.1、メタスコア52点、ロッテントマト78%。
▼観客2人(公開19日目の午前)1時間52分。
2026/01/18(日)「万事快調 オール・グリーンズ」ほか(1月第3週のレビュー)
「万事快調 オール・グリーンズ」

ラッパーを夢みる東海村の高校生・朴秀美(南沙良)は学校にも家にも居場所がない。映画好きの矢口美流紅(みるく=出口夏希)は陸上部のエースで社交的な美人。スクールカーストの上位にいながらも、家庭に問題を抱えていた。そして、授業中に小指を切断するけがを負い、スクールカーストを滑り落ちて秀美たちとつるむようになる。どん詰まりの日々のなか、秀美は地元のラッパー佐藤(金子大地)の家で大麻の種を手に入れる。故郷を出るため一攫千金を夢みる秀美は漫画に詳しい毒舌キャラの岩隈真子(吉田美月喜)、岩隈の後輩で漫画オタクの藤木漢(羽村仁成)らを仲間に加え、園芸同好会オール・グリーンズを結成、大麻栽培に乗り出す。
読書好きの秀美が読むのは「侍女の物語」「夏への扉」「ニューロマンサー」などハヤカワ文庫のSFばかり。映画好きの美流紅は東海村が出てくる「太陽を盗んだ男」を見に行こうと秀美たちを誘います。「東海村からプルトニウムを盗む場面がかっこいいんだ」。SFファンで映画ファンにはうれしい設定です。
物語のメインになるのは秀美なんですが、美流紅のエピソードが良いです。美流紅は“みるく”という名前が好きではなく、友人には名前の由来を「親がアメリカのハーヴェイ・ミルクが好きで」と嘘をついています(自殺した父親とアイドルおたくの母親がハーヴェイ・ミルクなんて知っていたはずはないのだけど)。そんな美流紅が母親から名前の由来を聞く場面が泣かせます。
秀美たちが行っているのは犯罪なので、決着をどうつけるか難しいところですが、映画は終盤、あり得ないような場面を描いています。考えてみれば、ここは「太陽を盗んだ男」の終盤を参考にしたのかもしれません。「そんな訳ねえだろ、バーカ」という人をくったセリフで終わるのは物語の結末としては弱いですが、この映画としては正しい終わり方だと思いました。
前半を少しコンパクトにして後半に注力した方が良かったとは思いますが、十分に面白く、公開初日の1回目の上映で閑古鳥を鳴かせて良いような映画ではありません。PRが足りず、内容の伝え方も良くなかったのでしょう。
▼観客1人(公開初日の午前)1時間59分。
「28年後…白骨の神殿」
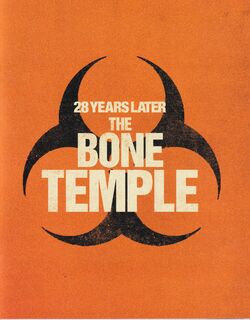
前作でケルソンのもとで病気の母親を看取った少年スパイク(アルフィー・ウィリアムズ)は感染者に襲われかけたところを、ジミー・クリスタル(ジャック・オコンネル)率いる集団に救われますが、この集団、悪魔を崇拝していて、とんでもない残虐行為を繰り返していました。一方、ケルソンはサムソンと名づけた感染者(チャイ・ルイス=ペリー)にある治療法を試し、一定の効果があることが分かります。ジミーの集団は感染者を手懐けるケルソンを覇王=悪魔と誤解して接触してきます。
話は悪くないですし、レイフ・ファインズも好演していますが、ゾンビよりも人間の方が残酷という描写はドラマ「ウォーキング・デッド」でも描かれましたし、感染者が頭を胴体から引っこ抜いたり、脳みそをすくって食べたり、ジミーたちが生きた人間の皮を剥いだりする残虐描写は苦手です。もう少し、描写を抑えてくれると良いのですがね。脚本は前作に続いてアレックス・ガーランド、監督は「キャンディマン」(2021年)、「マーベルズ」(2023年)のニア・ダコスタ。「28年後…」は三部作になるようで3作目が予定されています。
IMDb7.8、メタスコア81点、ロッテントマト94%。
▼観客10人ぐらい(公開初日の午後)1時間49分。
「小川のほとりで」
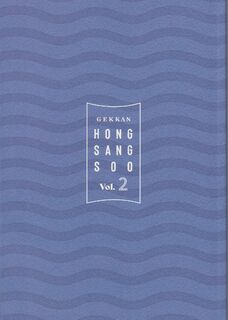
ソウルの女子美術大学を舞台に大学講師(キム・ミニ)が演劇祭の演出に叔父(クォン・ヘヒョ)を招聘したことから起こる出来事を描いています。キム・ミニもクォン・ヘヒョもホン・サンス映画の常連ですし、固定カメラで長回しの会話劇なのも同じです。代わり映えしない内容だなと思いつつ、退屈はしませんでした。
IMDb6.8、メタスコア76点、ロッテントマト100%。キム・ミニがロカルノ国際映画祭最優秀演技賞を受賞。
▼観客4人(公開5日目の午後)1時間51分。
「満江紅 マンジャンホン」

加えて、主要登場人物が任務を果たす途上で次々に死んでいくのはクレイグ・トーマスあたりのスパイ小説を思わせました(ただし、コメディーみたいな場面は不要でしょう)。
こちらの中国の歴史に関する知識の乏しさはいかんともしがたく、完全に理解したとは言えないのが辛いところ。こういう映画こそパンフレットを読みたくなりますが、キネマ館では扱っていませんでした。全国公開から2カ月ほど遅れたので、在庫がなかったのでしょう。残念。メルカリでは出品されていますが、あまり買いたくありません。パンフも電子書籍化すればいいのにと思います。
IMDb6.4、メタスコア75点、ロッテントマト94%。
▼観客2人(公開6日目の午後)2時間37分。
「藤本タツキ 17-26 Part-1」、6位「同Part-2」
昨年10月の公開に続いて16日から再公開されました。といっても昨年11月からamazonプライムビデオで配信が始まっていて、僕も配信で見ました。「チェンソーマン」の原作者藤本タツキが17歳から26歳までに描いた短編8作品のアニメ化で、7人が監督しています。Part-1は「庭には二羽ニワトリがいた。」(長屋誠志郎監督)、「佐々木くんが銃弾止めた」(木村延景監督)、「恋は盲目」(武内宣之監督)「シカク」(安藤尚也監督)の4作品。Part-2は「人魚ラプソディ」(渡邉徹明監督)、「目が覚めたら女の子になっていた病」(寺澤和晃監督)、「予言のナユタ」(渡邉徹明監督)、「妹の姉」(本間修監督)の4作品で、いずれも20分程度の長さです。
最も面白かったのは「庭には二羽ニワトリがいた」。宇宙人に侵略され、人類は食べ尽くされてしまいますが、少年と幼い少女だけが学校の裏庭でニワトリの格好をして生き延びているというシチュエーション。人間が家畜を食べるように宇宙人は人間が大好物なので2人はヒヤヒヤしながら生きています。やがて1人の宇宙人が2人の正体を知ってしまう、という展開。怪物のような宇宙人のバラエティーに富んだデザインが良く、残酷描写を含めた描写も良いです。
8本のうち7本はSFあるいはファンタジー。最後の「妹の姉」のみ高校で美術を学ぶ姉妹を描いた作品でした。これも絵に打ち込む姿が良いです。
IMDb8.0(アメリカは限定公開、韓国と台湾でも劇場公開していますが、他は配信のようです)。Part-1が1時間8分、Part-2は1時間16分。
2026/01/11(日)「Black Box Diaries」ほか(1月第2週のレビュー)
「Black Box Diaries」

ジャーナリストの伊藤詩織さんが監督を務め、自らの性被害を告発、追及する過程を描いたドキュメンタリー。理不尽な誹謗中傷と脅しにさらされる苦しい日々が続いた後、クライマックスにまるでドラマのような場面が訪れます。それは事件があったホテルのドアマンの証言。事件から4年たった頃、ドアマンの男性は事件の夜に自分が見たことを伊藤さんにメールで連絡してきます。これまでに明らかになっていなかった新たな重要証言であり、伊藤さんは民事訴訟の裁判でこの証言を出したいと、男性に電話で許可を請います。そして男性の「裁判で私の名前を出してもらってかまいません」という返事を聞いて泣き崩れます。
意識がもうろうとした状態でTBSの元記者に無理矢理ホテルに連れ込まれ、レイプされた事件。それから裁判までの大まかな流れは知っていましたが、映画で描かれる伊藤さんへの謂れ無い誹謗中傷の多さに胸が痛むと同時に怒りがふつふつと沸騰してきます。伊藤さんは強い女性だから事件を追及し、民事裁判を闘えたわけではなく、性被害のPTSDから逃れるために打ち込んできたのではないかと思えます。
ドアマンの男性の証言を裁判に使うことで彼は職場を追われるかもしれない、と伊藤さんの弁護士は忠告しますが、「名前を出してかまわない」と言った男性はそれを承知の上でした。伊藤さんの苦闘をさんざん見せられた後だったので、男性の言葉に救われる思いがしました。事件を握りつぶそうとする警察上層部の腐った幹部やネットのデマに踊らされて被害者を誹謗中傷する浅薄な人たちもいますが、もちろん、そんな人間ばかりではないわけです。幸い、男性が職を失うことはなかったそうです。
両親への遺書のようなビデオレターの自撮り撮影直後に病院の描写があり、伊藤さんが自殺未遂していたことを示唆する場面があります。性被害は深刻な心の傷を残し、それが完全に癒えることはないのでしょう。被害を受けて11年。#MeToo運動(2017年、ニューヨーク・タイムズがハーヴェイ・ワインスタインの性加害を告発した記事がきっかけ)の前に起きた事件であり、伊藤さんの行動はその先駆けになったものと言えます。心の傷が少しでも和らぐことを願うばかりです。
IMDb7.5、メタスコア82点、ロッテントマト99%。アカデミー長編ドキュメンタリー賞候補。
▼観客5人(公開初日の午前)1時間42分。
「五十年目の俺たちの旅」

今回は50周年だからということで作ったのでしょうが、残念ながらドラマの中身に見るべきものはほとんどありません。初めて監督を務めた中村雅俊が歌う主題歌と昔の映像には懐かしさを感じましたが、それだけ。かつての登場人物たちの現在のドラマに語るべきことがない(思いつかない)のなら、作る必要はなかったと思います。
原作・脚本は50年前のドラマも担当した鎌田敏夫。70代になった津村浩介(カースケ=中村雅俊)と大学時代の同級生・神崎隆夫(オメダ=田中健)、カースケの小学校の先輩・熊沢伸六(グズ六=秋野太作)の現在の状況が描かれます。僕は知りませんでしたが、山下洋子(金沢碧)は「三十年目の運命」の中で死んでいたことが分かったという設定だったそうです。
洋子はカースケに思いを寄せる重要な役柄でしたから、しばしば挿入される過去の映像にも頻繁に登場します。しかし、映画のエンドクレジットに金沢碧の名前はありませんでした。僕の見落としかと思い、パンフレットを確認しましたが、やはりありません。金沢碧は女優を引退しているらしいですが、映像を使っているのにクレジットに入れなくて良いのでしょうかね。
映画を見る前にドラマの第1話をHuluで見たんですが、映像が意外にきれいなことに少し驚きました。地デジが始まる前にビデオ撮影されたテレビドラマは例外なく画質が悪いです。このドラマがきれいなのはフィルム撮影だったからでしょう。といっても16ミリフィルムのはずですから、スクリーンでは画質の粗さは出てしまいます。映画は現在と過去の映像をスムーズにつなげるため、画面比率1:1.37のスタンダードサイズで撮られています。今のテレビだと、この画面比率でドラマを作るのは民放では難しいでしょうから、映画にしたのはそれが理由の一つかもしれません。
映画を見た後に「十年目の再会」をTVerで見ました。オメダは妻子を残して家を出てシングルマザー(永島暎子)と暮らし、洋子の夫は不倫しており、オメダの妹真弓(岡田奈々)は離婚という状況。鎌田敏夫はこの前に「金曜日の妻たちへ」の脚本を書いており、それに引きずられたような内容と言えますが、ドラマ全体の出来は悪くないと思いました。「五十年目」もこれぐらいの水準は保って欲しかったところです。
▼観客20人ぐらい(公開初日の午後)1時間49分。
「手に魂を込め、歩いてみれば」

そのファトマと1年近くビデオ通話を続けたイラン人の監督セピデ・ファルシがまとめたドキュメンタリー。イスラエルによる爆撃が続くガザでファトマは死の恐怖と飢えに苦しみながら、ビデオ通話では笑顔を絶やしません。ガザの犠牲者は昨年12月の段階で7万人を超えたそうです。数字だけでは実感しにくい人の命の重さを、この映画は25歳で亡くなった1人の女性の考え方と生き方、人柄を描くことで痛切に伝えています。
観客の多くは映画を見ているうちにファトマに親近感を持つでしょう。元々、途切れがちだったビデオ通話が完全につながらなくなると、ファルシ監督と同じくファトマの身を案じて不安になるはず。イスラエルがやっていることは狂気の沙汰であり、これまでのナチスのホロコーストを糾弾した数々の映画の価値を著しく貶めることにつながっています。イスラエルはナチスと同等の醜悪な存在になるつもりなんでしょうか。
IMDb7.7、メタスコア83点、ロッテントマト98%。
▼観客3人(公開11日目の午前)1時間53分。
「殺し屋のプロット」

きちんと伏線を張っているのが良く(途中でこれは何をやってるんだろうと思うシーンがありましたが、忘れちゃいますね)、ミステリーファンにもアピールする内容だと思います。アメリカでの評判はあまり良くないんですが、日本ではそこそこ良い評価になってます。脚本は「ナショナル・トレジャー2 リンカーン暗殺者の日記」(2007年、ジョン・タートルトーブ監督)などのグレゴリー・ポイリアー。共演はアル・パチーノ、マーシャ・ゲイ・ハーデンら。
IMDb7.0、メタスコア54点、ロッテントマト66%。
▼観客3人(公開5日目の午後)1時間55分。
「プラハの春 不屈のラジオ報道」

「プラハの春 不屈のラジオ報道」でもソ連率いるワルシャワ条約機構軍の戦車は登場しますが、「存在の…」ほど強い印象を残さないのはプラハの春以前の不自由な時代が描かれているからでしょう。「存在の…」はダニエル・デイ・ルイス演じる主人公の脳外科医がプレイボーイであるという軽さが対比の上で効果を上げていました。
チェコスロバキア国営ラジオ局の国際報道部を舞台にしたこの映画は1967年10月の学生デモから始まります。プラハの春は1968年1月始まったとされていますが、映画では同年3月にノヴォトニー大統領が裏金発覚で辞任したことから本格化したように描かれています。そして自由化阻止を狙った8月のソ連による軍事侵攻で“春”は終わります。
脚本・監督のイジー・マードルは当時の記録映像も取り入れて事態の経過を描いています。真正直な映画化ではあるんですが、監督が参照したという「アルゴ」(2012年、ベン・アフレック監督)や「グッドナイト&グッドラック」(2005年、ジョージ・クルーニー監督)には及ばないと思えました。
IMDb7.8(アメリカでは限定公開)
▼観客10人ぐらい(公開7日目の午後)2時間11分。
2026/01/04(日)「教場 Reunion」ほか(1月第1週のレビュー)
さっそく第3シーズンを見始めたばかりだった「窓際のスパイ」を見てみたら、字幕がクローズドキャプション(CC)しか選べません。CCは主に聴覚障害者向けの字幕で普通の会話のほか、ドアの音や音楽、誰のセリフかなどが分かる説明が入ります。逆にほかの映画は普通の字幕しかなく、CCは選べません。うーん、これもおかしな仕様ですね。普通の字幕とCCの両方から選べるようにするのが理想でしょう。ドラマにCCしかないのは日本語吹き替え版で見る人が多いだろうという考えなんでしょうかね。
「教場 Reunion」
長岡弘樹原作のテレビドラマの後を受けて脚本・君塚良一、監督・中江功で映画化したNetflix作品。Reunion(再集結)のタイトルは風間公親(木村拓哉)教場の教え子たちが、シリーズ最大の凶悪犯で風間に恨みを持つ十崎(森山未來)の捜査で一堂に会することに由来しているのでしょう。物語はいつものように警察学校の新入生たちのエピソードが描かれる形で進行しますが、中盤にかつての教え子たちが集う場面、染谷将太、新垣結衣、赤楚衛二、川口春奈、白石麻衣、福原遥、大島優子らが十崎捜査の話し合いをする場面が入ることでぐっと引き締まりました。ラストは2月20日劇場公開の「教場 Requiem」につながる形で終わります。最後の場面に意外な人物を出してくるのがうまいところ。劇場版への期待が高まりました。
今回の新入生の中心になるのは綱啓永。ほかに齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃、猪狩蒼弥らが出ていますが、井桁弘恵ら一部の出演者は活躍の場があまりなく、劇場版の方に持ち越されたようです。元日向坂46の齊藤京子は最初にドラマ「泥濘の食卓」(テレ朝系)に出た時は演技が不安定でしたが、ドラマ出演を重ねてだんだん巧くなった感があります。今月公開の「恋愛裁判」(深田晃司監督)も楽しみです。
これを見ていなくても劇場版は分かる作りになっていると思います。もちろん、見ておいた方が楽しめるでしょう。
画面に出たタイトルは「教場III Reunion」となってました。第3シーズンにあたりますからね。2時間30分。
「ナイブズ・アウト ウエイク・アップ・デッドマン」
ダニエル・クレイグが名探偵ブノワ・ブラン役を演じる本格ミステリーシリーズ第3弾。昨年9月にカナダのトロント国際映画祭で上映された後、各地の映画祭や一部の国で劇場公開し、12月12日からNetflixで配信が始まりました。田舎町の教会で司祭(ジョシュ・ブローリン)が密室的な状況下で殺される。教会の中には地域の住民たちがいたが、赴任したばかりの若い神父(ジョシュ・オコナー)が一番近くにおり、司祭と不仲だったためもあって容疑がかかる。警察の要請を受けたブノワ・ブランが捜査を始める中、もう一つの殺人事件が起こる。
2つの殺人はいずれも不可能犯罪と呼べるもので、特に2番目の事件はタイトル通り、死者が死体安置所のコンクリートを砕いて登場し、殺人を犯すというもので興味を引きます。脚本・監督はライアン・ジョンソン。ジョン・ディクスン・カーの名作「三つの棺」への言及シーンがあるなど、ジョンソン監督の本格ミステリー好きがうかがえました。4作目の構想もあるとか。
出演はほかにグレン・クローズ、ジェレミー・レナー、ミラ・クニス、アンドリュー・スコット、ケリー・ワシントン、ケイリー・スピーニーら。スピーニーは車椅子で登場し、「エイリアン:ロムルス」「シビル・ウォー アメリカ最後の日」とは違った魅力を見せています。
IMDb7.4、メタスコア80点、ロッテントマト92%。2時間24分。