2006/09/09(土)「X-MEN ファイナル ディシジョン」
 監督がブライアン・シンガーからブレット・ラトナーに替わった第3作。ジェームズ・マーズデンはシンガーの「スーパーマン リターンズ」にも出ているためか、本来ならX-MENの中心メンバーであるはずのサイクロップスがあっさり退場。それとは関係ないが、ひいきのミスティーク(レベッカ・ローミン)も早々に姿を消すのにがっかり。今回の中心は前作のラストで死んだと思われたジーン・グレイ(ファムケ・ヤンセン)で、エグゼビア教授(パトリック・スチュワート)教授もマグニートー(イアン・マッケラン)をも上回る超能力の暴走がX-MENにとって大きな脅威となる。ラトナーの演出はこの悲劇的な話を少しもエモーショナルには描かず、VFXだけの映画という印象となっている。映画を盛り上げるポイントがないのである。シンガーならもう少し情感たっぷりに描いたはずだ。個人的にはストーム(ハル・ベリー)とヤンセンを見ているだけで満足なのだが、ヤンセンのあの怪物のような形相はいただけない。抑えきれない超能力の暴走という点で「キャリー」や「フューリー」を思い起こさせる映画である。
監督がブライアン・シンガーからブレット・ラトナーに替わった第3作。ジェームズ・マーズデンはシンガーの「スーパーマン リターンズ」にも出ているためか、本来ならX-MENの中心メンバーであるはずのサイクロップスがあっさり退場。それとは関係ないが、ひいきのミスティーク(レベッカ・ローミン)も早々に姿を消すのにがっかり。今回の中心は前作のラストで死んだと思われたジーン・グレイ(ファムケ・ヤンセン)で、エグゼビア教授(パトリック・スチュワート)教授もマグニートー(イアン・マッケラン)をも上回る超能力の暴走がX-MENにとって大きな脅威となる。ラトナーの演出はこの悲劇的な話を少しもエモーショナルには描かず、VFXだけの映画という印象となっている。映画を盛り上げるポイントがないのである。シンガーならもう少し情感たっぷりに描いたはずだ。個人的にはストーム(ハル・ベリー)とヤンセンを見ているだけで満足なのだが、ヤンセンのあの怪物のような形相はいただけない。抑えきれない超能力の暴走という点で「キャリー」や「フューリー」を思い起こさせる映画である。
ミュータントの能力をなくす治療薬キュアが開発される。ミュータント省の長官を務めるビースト(ケルシー・グラマー)は「恵まれし子供たちの学園」を訪れ、エグゼビア教授にそれを告げる。政府はミュータント政策としてキュアの投与を呼びかけるが、マグニートー率いるブラザーフッドは反発。キュアを開発したのはワージントン(マイケル・マーフィー)。ワージントンの息子エンジェルは背中に翼を持つミュータントだった。一方、ジーン・グレイを失って失意のサイクロップスはグレイの声に導かれるようにジーンが死んだ湖に行く。そこへ死んだはずのジーンが現れる。ウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)とストームも湖に駆けつけ、ジーンを学園に連れ帰るが、サイクロップスの姿はなかった。エグゼビア教授はウルヴァリンに、ジーンは邪悪なフェニックスとの二重人格者だと教える。そしてジーンはウルヴァリンの目の前で学園を脱走、接触してきたマグニートーの仲間に加わる。
キュアの元になったのはミュータントの能力を無力化する能力を持つミュータントのリーチ(キャメロン・ブライト)。保護された研究所の中にいるリーチの在り方は大友克洋「アキラ」を思わせる。クライマックスはこのリーチを抹殺しようと図るミュータント軍団に立ち向かうウルヴァリンたちが描かれる。この場面は映画の最初の方にある戦闘シミュレーションと呼応しているのだが、撮り方もVFXもそれほど際だったものではない。復讐の女神と化したジーン・グレイをどう助けるかでリーチの能力を生かすのかと思ったら、普通の決着の付け方なので少しがっかり。というか、本来ならこの決着の付け方の方が悲劇的ではあるのだが、ラトナーの演出がそれを生かせていないのである。パンフレットのみのわあつおの文章によると、「X-MEN」はキャラクターのスピンオフを含めて計10作が作られる予定という。せめてこの第3作まではシンガーに撮って欲しかったところではある。
ファムケ・ヤンセンは今年41歳、ハル・ベリーも40歳だが、年を感じさせない魅力はさすが、というべきか。前作までレベッカ・ローミンはレベッカ・ローミン=ステイモスという名前だったが、ジョン・ステイモスとは昨年、離婚したのだそうだ。
2006/09/06(水)「うつせみ」
キム・ギドクがヴェネチア映画祭で銀獅子賞を受賞した作品。詩情あふれる映画で、予告編にある「至福のロマンス」という表現がぴったり来る。セリフが少ないのはギドク作品では珍しくはないが、主人公(ジェヒ)にはまったくセリフがなく、相手役のイ・スンヨンは「愛してる」などひと言、ふた言だけというのが徹底している。これだけセリフがないと、字幕なしでも十分理解できるだろう。主演の2人の心の動きは描写だけで分かるのだ。描写の洗練度は最近のギドク作品の中でも上位に来ると思う。
留守の家を探して忍び込み、洗濯をしたり、掃除をしたり、故障した時計を直す青年がある豪邸で女と出会う。女は殴られて顔にあざができている。青年の様子を見ていた女は何となく親近感を覚えるが、そこに夫が帰ってくる。横暴な夫を見て腹を立てた青年はゴルフボールをぶつけ、女は青年と一緒に出て行く。そこから2人は留守の家を探し、忍び込み、という生活を続ける。
こういう生活に破綻が来るのは目に見えているが、そこからの展開も面白い。2人の間にある障害をどう克服していくかの話と見ることもできるだろう。ファンタスティックな描写はないけれど、ジェヒとイ・スンヨンがどちらも美形なので、幻想的な雰囲気が立ち上ってくる。
ギドクは誰にも教わらず独学で独自の世界を作り上げている希有な監督で、そのオリジナリティーは大したものだと思う。残念ながら、新作の「弓」は韓国では1週間で打ち切られたそうで、「グエムル」のポン・ジュノとは対極の立場にあるが、それでも作品から目を離せない監督であることは間違いない。
2006/09/03(日)「グエムル 漢江の怪物」
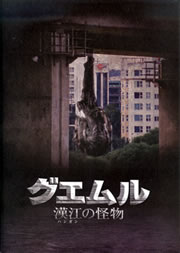 映画の冒頭、米軍が大量のホルムアルデヒドを下水に流す場面は韓国で2000年に実際にあった事件だそうだが、たかがホルムアルデヒドぐらいで巨大化した突然変異の怪物ができるわけはないと思う。監督のポン・ジュノはしかし、そんなことは単なる設定だよと言わんばかりに、怪物に娘をさらわれた家族の奮闘をユーモアを絡めて徹底的にエンタテインメントに描いていく。
映画の冒頭、米軍が大量のホルムアルデヒドを下水に流す場面は韓国で2000年に実際にあった事件だそうだが、たかがホルムアルデヒドぐらいで巨大化した突然変異の怪物ができるわけはないと思う。監督のポン・ジュノはしかし、そんなことは単なる設定だよと言わんばかりに、怪物に娘をさらわれた家族の奮闘をユーモアを絡めて徹底的にエンタテインメントに描いていく。
怪獣映画の中には怪獣の出てくる場面だけが見所で、あとは延々と退屈という作品がよくあるけれど、この映画の場合、家族を描いた部分が怪物登場シーン以上に面白い。というか、おかしい。このユーモアは登場人物のキャラクターと直結していて、主人公のソン・ガンホは小さいころ頭が良かったのに成長時にタンパク質がたりなくて今のようになってしまったとか、出てくるアメリカ人科学者がなぜか斜視であったりとか、ソン・ガンホの妹と弟も駆けつけた合同葬儀の場面のドタバタとか、怪物追跡で疲れきって寝入ってしまう場面とか、頭からウィルスを採取されようとするソン・ガンホの手術の場面とか、ほとんど冗談かと思える描写が多くて実におかしい。この面白さはポン・ジュノの前作「殺人の追憶」に共通するもので、この作り方がポン・ジュノの個性なのだなと思う。こうしたユーモアがキャラクターの分厚い肉付けとなっている。それはあらゆる映画に必要なものであるにもかかわらず、書き割りみたいな類型的キャラクターが怪獣映画には多くてうんざりするのだが、基本的に映画作りのうまい監督が撮ると、やはり映画は面白くなるのだった。怪物自体に新機軸はないものの、怪物映画の快作になり得たのはそのうまさがあるからにほかならない。
怪物をゴジラのように巨大化しなかったのは賢明で、あれぐらいの大きさなら家族で対抗できると思う。巨大鮫や巨大熊が出てくる動物パニック映画と基本的には同じ作りなのである。惜しむらくはこの映画、軍隊が登場しない理由が明確には描かれない。あんな怪物、バズーカ砲を一発見舞ってしまえば、終わりだろう。
漢江から謎の怪物(グエムル)が現れ、人々をむさぼり食う。漢江のそばで売店を営むパク・ヒボン(ピョン・ヒボン)は長男のカンドゥ(ソン・ガンホ)とその娘ヒョンソ(コ・アソン)と暮らしていたが、ヒョンソが怪物にさらわれ、水の中に消える。弟のナミル(パク・ヘイル)とアーチェリーの選手でもある妹のナムジュ(ペ・ドゥナ)が犠牲者の合同葬儀に駆けつけるが、怪物は謎のウィルスの宿主だったとして韓国政府は怪物に接触した人々を隔離する。その夜、カンドゥの携帯にヒョンソから電話が入る。ヒョンソは生きていたのだ。家族4人は病院を抜け出し、武器を調達して怪物が逃げ込んだ下水道を探し始める。
グエムルが橋の欄干からゆっくりと水中に落ちる場面の動きなどは「エイリアン」を参考にしたのかと思う。同様に娘をさらわれるのも「エイリアン2」の設定を借りているのだろう。家族で怪物に対抗するのは「トレマーズ」あたりか。僕はなんとなくこれまたB級怪物映画の快作「ミミック」(1997年、ギレルモ・デル・トロ監督)も連想したが、パンフレットでポン・ジュノ、やはり「ミミック」に影響を受けていると語っていた。ペ・ドゥナの役柄はアーチェリーで銅メダルを取った選手だから、これはクライマックスにそれを利用するシーンがあるだろうと思っていたら、やはり。その使い方も工夫があって面白かった。
怪物のデザインはWETA社が担当したそうで、魚とトカゲを組み合わせたような造型はよくできている。CGのスピーディーな動きが凶暴性を感じさせて良かった。それにしてもこの怪物、1匹だけではないだろう。続編も期待できるが、有能なポン・ジュノは同じことを2度はしないような気がする。
2006/08/26(土)「ラフ」
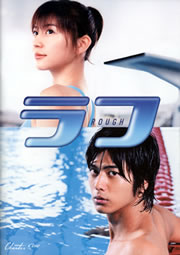 あだち充の原作コミックを大谷健太郎監督が映画化。主演は長澤まさみと映画初出演の速水もこみち。この2人に関してはそれぞれの魅力を見せていると思うし、いくつか良い場面もあるのだが、肝心のドラマがあまり盛り上がっていかない。設定だけを用意して、描写が不十分なのである。状況を説明するシーンがあるだけで、それぞれのシーンが有機的に結合していかないのがもどかしい。原作は未読だが、そのダイジェストになった観がありあり。原作のキーとなる場面を取り出して組み合わせただけで、もったいない作りだと思う。力点となるべきポイントが不鮮明なので平板な印象を与える結果になっている。
あだち充の原作コミックを大谷健太郎監督が映画化。主演は長澤まさみと映画初出演の速水もこみち。この2人に関してはそれぞれの魅力を見せていると思うし、いくつか良い場面もあるのだが、肝心のドラマがあまり盛り上がっていかない。設定だけを用意して、描写が不十分なのである。状況を説明するシーンがあるだけで、それぞれのシーンが有機的に結合していかないのがもどかしい。原作は未読だが、そのダイジェストになった観がありあり。原作のキーとなる場面を取り出して組み合わせただけで、もったいない作りだと思う。力点となるべきポイントが不鮮明なので平板な印象を与える結果になっている。
日本水泳連盟が全面的にバックアップしたという水泳シーンの吹き替えには違和感がないのだが、その水泳のドラマがスポーツを題材にした映画ならばこうあるべきという描き方になっていないのは残念。水泳の魅力をしっかり描いた方が本筋の主人公2人の恋愛感情の揺れ動きも効果的になったと思う。脚本の金子ありさ、監督の大谷健太郎ともスポーツには興味がないのではないか。
「タッチ」同様、基本的には重いテーマを含んだ話である。競泳の自由形で日本選手権に出場した高校生の大和圭介(速水もこみち)はレースの途中で足を痛めてリタイア。通路ですれ違った少女から「ひとごろし」と言われる。その少女は高飛び込み選手の二ノ宮亜美(長澤まさみ)で、圭介と亜美の実家はともに和菓子屋でライバル関係にあった。2人は同じ高校で同じ寮に入った。くじを引いた男女がデートするという寮の伝統で、2人は1日デートすることになる。そこで圭介は亜美が自由形の日本記録保持者の仲西弘樹(阿部力)と幼なじみで「おにいちゃん」と慕っていることを知る。ちょっとした誤解から圭介はデートの最後で「お前なんか、大嫌いだ」と言ってしまうが、徐々に2人は心を通わせていく。翌年の日本選手権、仲西は自損事故で重傷を負って欠場し、圭介が優勝する。その事故に亜美は責任を感じ、圭介との仲は疎遠になっていく。
この三角関係が映画のメイン。前半の1日デートの場面などはいい感じだが、後半、映画はストーリーを消化するのに性急になった感じが拭いきれない。事故の責任を感じる亜美という設定が十分に機能していかないのはこの性急さがあるためだろう。亜美の心変わりの描き方にも説得力を欠く。描写が不足する一方で、高飛び込みチャンピオンの小柳かおり(市川由衣)が圭介に告白するシーンは不要としか思えない。これだけで終わっているのである。もっとストーリーをすっきり整理する脚色が必要だったのだと思う。
タイトルの「ラフ」の意味は映画の最初の方で寮の管理人(渡辺えり子)から説明される。寮に入った新入生たちはまだラフスケッチの段階でこれから1本1本しっかりした線を引いていくことになるという意味。これは2人の揺れ動く関係を表すとともに圭介の荒削りな才能という意味も含まれているのだろう。それにしては才能の部分が描かれないのがスポーツを題材にした映画としては弱いところだ。長澤まさみのアイドル映画としても、初の水着姿を披露しているのが大きな利点とはいえ、同じくあだち充原作を映画化した去年の「タッチ」(犬童一心監督)には及ばないと思う。
2006/08/20(日)「スーパーマン リターンズ」
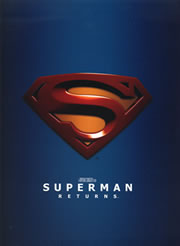 クリストファー・リーブ主演の1作目と2作目「冒険編」は予算をかけた作りだったが、3作目「電子の要塞」からガクッとチープになり、4作目「最強の敵」は映画館で見る気にならなかった。今回の映画はそのためかどうか、2作目からつながる物語として作られている。5年ぶりに地球に帰ってきたスーパーマンがレックス・ルーサーの悪事を打ち砕く。ジョン・ウィリアムスの音楽が鳴り響き、立体文字のタイトルが出てくるオープニングでノスタルジーをガンガンくすぐられる。リチャード・レスターの2作目から25年ぶりなので仕方がない。スーパーマンが地球に帰ってくる冒頭のシーンから1作目を意識したような作りだが、全体的にシリーズの伝統を大事にしており、父と子というテーマを根底に置いたオーソドックスな在り方には好感が持てる。終盤、意外な人間関係が出てくるのは、続編を意識したためだろう。ただ、2時間34分は少し長い。スーパーマンを演じるのは新人のブランドン・ラウス。リーブによく似ている。監督は「X-メン」シリーズのブライアン・シンガー。
クリストファー・リーブ主演の1作目と2作目「冒険編」は予算をかけた作りだったが、3作目「電子の要塞」からガクッとチープになり、4作目「最強の敵」は映画館で見る気にならなかった。今回の映画はそのためかどうか、2作目からつながる物語として作られている。5年ぶりに地球に帰ってきたスーパーマンがレックス・ルーサーの悪事を打ち砕く。ジョン・ウィリアムスの音楽が鳴り響き、立体文字のタイトルが出てくるオープニングでノスタルジーをガンガンくすぐられる。リチャード・レスターの2作目から25年ぶりなので仕方がない。スーパーマンが地球に帰ってくる冒頭のシーンから1作目を意識したような作りだが、全体的にシリーズの伝統を大事にしており、父と子というテーマを根底に置いたオーソドックスな在り方には好感が持てる。終盤、意外な人間関係が出てくるのは、続編を意識したためだろう。ただ、2時間34分は少し長い。スーパーマンを演じるのは新人のブランドン・ラウス。リーブによく似ている。監督は「X-メン」シリーズのブライアン・シンガー。
天文学者から惑星クリプトンのかけらが残っていると聞いたスーパーマン=クラーク・ケントは宇宙に旅立っていたが、5年ぶりに地球に帰ってくる。勤めていたデイリー・プラネット社に行くと、歓迎してくれるのはジミー(サム・ハンティントン)だけ。ロイス・レイン(ケイト・ボスワース)は編集長(フランク・ランジェラ)の甥リチャード(ジェームズ・マーズデン)と同棲し、子供までいる。しかもロイスは「世界になぜスーパーマンは必要でないか」という記事でピューリッツァー賞に選ばれていた。ロイスは「さよなら」も言わずに旅立ったスーパーマンに腹を立てていた。その頃、宿敵のレックス・ルーサー(ケヴィン・スペイシー)は老婦人に取り入って刑務所を出所し、莫大な財産を手にしていた。愛人のキティ(パーカー・ポージー)や手下とともにスーパーマンの北極の要塞でクリスタルを手に入れ、悪事の計画を進める。
ロイス・レインを乗せた飛行機を墜落から救うのが前半の大きな見所。VFXもそれなりによくできているが、スペースシャトルを乗せた飛行機からシャトルが燃料噴射するというシーンは「007 ムーンレイカー」(1979年)にもあった。思えば、1作目でスーパーマンが空を飛ぶシーンはそのあまりの自然さ(当時としては)に驚き、2作目のスーパー3悪人とスーパーマンの対決シーンでもSFXに驚いたものだが、25年もたてば、そういうシーンは普通に思えてくる。だから、今回の映画はドラマ部分に重点を置く必要があった。そのドラマがやや希薄に感じるのは上映時間が長い割にストーリーの進行がないからで、久しぶりのスーパーマンに満足しながらも、もっとドラマの密度を濃くしてほしいという思いも残った。
ケヴィン・スペイシーとケイト・ボスワースは「ビヨンドtheシー」で共演済み。スペイシーはユーモアと冷酷さ(スーパーマンをクリプトナイトでいたぶる場面の残酷さ!)をブレンドした演技で相変わらずうまい。「X-メン」のサイクロップス役ジェームズ・マーズデンは本来なら憎まれ役になりそうなのに良い役回りだと思う。物語の終わり方からして必ず続編ができるだろう。スーパーマンシリーズでいつも感じるのはスーパーマンがどの程度の悪事まで阻止するかということ。この映画でも単純な事件まで関わっていたが、そういうシーンが必要かどうか疑問なのだ。続編ではそういう部分も考慮し、主要な事件に絞った展開にしてはどうかと思う。