2004/12/13(月)「レディ・ジョーカー」
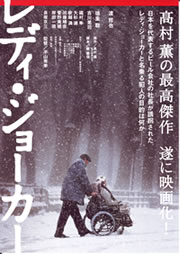 「グリコ・森永事件」を基にした高村薫の原作を平山秀幸監督が映画化。脚本は鄭義信(チョン・ウィシン)。「愛を乞うひと」「OUT」に続くこのコンビの第3作なのだから期待したのだが、完成した映画はがっかりさせられる出来だった。犯人グループ5人のそれぞれの犯行の動機の描き方が希薄で、物語に説得力がない。これが一番の敗因と思う。平山監督はパンフレットで「(原作の)全体から浮かび上がってくるのは、すきま風だらけの日本の現状です」と言っている。だからといって、すきま風だらけの映画にすることはなかった。僕はなんとなく「新幹線大爆破」を思い出しながら映画を見たが、「新幹線…」にあった犯人たちの切実さがこの映画からは感じられなかった。登場人物の多い原作だから、その中の誰に焦点を当てるかによっても映画の印象は変わってくる。誘拐される社長か、犯人か、合田刑事か。それを単に均等に描いていったのでは映画は面白くならない。どれかに重点を置いた方が良かっただろう。そうしなければ、こうした原作ものによくある原作のダイジェストにしかならないのは自明のことだ。脚本の段階でもう少し詰めが必要だったのだと思う。
「グリコ・森永事件」を基にした高村薫の原作を平山秀幸監督が映画化。脚本は鄭義信(チョン・ウィシン)。「愛を乞うひと」「OUT」に続くこのコンビの第3作なのだから期待したのだが、完成した映画はがっかりさせられる出来だった。犯人グループ5人のそれぞれの犯行の動機の描き方が希薄で、物語に説得力がない。これが一番の敗因と思う。平山監督はパンフレットで「(原作の)全体から浮かび上がってくるのは、すきま風だらけの日本の現状です」と言っている。だからといって、すきま風だらけの映画にすることはなかった。僕はなんとなく「新幹線大爆破」を思い出しながら映画を見たが、「新幹線…」にあった犯人たちの切実さがこの映画からは感じられなかった。登場人物の多い原作だから、その中の誰に焦点を当てるかによっても映画の印象は変わってくる。誘拐される社長か、犯人か、合田刑事か。それを単に均等に描いていったのでは映画は面白くならない。どれかに重点を置いた方が良かっただろう。そうしなければ、こうした原作ものによくある原作のダイジェストにしかならないのは自明のことだ。脚本の段階でもう少し詰めが必要だったのだと思う。
昭和22年、日の出ビールを解雇された物井清二が故郷の青森に帰ってくる場面で映画は始まる。清二は被差別部落出身者とともに不当解雇された。弟の清三は兄が日の出ビールに批判の手紙を出すのを見る。そして現代。清三(渡哲也)は東京で薬局を経営しながら一人暮らし。兄は特別養護老人ホームに入っており、やがて死ぬ。その5カ月前、清三の孫は日の出ビールの入社試験に落ちた後、バイク事故で死亡する。ここが重要なのだが、なぜ清三が競馬仲間4人と共謀して日の出ビールを恐喝するのかがよく伝わってこない。レディ・ジョーカーと名乗る犯人グループの5人はそれぞれに事情があるらしいが、それがはっきり見えないのである。レディとは犯人グループの1人、布川(大杉漣)の重度障害を抱えた娘。布川は自分の境遇を「ババを引かされたようなものだ」と自嘲的に言うが、企業恐喝に向かう理由は見あたらない。同じく刑事でありながら犯行に加わる半田(吉川晃司)についてもその理由は明確ではない。
加えて、犯行の描き方も不十分で、最初の日の出ビール社長(長塚京三)の誘拐はいいとしても、その後の恐喝の描写がきわめて物足りない。ビールに毒物を入れることをにおわせただけで、企業が20億円もの金を払うのかどうか。犯人グループの日の出ビールに対する明確な優位性をアピールする場面がほしかったところだ。
平山監督は「これは被差別側が、差別する側に対する復讐劇ですよね」と言ったら、高村薫に「違う」と言われたそうだ。確かに原作は社会の闇を含めてもっと幅が広いけれど、映画にするのならそういう風な単純な映画化もありだなと思う。原作のすべての要素を入れることは無理なのだから、一面的と言われようが、筋の通った映画にした方が良かった。いや、少なくともわかりやすさを捨てて、原作に近づこうとした平山監督と鄭義信の努力は買うべきなのかもしれない。不幸なことにそれが実を結んでいないのだ。
合田刑事役の徳重聡はやや弱いのだが、渡哲也、長塚京三、大杉漣、松重豊、吉川晃司、吹越満、國村隼、岸部一徳らがことごとく重みのある演技をしている。特に吉川晃司はすさんだ感じがいい。こうしたうまい役者をそろえながら、描写が表面的なもので終わってしまったことが惜しまれる。映画に核がないのである。
2004/12/11(土)「山猫は眠らない2 狙撃手の掟」
ルイス・ロッサのあの傑作から9年ぶりの続編。トム・ベレンジャーが50歳を過ぎた狙撃手トーマス・ベケットを演じる。バルカン半島でイスラム教徒抹殺作戦を行っている将軍の暗殺にかり出されたベケットが元エリート狙撃手で死刑囚のコール(ボキーム・ウッドバイン)とともに任務に就く。しかし、作戦の裏には別の作戦があった。
クライマックスは廃墟での敵の狙撃手との戦いになり、悪くない設定なのだが、どうも味が薄い。IMDBで調べたら、TVムービーとのこと。監督はクレイグ・R・バクスレー。原題はSniper2。
2004/12/08(水)「スカイキャプテン ワールド・オブ・トゥモロー」
 クラシックなスタイルの巨大ロボットがニューヨークの街中を地響きを立てながら行進する。そういうビジュアルな面では申し分ない。いや、良くできていると思う。羽ばたきながら飛ぶ飛行機とか、空中に浮かぶ巨大基地とか、後半に登場する恐竜のいる島の描写も優れている(キングコングが出てくれば、もっと良かった)。監督デビューのケリー・コンラン、かつてのSF映画や1930年代から40年代の映画に強く影響を受けているという。その通り、これはマニアが作ったことが一目で分かるビジュアルである。紗のかかった映像がレトロ感を煽るし、主演のジュード・ロウ、グウィネス・パルトロウのファッションもキャラクターも設定した時代によく合っている。しかし、話もクラシックにすることはなかった。古いSF映画そのままのストーリーでは、最新のVFXを使っているのにもったいない。こういう描写の映画として当然行き着くところの話に終わっていて、よくまとまっているけれども、新鮮さや驚きがなく、物足りないのである。ビジュアルが満点とすれば、話の方は60点程度。外見だけでなく中身にも凝ってほしかったところだ。
クラシックなスタイルの巨大ロボットがニューヨークの街中を地響きを立てながら行進する。そういうビジュアルな面では申し分ない。いや、良くできていると思う。羽ばたきながら飛ぶ飛行機とか、空中に浮かぶ巨大基地とか、後半に登場する恐竜のいる島の描写も優れている(キングコングが出てくれば、もっと良かった)。監督デビューのケリー・コンラン、かつてのSF映画や1930年代から40年代の映画に強く影響を受けているという。その通り、これはマニアが作ったことが一目で分かるビジュアルである。紗のかかった映像がレトロ感を煽るし、主演のジュード・ロウ、グウィネス・パルトロウのファッションもキャラクターも設定した時代によく合っている。しかし、話もクラシックにすることはなかった。古いSF映画そのままのストーリーでは、最新のVFXを使っているのにもったいない。こういう描写の映画として当然行き着くところの話に終わっていて、よくまとまっているけれども、新鮮さや驚きがなく、物足りないのである。ビジュアルが満点とすれば、話の方は60点程度。外見だけでなく中身にも凝ってほしかったところだ。
1939年のニューヨークが舞台。突然、巨大なロボットが多数、飛来してくる。科学者失踪事件の取材をしていたクロニクル紙の記者ポリー・パーキンス(グウィネス・パルトロウ)はロボットに遭遇し、必死に写真を撮る。空軍はエースパイロットであるスカイキャプテンことジョー・サリバンに助けを求める。現場に急行したジョーは巧みな操縦技術でロボットを食い止め、街の危機を救う。科学者失踪事件と巨大ロボットの間には関連があるらしい。かつて恋人だったジョーとポリーは事件を捜査し、背後にドイツ人の科学者トーテンコフ博士がいることが分かってくる。ロボットによって空軍基地が襲われ、ジョーの助手で天才技師のデックス(ジョヴァンニ・リビシ)が連れ去られる。デックスの残した地図からトーテンコフ博士がネパールにいることが分かり、ジョーとポリーはネパールに向かう。そしてトーテンコフ博士が「明日の世界計画」と呼ばれるプロジェクトを進行させていることを知る。
ジュード・ロウはハンサムなのでこうした冒険活劇にぴったりのように思えるのだが、この人、陰を引きずった部分があるので、ユーモアの部分が弾けにくい。グウィネス・パルトロウは活発な美人記者役に徹していて悪くない。ゲスト出演的なアンジェリーナ・ジョリーも空の要塞を指揮する隻眼の女艦長を好演。監督も出演者も映画を楽しんで作った感じがあり、それが好感度につながっている。
映画の元になったのはコンランが1人で4年かけてパソコンで作った6分間の短編という。コンラン、オタクな人なのだと思う。そうしたオタクがまず外観を真似ることから始めるように、この映画の外観もかつての映画のイメージで組み立てられている。急いで付け加えると、外観は似ていても、そのアレンジはオリジナリティにあふれており、コンランが作るイメージには一見の価値がある。コンランの次作はエドガー・ライス・バロウズの「火星のプリンセス」。これまたコンランにぴったりのクラシックな題材に思えるが、脚本まで1人で担当するのではなく、強力な助っ人を頼んだ方がいいのではないかと思う。
2004/12/03(金)「モンスター」
 酒場で意気投合したセルビー(クリスティーナ・リッチ)に「一緒に逃げて」と言うアイリーン(シャーリーズ・セロン)の寂寥感が胸を打つ。いや、セルビーにしか希望を見いだせなかった孤独が可哀想すぎる。父親の親友に8歳でレイプされ、弟と妹のために13歳から客を取り始めたアイリーンはそれを家族の前で公にされ、家族から家を追い出されてしまう。金が必要だったから取った選択だが、家族はそんなことを考慮しなかった。アイリーンはヒッチハイクしながら売春するようになり、男から虐げられる毎日を送ることになる。
酒場で意気投合したセルビー(クリスティーナ・リッチ)に「一緒に逃げて」と言うアイリーン(シャーリーズ・セロン)の寂寥感が胸を打つ。いや、セルビーにしか希望を見いだせなかった孤独が可哀想すぎる。父親の親友に8歳でレイプされ、弟と妹のために13歳から客を取り始めたアイリーンはそれを家族の前で公にされ、家族から家を追い出されてしまう。金が必要だったから取った選択だが、家族はそんなことを考慮しなかった。アイリーンはヒッチハイクしながら売春するようになり、男から虐げられる毎日を送ることになる。
本当にこの映画に出てくるのはカスのような男ばかりである。だからレズビアンのセルビーとの出会いはアイリーンにとってかけがえのないものになる。「男も嫌い、女も嫌い。あんただけが好き」。自身はレズビアンでもないのに、暗がりで激しく求め合うのはアイリーンにとって、セルビーが初めて心が触れあえた(と思えた)相手だったからだ。しかし、セルビーと暮らす金のために取った客がひどい男で、森の中でアイリーンは殴られ、あわや殺されそうになる。やむなく男を銃で撃ったアイリーンは約束の時間に待ち合わせ場所に行くことはできず、待ちきれずに帰ったセルビーの部屋の窓をたたく。そして「一緒に逃げて」と懇願し、悲惨な生活の中で初めて(一時的に)ハッピーな逃避行が始まるのだ。
7人の男を殺した実在の連続殺人犯アイリーン・ウォーノスを監督デビューのパティ・ジェンキンスが映画化。連続殺人といっても、よくあるサイコキラーではなく、アイリーンの場合には単純に金を得るための殺しだった。ジェンキンスがイメージしたのは「『タクシードライバー』や『地獄の逃避行』のような70年代型のキャラクター映画」だったという。「『モンスター』と『レイジング・ブル』が比べられるのは、私にとっては最大級の賛辞よ」。映画は女性の連続殺人犯=モンスターが生まれた理由をこれでもかと見せつける。精神に異常を来した連続殺人犯ではなく、社会から受け入れられず、追いつめられた結果、生まれた殺人者。アイリーンの存在が重いのは特殊な事例として遠ざけることができないからだ。弟や妹のために始めた売春のように、アイリーンはセルビーとの生活を守るために殺人を続けねばならなくなる。アイリーンにとって、自分を買うような男は殺されて当然の存在だったのだろう。裁判でセルビーからも見捨てられ、死刑判決を受けたアイリーンの最後のセリフは「勝手にほざけ」。アイリーンの孤独と絶望感はあまりにも深い。
セロンが目を大きく見開いて顔が引きつったような表情をたびたび見せるのはメイクのせいもあるだろう。僕はアカデミー主演女優賞を取ったセロンの演技を必ずしもうまいとは思わない。13キロ体重を増やし、美形を跡形もなく消し去った(パンフレットにある実際のアイリーンよりも美しくない)女優根性には頭が下がるけれども、やはり美人女優は美人のままで女優賞を取ってほしいと思う。しかし、この映画のいくつかの場面でセロンが絶望的な寂寥感を体現していることは否定しようがない。そして、セロンが美しい外見のままでは演技が評価されなかったことと、アイリーンが娼婦になったこととの間にはそんなに大きな隔たりはないように思える。
2004/11/27(土)「Mr.インクレディブル」
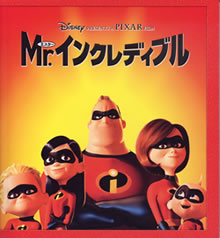 スーパー・パワーが社会の迷惑になるとして引退させられ、政府の保護下に置かれたスーパー・ヒーローとその家族が難事件に出会ったことで復活する姿を描くピクサーの3DCGアニメ。おもちゃや魚やお化けを描いてきたピクサーとしては珍しく人間(スーパー・ヒーローだが)が主役の映画で、これは監督のブラッド・バードが加わったことによるものだろう。「アイアン・ジャイアント」の監督であるバードは今回も伏線を張ってしっかりとした物語を組み立て、大人が見ても楽しめるアニメに仕上げている。音楽や悪役の描き方は007調、構成は「スパイキッズ」を思わせるけれど、家族が絆を深める姿やスーパー・パワーを持つ子どもの自己実現の姿をじっくりと描いており、その両者よりは良い出来である。主人公の家族の絆や愛情は普通の家族にも当てはまることで、そうした普遍性を備えているのが強いところか。エモーショナルなものを根底に置くのはピクサー映画の特徴だが、この映画もその例に漏れない。少し長い(上映時間は2時間)ので、小さな子どもにはつらい部分もあるけれど、バードの映画としては、個人的に違和感がつきまとった「アイアン・ジャイアント」よりはるかに優れていると思う。
スーパー・パワーが社会の迷惑になるとして引退させられ、政府の保護下に置かれたスーパー・ヒーローとその家族が難事件に出会ったことで復活する姿を描くピクサーの3DCGアニメ。おもちゃや魚やお化けを描いてきたピクサーとしては珍しく人間(スーパー・ヒーローだが)が主役の映画で、これは監督のブラッド・バードが加わったことによるものだろう。「アイアン・ジャイアント」の監督であるバードは今回も伏線を張ってしっかりとした物語を組み立て、大人が見ても楽しめるアニメに仕上げている。音楽や悪役の描き方は007調、構成は「スパイキッズ」を思わせるけれど、家族が絆を深める姿やスーパー・パワーを持つ子どもの自己実現の姿をじっくりと描いており、その両者よりは良い出来である。主人公の家族の絆や愛情は普通の家族にも当てはまることで、そうした普遍性を備えているのが強いところか。エモーショナルなものを根底に置くのはピクサー映画の特徴だが、この映画もその例に漏れない。少し長い(上映時間は2時間)ので、小さな子どもにはつらい部分もあるけれど、バードの映画としては、個人的に違和感がつきまとった「アイアン・ジャイアント」よりはるかに優れていると思う。
主人公のインクレディブルはスーパー・ヒーローとして街を守っていたが、ビルから落ちた男を助けたために訴訟を起こされる。男は自殺しようとしたのであって、助けてもらおうとは思っていなかった。助けられた時のけがで不自由な体になったという理由。同時にスーパー・ヒーローたちの強すぎるパワーは社会問題となり、ヒーローたちは活動を禁じられる。15年後。インクレディブルことボブ・パーは保険会社に勤めてさえない毎日を送っている。妻は元スーパー・レディのイラスティガールことヘレン。消える能力を持つヴァイオレット、超人的な走りの能力を持つダッシュ、赤ん坊のジャック・ジャックの3人の子どもがいる。会社で困っている人に保険金が出るよう手を回したボブは社長から責められ、ふとした弾みで社長に重傷を負わせて会社をクビになる。そこへスーパー・ヒーローの能力を使う依頼が来る。暴走したロボット兵器を止めてほしいというものだった。しかし、その依頼には陰謀があり、ボブは捕らわれの身となる。ヘレンとヴァイオレット、ダッシュは力を合わせて父親を救出しようとする。
一般市民としての生活を守るため、インクレディブルの家では子供たちにスーパー・パワーの使用を禁じている。その力を思い切り使う場面を用意することで、映画は子どもの自己実現の重要さを訴えているし、同時に父親を助けようとする家族、家族を思う父親の姿を描いて、脚本には隙がない。ユーモラスな描写に絡めてそうした部分をしっかりと描いているのがいい。3DCGの技術はピクサー独自のものではなくなったし、今さら珍しくはないけれど、脚本を大事にする姿勢はピクサー映画のブランド化に大きく貢献していると思う。
吹き替えは主人公をクレイグ・T・ネルソン、ヘレンをホリー・ハンターが担当。日本語吹き替え版は三浦友和、黒木瞳がそれそれ演じている。どうでもいいが、手足がグイーンと伸びるインクレディブル夫人の能力は「ワンピース」のゴム人間ルフィを参考にしたのではないか。バードはパンフレットで「日本人はそのアニメのポテンシャルに気づいて、アニメの可能性をどんどん切り開いていると思う。世界のアニメは今、日本に追いつこうとしているんだよ」と語っており、日本のアニメはよく研究しているはずである。