 素直に罪を認めれば、罰金刑で済み、午後までには釈放。否認すると、勾留が数カ月に及ぶこともある。痴漢のような軽犯罪であっても扱いは重罪犯と何ら変わらない。そういう現状を改めて詳細に描くとともに、映画は裁判自体の理不尽さを徹底して描く。日本の裁判に無罪の推定なんてない。警察からいったん犯人扱いされたら終わり。無実を証明するには被告人と弁護士、支援者に大変な労力が要求される。それでも無罪判決を勝ち取ることはまれだ。日本の裁判は有罪率99.9%なのだという。映画には推定無罪を信念とする裁判官も登場するが、弁護士によってそうした裁判官が少数派であることが説明される。なぜか。国家を敵に回す裁判官は昇進しないからだ。もう絶望的な気分になる状況を周防正行は怒りをこめて描き出す。満員電車の中で痴漢に間違われることなんていつ何時、自分に降りかかる災難か分かったものではない。だからこそ、この映画は怖い。周防正行は脚本を書くのに3年かけたという。チャラチャラしたお手軽な作品が多い最近の日本映画において、この映画が持つ重みは取材の充実が裏打ちしているのだと思う。11年ぶりの監督作に過去の作品とはまるで異なる社会派の題材を選んだ周防正行はそれを見事に成功させた。
素直に罪を認めれば、罰金刑で済み、午後までには釈放。否認すると、勾留が数カ月に及ぶこともある。痴漢のような軽犯罪であっても扱いは重罪犯と何ら変わらない。そういう現状を改めて詳細に描くとともに、映画は裁判自体の理不尽さを徹底して描く。日本の裁判に無罪の推定なんてない。警察からいったん犯人扱いされたら終わり。無実を証明するには被告人と弁護士、支援者に大変な労力が要求される。それでも無罪判決を勝ち取ることはまれだ。日本の裁判は有罪率99.9%なのだという。映画には推定無罪を信念とする裁判官も登場するが、弁護士によってそうした裁判官が少数派であることが説明される。なぜか。国家を敵に回す裁判官は昇進しないからだ。もう絶望的な気分になる状況を周防正行は怒りをこめて描き出す。満員電車の中で痴漢に間違われることなんていつ何時、自分に降りかかる災難か分かったものではない。だからこそ、この映画は怖い。周防正行は脚本を書くのに3年かけたという。チャラチャラしたお手軽な作品が多い最近の日本映画において、この映画が持つ重みは取材の充実が裏打ちしているのだと思う。11年ぶりの監督作に過去の作品とはまるで異なる社会派の題材を選んだ周防正行はそれを見事に成功させた。
痴漢に間違われた青年(加瀬亮)が無実を主張し、裁判を闘うことになる。というプロットは簡単だ。監督の狙いは裁判そのものを描くことにあったのだから、余計な夾雑物は一切廃している。キネマ旬報2月上旬号によると、周防監督は中年のサラリーマンと若者を主人公にした脚本をそれぞれ5稿まで書いたそうだ。若者が主人公になったのは、中年が主人公になると家族の話まで広げざるを得なくなるからであり、それでは裁判自体を描くというテーマに沿うことができなくなるからだ。それでも脚本を見せた人からは「映画と講演つきで公民館などを回るしかないんじゃないか」と言われたという。一歩間違えれば、そうした文化・啓発映画にしかなりそうにない題材だが、主義主張だけでなく、映画をコントロールし、面白い映画に仕上げる技術が周防正行には備わっていた。
過去のエンタテインメント作品で培った技術はここにも生かされている。それを端的に感じるのはおなじみの竹中直人であったり、主人公が留置場で知り合う本田博太郎のおかしなキャラクターであったりするのだが、弁護士役の役所広司、瀬戸朝香(「Death Note」に続いて好演)をはじめ、母親役のもたいまさこ、裁判官役の小日向文世、刑事の大森南朋らのキャラクターの作り方にも功を奏している。加えて、主人公に最初に接した当番弁護士が人権派の浜田(田中哲司)であるにもかかわらず、浜田は裁判制度にあきらめを感じつつあったために主人公に示談を勧めるという描写や、推定無罪を信条とする裁判官(正名僕蔵)が途中で交代させられる点、同じく痴漢冤罪事件で控訴審を闘う佐田(光石研)が主人公の支援に回るエピソードなどが積み重ねられ、映画を重層的なものにしている。
正義の実現に努力する弁護士たちの姿にはよくある裁判劇のように胸を熱くするものがあるのだけれど、周防正行は決してそれを中心にせず、裁判制度の問題点のみに焦点を絞っていく。2時間23分は少し長いと思ったが、冗長な部分はなく、息抜きの場面を入れながら、テーマを掘り下げて描いた構成と演出力は大したものだと思う。2年後には裁判員制度が始まるが、一般から選ばれた裁判員がかかわる刑事裁判は重大事件に限られるので、こうした痴漢冤罪事件の構造は今後も変わらないだろう。映画の中で「痴漢冤罪事件には日本の刑事裁判の問題点がはっきりと表れている」と役所広司が言うが、その現状を変えたい、変えなくてはいけないという主張が明確に伝わる映画である。
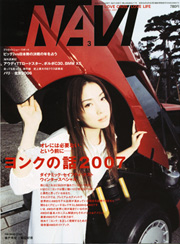 自動車雑誌「NAVI」3月号の特集。これは読み応えがあった。清水和夫が内外の10台の車の走行性能を雪道でテストしたレポートで、ダイナミック・セーフティ・テスト(DST)の雪上版。心が動きつつある日産スカイラインはさんざんな評価で、購入意欲が萎えてくる。一般道と高速走行は問題ないが、雪道では他の車に比べてほとんど話にならないぐらいのレベルだ。
自動車雑誌「NAVI」3月号の特集。これは読み応えがあった。清水和夫が内外の10台の車の走行性能を雪道でテストしたレポートで、ダイナミック・セーフティ・テスト(DST)の雪上版。心が動きつつある日産スカイラインはさんざんな評価で、購入意欲が萎えてくる。一般道と高速走行は問題ないが、雪道では他の車に比べてほとんど話にならないぐらいのレベルだ。 素直に罪を認めれば、罰金刑で済み、午後までには釈放。否認すると、勾留が数カ月に及ぶこともある。痴漢のような軽犯罪であっても扱いは重罪犯と何ら変わらない。そういう現状を改めて詳細に描くとともに、映画は裁判自体の理不尽さを徹底して描く。日本の裁判に無罪の推定なんてない。警察からいったん犯人扱いされたら終わり。無実を証明するには被告人と弁護士、支援者に大変な労力が要求される。それでも無罪判決を勝ち取ることはまれだ。日本の裁判は有罪率99.9%なのだという。映画には推定無罪を信念とする裁判官も登場するが、弁護士によってそうした裁判官が少数派であることが説明される。なぜか。国家を敵に回す裁判官は昇進しないからだ。もう絶望的な気分になる状況を周防正行は怒りをこめて描き出す。満員電車の中で痴漢に間違われることなんていつ何時、自分に降りかかる災難か分かったものではない。だからこそ、この映画は怖い。周防正行は脚本を書くのに3年かけたという。チャラチャラしたお手軽な作品が多い最近の日本映画において、この映画が持つ重みは取材の充実が裏打ちしているのだと思う。11年ぶりの監督作に過去の作品とはまるで異なる社会派の題材を選んだ周防正行はそれを見事に成功させた。
素直に罪を認めれば、罰金刑で済み、午後までには釈放。否認すると、勾留が数カ月に及ぶこともある。痴漢のような軽犯罪であっても扱いは重罪犯と何ら変わらない。そういう現状を改めて詳細に描くとともに、映画は裁判自体の理不尽さを徹底して描く。日本の裁判に無罪の推定なんてない。警察からいったん犯人扱いされたら終わり。無実を証明するには被告人と弁護士、支援者に大変な労力が要求される。それでも無罪判決を勝ち取ることはまれだ。日本の裁判は有罪率99.9%なのだという。映画には推定無罪を信念とする裁判官も登場するが、弁護士によってそうした裁判官が少数派であることが説明される。なぜか。国家を敵に回す裁判官は昇進しないからだ。もう絶望的な気分になる状況を周防正行は怒りをこめて描き出す。満員電車の中で痴漢に間違われることなんていつ何時、自分に降りかかる災難か分かったものではない。だからこそ、この映画は怖い。周防正行は脚本を書くのに3年かけたという。チャラチャラしたお手軽な作品が多い最近の日本映画において、この映画が持つ重みは取材の充実が裏打ちしているのだと思う。11年ぶりの監督作に過去の作品とはまるで異なる社会派の題材を選んだ周防正行はそれを見事に成功させた。 平山夢明の悪夢と狂気の異様な短編集。8編が収録されている。「このミステリーがすごい」で1位となり、収録してある同名の短編は日本推理作家協会賞を受賞している。最初の「C10H14N2(ニコチン)と少年 乞食と老婆」で軽いジャブ。続く「Ω(オメガ)の聖餐」でノックアウトされた。その後は普通のミステリっぽいSF、あるいはSFっぽいミステリが続くが、最後の「怪物のような顔の女と溶けた時計のような頭の男」で再びノックアウトされる。平山夢明はもの凄い話を書く作家だなと思う。
平山夢明の悪夢と狂気の異様な短編集。8編が収録されている。「このミステリーがすごい」で1位となり、収録してある同名の短編は日本推理作家協会賞を受賞している。最初の「C10H14N2(ニコチン)と少年 乞食と老婆」で軽いジャブ。続く「Ω(オメガ)の聖餐」でノックアウトされた。その後は普通のミステリっぽいSF、あるいはSFっぽいミステリが続くが、最後の「怪物のような顔の女と溶けた時計のような頭の男」で再びノックアウトされる。平山夢明はもの凄い話を書く作家だなと思う。