 「あたしたちには県庁さんの力が必要なんです」。高校を中退して16歳から三流スーパーにパートで勤める二宮あき(柴咲コウ)が主人公の野村聡(織田裕二)に言う。もちろん、「県庁さん」とは県庁の組織のことではなく、主人公を指す。野村は県の巨大プロジェクトの中心にいて、「県庁の星」と期待されていたが、派閥によってプロジェクトから外され、建設会社社長の娘との婚約も解消。自分が望んでいたものをすべて失い、「エリザベスタウン」の主人公のようなどん底の状態に落ちる。ショックで民間研修先のスーパーも無断欠勤。そこへ、野村が書いたスーパーの改善計画を読んだあきがやってきて「あなたが必要だ」と話すのだ。「あたし、いつも気づくのが遅いんだ」。
「あたしたちには県庁さんの力が必要なんです」。高校を中退して16歳から三流スーパーにパートで勤める二宮あき(柴咲コウ)が主人公の野村聡(織田裕二)に言う。もちろん、「県庁さん」とは県庁の組織のことではなく、主人公を指す。野村は県の巨大プロジェクトの中心にいて、「県庁の星」と期待されていたが、派閥によってプロジェクトから外され、建設会社社長の娘との婚約も解消。自分が望んでいたものをすべて失い、「エリザベスタウン」の主人公のようなどん底の状態に落ちる。ショックで民間研修先のスーパーも無断欠勤。そこへ、野村が書いたスーパーの改善計画を読んだあきがやってきて「あなたが必要だ」と話すのだ。「あたし、いつも気づくのが遅いんだ」。
あきの言葉がきっかけとなり、野村はスーパーの改善に懸命に取り組み、同時に一般庶民の視線に立って人間的な成長を果たしていく。桂望実の原作を「白い巨塔」や「ラストクリスマス」などテレビドラマのディレクター西谷弘が監督。終盤にある主人公の演説シーンなどは設定がリアリティーに欠けるし、県庁内部の描写にステレオタイプなものもある。しかし、後半、厳しい現実を知った主人公がそれまでの上昇志向から変わっていく姿には深く共感できるし、映画デビュー作としては上々の出来と思う。こういう話、僕はとても好きだ。織田裕二もいいけれど、目の動きや言いかけた言葉、さりげない仕草に深い情感を込めた柴咲コウの演技にほとほと感心させられた。柴咲コウ、「メゾン・ド・ヒミコ」に続いて絶好調である。
元々、野村がスーパー「満天堂」に研修に来たのは事業費200億円をかけたプロジェクトを成功させるためだった。そのプロジェクト、「特別養護老人複合施設(ケアタウン)」の建設は市民団体から反対の声が起きていた。プロジェクトに民間の視点を取り入れるため、野村など数人が民間企業に研修に行くことになる。スーパーのことを知り尽くし、“裏店長”と呼ばれるあきが店長(井川比佐志)から野村の教育係に指名される。最初は反発し合っていた2人が徐々に心を開くのはこうしたドラマの定跡と言えるが、この映画、べたべたしない展開が非常に良い。少しずつ少しずつ、2人は距離を縮めていくのだ。原作では中年女性のあきを25歳の女性に変更したのはロマンスの要素を取り入れるためだそうで、それは成功している。
町並みにそびえ立つ県庁のビルは庶民とかけ離れた県の政策、姿勢の比喩でもあるのだろう。高層ビルから下界に降りた野村は庶民の高さで物事を見ていくようになる。そしてスーパーの現状を仕方がないとあきらめていたあきも野村によって変わっていくことになる。「出会うはずのなかった二人 起こるはずのなかった奇跡」というこの映画のコピーは内容を端的に表していてうまいと思う。外国人もいるスーパー店員たちとの交流や売れる弁当を作るために主人公が奮闘する「満天堂」内の描写はどれも良い。残念ながら、県庁の描写はやや誇張された部分が感じられる。プロジェクトの話も原作にはないそうで、どうもこの部分の処理があまりうまくないのだが、人生の絶頂にあった主人公が転落するドラマティックさを強調するためには必要だったのかもしれない。
柴咲コウは「日本沈没」の撮影が終わって1週間でこの映画の撮影に入ったそうだ。準備期間がほとんどないままで、これだけの演技ができるのなら大したものだと思う。大作などよりはこうした生活感のある役の方が向いているのではないか。
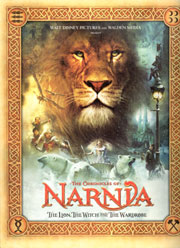 C・S・ルイスの傑作ファンタジーを「シュレック」(2001年)のアンドリュー・アダムソン監督で映画化。「シュレック」はおとぎ話をひねった大人向け作品だったが、今回はディズニー製作ということもあって真っ当な子供向け作品である。子供向けとしてはロバート・ロドリゲス「シャークボーイ&マグマガール」などよりはよほど志が高く、刺激は少ないけれども大人が一緒に見に行っても退屈はしない。クリーチャーのデザインはWETA社が担当しているので、敵方の怪物などは「ロード・オブ・ザ・リング」を思わせる。クライマックスの戦闘シーンも「ロード…」風である。大きく異なるのは主人公が子供であることもあって、物語の深みやドラマティックな展開に欠けることだ。原作が子供向けなのでしょうがないのだが、外見をいくら似せようとも「ロード・オブ・ザ・リング」の牙城には大きく及ばない。いや同じ子供向けの「ハリー・ポッター」にも負けているだろう。主役の4人の兄妹にあまり魅力がないとかの問題はあるにせよ、物語の語り口が単調なことが一番の問題で、これはもう少し緩急を付けて見せる工夫が必要だったように思う。当然作られるであろう第2作ではそのあたりを考えてドラマを面白く見せて欲しいと思う。
C・S・ルイスの傑作ファンタジーを「シュレック」(2001年)のアンドリュー・アダムソン監督で映画化。「シュレック」はおとぎ話をひねった大人向け作品だったが、今回はディズニー製作ということもあって真っ当な子供向け作品である。子供向けとしてはロバート・ロドリゲス「シャークボーイ&マグマガール」などよりはよほど志が高く、刺激は少ないけれども大人が一緒に見に行っても退屈はしない。クリーチャーのデザインはWETA社が担当しているので、敵方の怪物などは「ロード・オブ・ザ・リング」を思わせる。クライマックスの戦闘シーンも「ロード…」風である。大きく異なるのは主人公が子供であることもあって、物語の深みやドラマティックな展開に欠けることだ。原作が子供向けなのでしょうがないのだが、外見をいくら似せようとも「ロード・オブ・ザ・リング」の牙城には大きく及ばない。いや同じ子供向けの「ハリー・ポッター」にも負けているだろう。主役の4人の兄妹にあまり魅力がないとかの問題はあるにせよ、物語の語り口が単調なことが一番の問題で、これはもう少し緩急を付けて見せる工夫が必要だったように思う。当然作られるであろう第2作ではそのあたりを考えてドラマを面白く見せて欲しいと思う。 「あたしたちには県庁さんの力が必要なんです」。高校を中退して16歳から三流スーパーにパートで勤める二宮あき(柴咲コウ)が主人公の野村聡(織田裕二)に言う。もちろん、「県庁さん」とは県庁の組織のことではなく、主人公を指す。野村は県の巨大プロジェクトの中心にいて、「県庁の星」と期待されていたが、派閥によってプロジェクトから外され、建設会社社長の娘との婚約も解消。自分が望んでいたものをすべて失い、「エリザベスタウン」の主人公のようなどん底の状態に落ちる。ショックで民間研修先のスーパーも無断欠勤。そこへ、野村が書いたスーパーの改善計画を読んだあきがやってきて「あなたが必要だ」と話すのだ。「あたし、いつも気づくのが遅いんだ」。
「あたしたちには県庁さんの力が必要なんです」。高校を中退して16歳から三流スーパーにパートで勤める二宮あき(柴咲コウ)が主人公の野村聡(織田裕二)に言う。もちろん、「県庁さん」とは県庁の組織のことではなく、主人公を指す。野村は県の巨大プロジェクトの中心にいて、「県庁の星」と期待されていたが、派閥によってプロジェクトから外され、建設会社社長の娘との婚約も解消。自分が望んでいたものをすべて失い、「エリザベスタウン」の主人公のようなどん底の状態に落ちる。ショックで民間研修先のスーパーも無断欠勤。そこへ、野村が書いたスーパーの改善計画を読んだあきがやってきて「あなたが必要だ」と話すのだ。「あたし、いつも気づくのが遅いんだ」。