2006/07/17(月)「日本沈没」
 映画を見た某SF作家が「小松左京原作とはまったくの別物」という趣旨のことを書いていたのが気になっていた。映画を見てみると、なるほど、原作の大きな改変がある。某アクションスターが主演したアメリカ映画を思わせる展開である(パンフレットでは小松左京原作の「さよならジュピター」を指摘している)。これが安易な改変なら口を極めて罵るところだが、樋口真嗣監督、映画をうまくまとめている。改変には興行上の計算もあったのかもしれないが、阪神大震災後の映画として何よりも映画のラストに希望が欲しかったのだろう。こういう改変をしつつ成功したことは褒められていい。樋口真嗣のこのまとめ方と通俗性はハリウッド映画を目指しているように思える。正攻法に徹した岩代太郎の音楽が映画に風格を与えている。
映画を見た某SF作家が「小松左京原作とはまったくの別物」という趣旨のことを書いていたのが気になっていた。映画を見てみると、なるほど、原作の大きな改変がある。某アクションスターが主演したアメリカ映画を思わせる展開である(パンフレットでは小松左京原作の「さよならジュピター」を指摘している)。これが安易な改変なら口を極めて罵るところだが、樋口真嗣監督、映画をうまくまとめている。改変には興行上の計算もあったのかもしれないが、阪神大震災後の映画として何よりも映画のラストに希望が欲しかったのだろう。こういう改変をしつつ成功したことは褒められていい。樋口真嗣のこのまとめ方と通俗性はハリウッド映画を目指しているように思える。正攻法に徹した岩代太郎の音楽が映画に風格を与えている。
主演2人の好演も映画を支えている。特に柴咲コウ、「東京消防庁ハイパーレスキュー隊阿部玲子、皆さんを救出に来ました」というラストのセリフは、ヘリからカッコ良く登場する冒頭のシーンと呼応していてとてもいい。草なぎ剛も役柄に真摯に取り組んだ姿勢がかいま見えて僕は好感を持った。残念なのは庶民の視線で未曾有の大災害を描きながら、庶民のエピソードが少ないこと。これをもっともっと描けば、映画はより充実したのではないか。脚本にそういう部分での厚みが足りないのである。
太平洋プレートの沈み込みで蓄積されたマントル(メガリス)が崩壊することによって、太平洋プレートの沈み込みが加速、それに引きずられて日本は沈没する。というのが映画の最初の方でアメリカの科学者が提示する仮説。これは30年後に起きるとされていた。しかし、田所博士(豊川悦司)は独自の調査によってマントル内のバクテリアの増殖でプレートの沈み込みが加速し、日本は1年以内に沈没することを発見する。そして日本各地で火山が噴火、大地震が発生し、日本列島は崩壊していく。
映画はこの骨格に深海潜水艇のパイロット小野寺(草なぎ剛)と東京消防庁のハイパーレスキュー隊員阿部玲子(柴咲コウ)のエピソードを絡めて描く。冒頭、静岡を襲った大地震で両親を失った少女美咲(福田麻由子)が火に巻き込まれそうになるのを小野寺は見つける。間一髪のところで、レスキュー隊のヘリが来て、ロープで下りた隊員が少女を救う。この呼吸がとてもよろしい。隊員はもちろん玲子で、このことで2人は親しくなる。政府側の対応を代表するのが文部科学大臣で危機管理担当大臣に指名された鷹森沙織(大地真央)。沙織は田所博士と20年前に離婚したという設定。首相(石坂浩二)が阿蘇の噴火で死に、首相代行となった内閣官房長官(國村隼)と対立しながら、国民を救出しようと奔走する。
映画は後半、次々に起きる大災害と、まるで「ドラゴンヘッド」のような火山灰が降る中で逃げまどう人々を描きながら、イギリスに脱出しようと誘う小野寺と玲子の関係に焦点を絞っていく。玲子は阪神大震災で両親を亡くし、自分だけレスキュー隊員に助けられた過去を持つ。今は東京の叔母(吉田日出子)の世話になっている。だから美咲の姿に自分を重ねており、「一人でも多くの人を助けたい」と思っている。愛する者を失う悲しみに耐えられなかった玲子は「もう誰も愛さない」と誓ったが、小野寺を愛してしまう。終盤の小野寺と玲子の関係が切ない。
樋口真嗣は73年版「日本沈没」の影響を大きく受けているそうだ。73年版は名作でも傑作でもないが、それなりのインパクトは持っていた。パニック映画流行の中で封切られた旧作と樋口版「日本沈没」の違いは時代背景の違いとも重なっているのだろう。映画の出来としては今回の方が良いと思う。
2006/07/16(日)「寝ずの番」
中島らもの原作をマキノ雅彦監督が映画化。「ほな、師匠、行かせてもらいます」という木村佳乃がすごくいい。色っぽくていい。ポルターガイストみたいな嫁はんという形容もおかしい。落語の師匠が死んで、通夜に集まった弟子たちが艶笑談を繰り広げる。何てことはない話だが、笹野高史、岸部一徳、長門裕之、木下ほうからが芸達者なので、大人向けの喜劇に仕上がっている。一番の儲け役は笹野高史か。
中井貴一はこうした喜劇には向かないかなと思ったが、健闘していると言うべきか。ちょっとだけ出てくる高岡早紀も良かった。
2006/07/10(月)「リンダ リンダ リンダ」
キネ旬ベストテン6位、日本映画プロフェッショナル大賞2位(ちなみに1位は「いつか読書する日」)。山下敦弘の作品だけにダラダラしているが、そのダラダラが女子高生の日常を表していて悪くない。そんなにドラマティックな日常はないものなのだ。
「ばかのハコ船」を見た時にはダラダラ感がいやだったが、この映画の場合、主演の4人がいいので、退屈せずに見ていられる。
前田亜紀と香椎由宇が特に良かった。当たり前か。主演はペ・ドゥナなのだろうが、この2人がいなければ興味半減していただろう。松山ケンイチって、この映画にも出てるんですね。
2006/07/05(水)「いつか読書する日」
50代のラブストーリー。行間を読む映画だなと思う。モントリオール審査員特別大賞の授賞式で緒形明監督も「すべてを説明する映画ではなく、何かを感じ取ってもらえれば」とスピーチしていた。僕が思い浮かべたのは岸部一徳が死ぬシーンで成瀬巳喜男の「乱れる」(傑作ではない)、妻の死後に結ばれる2人を見て平岩弓枝の短編小説(タイトルは忘れた)。
主人公2人の心情を終盤までほとんど描かないのはハードボイルド的な手法。というか、僕は古い日本映画を見るような感じを持った。行間を読ませる映画というのは詩的な映画でもあるということだ。詩的であることを意識したかどうかは知らないが、映画監督である前に映画ファンという緒形明は古い日本映画もたくさん見ているのだろう。
主人公の美奈子(田中裕子)が長い坂道の階段を前に「よしっ」と自分に言い聞かせるシーンがおかしい。50代ともなれば、ああいう風になるのだろう。僕も既にあんな長い坂道を上る体力はありませんがね。怖かったのは仁科亜季子が点滴を引きずりながら、牛乳受けに手紙を入れるシーン。死を目前に控えた女の執念みたいなものを感じた。
2006/06/30(金)「Death Note 前編」
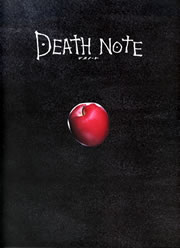 大場つぐみ・小畑健のベストセラーコミックを平成ガメラ3部作の金子修介監督が映画化。警察で対処できない犯罪者を主人公が殺すという始まりは警察内部の私設警察を描いた「黒い警察」や「ダーティハリー2」を思わせるが、この映画の場合、名前を書かれた人間は死ぬというデスノートを使うのでファンタジーっぽい様相がある。ただし、映画の魅力はファンタジーではなく、意外なストーリー展開とキャラクターの面白さの方で、ミステリ的な趣向の方にある。原作漫画を4巻まで読んでみたが、映画の脚色(大石哲也)は原作のエッセンスをコンパクトにまとめてあってうまいと思う。原作には登場しない主人公の恋人にクライマックス、劇的なドラマを用意しており、ここではっきりと主人公がダークサイドに落ちたことを明らかにしている。このあたりの驚きは最初から主人公に悪の雰囲気がある原作にはないものだ。デスノートの元の所有者である死神リュークのCGは良くできていて、原作よりも漫画チックな造型であるにもかかわらず、陳腐にはなっていない。金子修介のエンタテインメントの資質が良い方向に働いたと思う。2時間2分の上映時間のうち、少し冗長と思える部分もあるが、第2のキラと死神が加わって、夜神月(ライト)とLの対決が本格化する後編が楽しみになった。
大場つぐみ・小畑健のベストセラーコミックを平成ガメラ3部作の金子修介監督が映画化。警察で対処できない犯罪者を主人公が殺すという始まりは警察内部の私設警察を描いた「黒い警察」や「ダーティハリー2」を思わせるが、この映画の場合、名前を書かれた人間は死ぬというデスノートを使うのでファンタジーっぽい様相がある。ただし、映画の魅力はファンタジーではなく、意外なストーリー展開とキャラクターの面白さの方で、ミステリ的な趣向の方にある。原作漫画を4巻まで読んでみたが、映画の脚色(大石哲也)は原作のエッセンスをコンパクトにまとめてあってうまいと思う。原作には登場しない主人公の恋人にクライマックス、劇的なドラマを用意しており、ここではっきりと主人公がダークサイドに落ちたことを明らかにしている。このあたりの驚きは最初から主人公に悪の雰囲気がある原作にはないものだ。デスノートの元の所有者である死神リュークのCGは良くできていて、原作よりも漫画チックな造型であるにもかかわらず、陳腐にはなっていない。金子修介のエンタテインメントの資質が良い方向に働いたと思う。2時間2分の上映時間のうち、少し冗長と思える部分もあるが、第2のキラと死神が加わって、夜神月(ライト)とLの対決が本格化する後編が楽しみになった。
ガメラが登場してもおかしくない空撮で映画は始まり、ガメラのようなタイトルで物語が始まる。タイトル前にデスノートの効果を示すのが分かりやすい語り口。そこから映画は少しさかのぼってライトがデスノートを手にした経緯を語る。原作の高校生ライトはデスノートを拾ったことで、殺してもいい人間として犯罪者を選ぶが、映画のライト(藤原竜也)は司法試験一発合格の大学生で、裁ききれない犯罪者への怒りを感じてデスノートを利用する。犯罪のない新しい世界を作ろうと意図する善の男なのだ。ライトは次々に重犯罪者を殺していき、世間からキラと呼ばれるようになる。警察はキラの行為は大量殺人として、これまでさまざまな難事件を解決してきたというL(松山ケンイチ)に協力を仰ぐ。Lはライトが関東地方に住むことを突き止め、捜査情報が漏れていることから内部に関係者がいると見抜く。ここからライトとLの駆け引きが描かれていく。これに絡むのがFBI捜査官の恋人をライトに殺された南空(みそら)ナオミ(瀬戸朝香)。ナオミはライトを怪しいとにらみ、周辺を調べ始める。
ライトは超エリートで悪の主人公なのだが、演じるのが藤原竜也なので脚本の意図通り、単純な悪人には見えない。対するLのキャラクターはいかにも変人で不気味なメイク。善と悪が入れ替わってもおかしくない作りなのが面白い。脚本は原作の設定を尊重しながら、原作にはないさまざまなエピソードを取り入れている。知略を尽くしたライトとLの戦いというのは映画の方がより分かりやすく描かれているし、犯罪者たちの死の描写を取り入れたことでドラマに厚みもあると思う。脚本の大石哲也はこれまでテレビのミステリドラマが中心で、この映画のミステリ的な雰囲気もそれが功を奏したのかもしれない。
ライトの恋人を演じる香椎由宇は、犯罪者はあくまで法律で裁くべきというライトとは対照的な考え方の持ち主として描かれ、非日常的な物語を抑える役目を果たして好演。ライトの父親の鹿賀丈史も堂々とした演技で良かった。