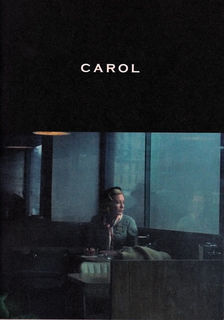2016/05/09(月)「スポットライト 世紀のスクープ」
カトリック教会の神父による児童への性的虐待と教会の組織的な隠蔽を調査報道したボストン・グローブ紙の実話。記者たちが一大スキャンダルを調査するという点で「大統領の陰謀」(1976年)を思い浮かべたが、監督のトム・マッカーシーも映画化の際に「大統領の陰謀」を参考にしたそうだ。そして「大統領の陰謀」と同じく、この作品もアカデミー作品賞を受賞した。
しかし、この映画は「大統領の陰謀」以上に胸を打つ。それは題材がワシントンポスト紙のボブ・ウッドワードとカール・バーンスタインが追及したウォーターゲート事件よりも身近であり、被害者が圧倒的に多いからだ。記者たちは被害者に会い、子ども時代に受けた傷が未だに影響していることを知る。中には自殺した被害者もいた。記者たちが突き動かされたのは単純な正義感ではない。権力をかさに貧困家庭の少年少女に標的を絞った汚いやり口への嫌悪感、信者の信頼を裏切る事件を隠蔽してきた教会への怒り、過去に事件を大きく取り上げてこなかった自分たちへの後悔などがないまぜになったものだ。
「スポットライト」とは同紙の特集記事で、4人の記者が担当している。2001年、ニューヨーク・タイムズのマイアミから編集局長としてマーティ・バロン(リーヴ・シュレイバー)が赴任してくる。バロンから指示された4人は神父の性的虐待事件を調べ始める。その神父、ゲーガンは30年間に80人の児童に性的虐待をした疑惑が持たれていた。事件を調べるうちに、虐待をした神父はゲーガン以外にもおり、それが想像以上に多いことが分かってくる。教会は事件を起こした神父を異動させ、被害者の家族と裁判所を通さない示談を行い、事件の表面化を防いできた。教会の組織的な隠蔽を暴き、事件の再発防止を図るため、チームは資料を調べ、地道な取材を積み重ねていく。
4人の記者はチームのリーダー、ウォルター”ロビー”ロビンソン(マイケル・キートン)、熱血漢で粘り強いマイク・レゼンデンス(マーク・ラファロ)、被害者に寄り添うサーシャ・ファイファー(レイチェル・マクアダムス)、データ分析担当のマット・キャロル(ブライアン・ダーシー・ジェームズ)。作品賞を取りながら、だれも主演賞にノミネートされなかった(ラファロとマクアダムスが助演賞ノミネート)のは、この調査報道が1人の功績ではなく、チームの共同作業およびそれをバックアップしたボストン・グローブ全体の成果として描いているからだろう。
4人はそれぞれに好演しているが、毅然とした編集局長を演じるリーヴ・シュレイバーが一番の儲け役かもしれない。事件への過去の対応を悔やむロビーに対して、バロンは言う。「我々は暗闇の中を手探りしながら歩いている。光が差して初めて間違っていたことに気づく」。ジャーナリズム云々の前にこれは組織を描いた映画として見ることができる。
欧米で教会の権力は大きく、その信者も多い。さまざまな圧力と妨害を受けながら、記者たちが真実にたどり着くまでをトム・マッカーシー監督は緊密なタッチでまとめた。ハワード・ショアの音楽も相変わらず一級品だ。
新聞をまねた体裁のパンフレットに「『スポットライト』の後、何が起こったのか」という文章を町山智浩さんが書いている。それによると、「2002年から全世界で報告された神父によるレイプは4000件におよび、800人が神父の資格を剥奪され、2600人が職務永久停止処分を受けた。カトリック教会が支払った賠償の額は2012年には26億ドルを超えた。多くの教区が破産した」。報道の影響はウォーターゲート事件以上なのではないか。
2016/05/06(金)「キャロル」
パトリシア・ハイスミスの原作を読んでから見たので、ダイジェスト感がそれなりにあったが、脚本が物語のセリフの多くを作り直していることに感心した。原作のプロットを追いながら、セリフの9割ぐらいはオリジナルではないか。主人公テレーズ(ルーニー・マーラ)が目指している仕事も違い、原作では舞台美術家だが、映画では写真家だ。このほか、原作にはないエピソードや描写を織り交ぜていながら、映画は原作通りという印象を与える。フィリス・ナジーの脚本は本筋を誤っていない。
結論から言うと、同じトッド・ヘインズ監督で同じく50年代を描き、同性愛がモチーフの一つにあった「エデンより彼方に」(2002年、ジュリアン・ムーアがアカデミー主演女優賞を受賞した)ほどの充実度はない。しかし50年代を再現した美術とファッション(衣装デザインは「エデン…」と同じサンディ・パウエル)、主演2人の的確な演技によって見応えのある映画になっている。
原作はハイスミスがデビュー作「見知らぬ乗客」の次、1952年に出版した第2作。同性愛を扱ったためにクレア・モーデン名義で出版されたが、1年後に出たペーパーバック版は100万部のベストセラーとなったそうだ。デビュー2作目とは思えないほどうまい小説で、描写の隅々や登場人物の造型、ハイスミスらしいサスペンスでぐいぐい読ませる。何より女性同士の恋愛を普通のラブストーリーとして描いたのが当時としては画期的だったのだろう。ハイスミスの名前で出版するにはそれから40年ほどかかった。
映画は原作よりもLGBTへの偏見の問題を前面に出している。テレーズはマンハッタンの高級百貨店フランケンバーグのおもちゃ売り場でアルバイトをしている。クリスマス間近のある日、毛皮のコートを優雅にまとった美しい女性(ケイト・ブランシェット)がやってくる。その女性、キャロル・エアードは4歳の娘リンディへのプレゼントを買いに来た。この出会いの場面はハイスミスが原作を書くきっかけになった実体験に基づいており、テレーズがキャロルの美しさに目を留め、そして視線が合う描写が印象的だ。この描写はラストシーンにつながっている。テレーズはキャロルが売り場に忘れた手袋をクリスマスカードとともに郵送する。数日後、キャロルが電話をかけてきて、テレーズを昼食に誘う。そこから2人の交流が始まる。キャロルは郊外の屋敷に住んでいるが、夫のハージ(カイル・チャンドラー)とはリンディの親権を巡って離婚協議を進めていた。
離婚理由の一つはキャロルの同性愛にあり、キャロルは幼なじみのアビー(サラ・ポールソン)と過去にそういう関係にあったことが示唆される。社会全体が同性愛を異常なものとしてとらえていた保守的な時代、離婚調停でも道徳的規範が持ち出され、親権の行方はキャロルに不利な状況にある。キャロルはテレーズを誘って、西部への旅行に出かける。
キャロルとハージの言い争いや離婚協議での口論は原作にはない。いや、同じ場面はあるが、映画の方がどちらの場面も激しく、LGBTの問題を浮き彫りにしている。それが60年以上前の原作を映画化する意味でもあるのだろう。1950年代より随分ましとはいえ、偏見はなくなっていないのだ。ゲイを公言しているヘインズと恐らく同性愛者のフィリス・ナジーはここに自身の主張を込めたのだろう。
ルーニー・マーラは相変わらず良い。マーラから美貌のひとかけらか、ふたかけらを取りのぞき、憂いの表情を葬り去ると、オードリー・ヘップバーンになる感じだ。「なんてきれいなの」とキャロルが感嘆するシーンがあるけれども、その通りだった。
旅行の途中、ウォータールーを訪れたキャロルが「ひどい名前ね」と言う場面がある。原作によると、ウォータールーには「挫折、失敗の意味がある」のだそうだ。
2016/04/27(水)「レヴェナント 蘇えりし者」
19世紀のアメリカ西部を舞台にした復讐劇。と言うよりは熊に襲われて瀕死の重傷を負い、厳寒の荒野に置き去りにされた主人公の過酷な自然の中でのサバイバル劇がメインになる。リチャード・ハリス主演、リチャード・C・サラフィアン監督の「荒野に生きる」(1971年)を彷彿させる内容だと思ったら、同じ実話を基にしていた。つまりリメイクだが、元の映画がそれほど知られていないためか、リメイクをアピールしてはいない。原案としてクレジットされているのは2002年に出版されたマイケル・パンクの小説(レヴェナント 蘇えりし者 =ハヤカワ文庫NV)なので製作者にリメイクの意識もなかったのだろう。同じ話とはいっても冒頭の先住民襲撃の場面から映像の迫力がただ事ではなく、「荒野に生きる」をはるかに凌駕した出来栄えである。
1823年、毛皮ハンターの一団のガイド役として主人公のヒュー・グラス(レオナルド・ディカプリオ)は息子のホーク(フォレスト・グッドラック)とともにミズーリ川沿いの荒野にいた。そこにさらわれた娘を捜す先住民のアリカラ族が襲撃してくる。飛び交う矢と銃撃で多くの男たちが倒れるが、グラスたち10人ほどが船で辛くも川に逃れる。このまま川を下るのは危険と判断したグラスの提案で一団は山沿いの道を選択。しかし、見張りに出たグラスは巨大な熊に襲われる。喉を食い破られ、体中に深い傷を負ったグラスの命が長くないとして隊長のヘンリー(ドーナル・グリーソン)はグラスの死を見届け、埋葬するよう命じた。ホークと友人のブリジャー(ウィル・ポールター)、金目当てのジョン・フィッツジェラルド(トム・ハーディ)がそれに応じ、荒野に残った。グラスの生命力は予想以上で、業を煮やしたフィッツジェラルドはグラスを殺そうとする。それを止めたホークをフィッツジェラルドはグラスの目の前で刺し殺し、グラスを穴の中に埋めてブリジャーとともに逃げ出す。
グラスは穴から這い出し、フィッツジェラルドへの復讐を誓う。生きるためにヘラジカの骨をすすり、草の根をかじり、生魚にかぶりつく。傷を消毒するために銃の火薬で喉を焼く。強い復讐心が生きる原動力になったのは想像に難くない。
残虐なシーンは多いが、映画は格調高い。それを支えるのがエマニュエル・ルベツキの撮影で、雄大な自然と人間の格闘をリアルなタッチで切り取っている。3年連続のアカデミー撮影賞受賞も当然と思える素晴らしさだ。坂本龍一もシーンに的確で印象的なスコアを提供し、格調を高めている。坂本龍一にはもっと映画音楽を担当してほしい。
巨大な熊の凶暴さはそこら辺のホラーを蹴散らす怖さ。CGであるにしても、この迫力は大したものだ。監督のアレハンドロ・G・イニャリトゥはほとんど息抜きのない緊張感あふれる映画に仕上げている。「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」に続く2年連続のアカデミー監督賞も納得できる。
死地から帰還した男の復讐と言えば、冒険小説では定番の設定で、そういう話が好きな人には必見の映画と言える。
2016/02/28(日)「俳優 亀岡拓次」
「ウルトラミラクルラブストーリー」以来7年ぶりの横浜聡子監督作品。と言うよりも、俳優・安田顕の主演作と言った方が一般的には通るだろう。横浜聡子は不幸なことに自主制作の「ジャーマン+雨」(2006年)で2007年の監督協会新人賞を受賞した。これは本人にとって重荷になったに違いない。次の「ウルトラミラクル…」はあまりにも普通の出来だったにもかかわらず、キネ旬は「天才候補」という代名詞を付けて紹介してしまった。「ウルトラミラクル…」を見た人は思っただろう。これのどこが「天才候補」なんだ?
それから7年、横浜聡子は普通のウェルメイドな作品を撮る監督として再登場したと言って良い、この映画を支えているのは澤井信一郎「Wの悲劇」のスター女優がそのまま年を重ねたような舞台女優を演じる三田佳子の在り方(容貌は年を重ねていても声はまったく変わっていない)であり、亀岡拓次とカウンターを挟んで差し向かいで飲む居酒屋「ムロタ」の女将・安曇(麻生久美子)の魅力である。
いや、もちろん安田顕のいつものおかしさもこの映画には至る所にあるのだけれど、それは監督の手腕とはあまり関係ないだろう。安田顕はどの監督の映画でもこういう演技をしたはずだ。
と、ここまで書いて不安になったので、まだ見ていなかった「ジャーマン+雨」を見た。うーん。主人公のキャラと設定が面白いだけで、素人の習作の域を少しも出ない作品だった。2006年の日本映画界はこれが新人監督賞を取るぐらい不作な年だったのだろうか? この程度の映画を「天才」だなんだと書いた映画関係者はすべて廃業していただいた方が日本映画のためだと思う。だいたい、「天才」なんて言葉が似合うのは十代までだろう(横浜聡子は当時、20代後半だった)。
「ジャーマン+雨」に比べれば、「俳優 亀岡拓次」は、はるかにプロの仕事だ。主人公の亀岡は脇役専門の役者。そのさまざまな映画と舞台の現場を描きながら、映画は亀岡の日常を描いている。主役を張れない役者の在り方はほとんどの観客(主観的にはその人の人生において主役であっても、客観的、社会的には主役ではあり得ない人たち)の共感を得ることができるだろう。戌井昭人の原作で亀岡拓次のモデルになったといわれる宇野祥平も良い味を出している。
「ジャーマン+雨」当時よりも、「俳優 亀岡拓次」現在の横浜聡子の進歩を素直に評価した方がいい。横浜聡子は過去ではなく、今を評価すべき監督なのだと思う。一部の人からのみ評価される天才よりも、より多くの人の支持を得る凡人の方が良い場合もあるのだ。
劇場でパンフレットを買ったら、キネ旬ムックだった。監督・出演者のインタビューのほか、完成台本も収録されていて普通のパンフよりも中身が濃いのはキネ旬が編集したためか。パンフにはこれぐらいの内容がいつも欲しい。amazonでも販売している。
【amazon】映画『俳優 亀岡拓次』オフィシャルブック (キネマ旬報ムック)
2016/02/27(土)「スパイダー・シティ」
多数の巨大なクモが突然出現するパニック映画。2012年のテレビムービーなのでやっぱりそれなりの出来。主演はなんとエドワード・ファーロングだった。「ターミネーター2」でジョン・コナーを演じた時には将来のスターかと思ったが、そんなにうまくは行かなかったらしい。
Wikipediaのファーロングの項目を見ると、薬物・アルコール依存症になったり、妻への接近禁止命令が出されたりとかさんざんだ。若くして必要以上に注目されると、良いことはないなと思う。フィルモグラフィーはほとんどB・C級映画とテレビ。それでも出演作が途切れていないのは幸いだ。
映画はツッコミどころ満載だが、テレビでボーッと眺めている分には腹は立たない。クモが出現した理由はそれなりに説明される。このクモ、地下のシェール層に巣を作っていたが、シェールガスの開発で巣を追われ、地上に出てきた。数センチから1メートル超までサイズはさまざま。シェールガスを体内に取り込んでいるので火を噴いたりする。最後には巨大な女王グモが出現する。クモはコロニーを作らないはずで、脚本家はクモをアリやハチと勘違いしているようだ。
原題は「Arachnoquake」。IMDbの採点は2.8とメタメタだ。監督は俳優としての作品が多いグリフ・ファースト。監督としての才能は感じられないから俳優に専念した方がいいと思う。
【amazonビデオ】スパイダー・シティ (字幕版)