2006/11/12(日)「手紙」
 「そんなことしたらあかん、大事なものやんか! そんなことしたらあかん!」。沢尻エリカ扮する白石由美子が兄からの手紙を破り捨てた主人公の武島直樹(山田孝之)に言う。ここで2人の仲が急速に接近してそれで映画は終わりになるのかと思ったら、その後にさらに本当の決着がある。罪を犯した者とその家族、犠牲者の家族の関係。原作は未読だが、そこまで描くのは大したものだと思う。しかし、全体的には主人公が漫才師を夢みることにどうしても違和感があった。山田孝之は本質的に暗いイメージなので、似合っていないのである。非常にうまく演じているのだが、似合っていず、中学の頃から笑いを目指していたとは思えない。とんとん拍子に人気者になることにはもっと違和感があるし、大企業の専務令嬢(吹石一恵)との愛と破局などは破局の場面に一工夫あるとはいえ、吹石一恵が登場した時から先が読める展開。会社の先輩である田中要次の過去と大検を目指す現在の姿などは泣かせるし、杉浦直樹の差別社会の本質を突いたセリフも泣かせる。そうした美点とあまりにもありふれた描写が混在していて、そこが評価をためらわせる。もっともっと脚本を練ることが必要だったのではないかと思う。
「そんなことしたらあかん、大事なものやんか! そんなことしたらあかん!」。沢尻エリカ扮する白石由美子が兄からの手紙を破り捨てた主人公の武島直樹(山田孝之)に言う。ここで2人の仲が急速に接近してそれで映画は終わりになるのかと思ったら、その後にさらに本当の決着がある。罪を犯した者とその家族、犠牲者の家族の関係。原作は未読だが、そこまで描くのは大したものだと思う。しかし、全体的には主人公が漫才師を夢みることにどうしても違和感があった。山田孝之は本質的に暗いイメージなので、似合っていないのである。非常にうまく演じているのだが、似合っていず、中学の頃から笑いを目指していたとは思えない。とんとん拍子に人気者になることにはもっと違和感があるし、大企業の専務令嬢(吹石一恵)との愛と破局などは破局の場面に一工夫あるとはいえ、吹石一恵が登場した時から先が読める展開。会社の先輩である田中要次の過去と大検を目指す現在の姿などは泣かせるし、杉浦直樹の差別社会の本質を突いたセリフも泣かせる。そうした美点とあまりにもありふれた描写が混在していて、そこが評価をためらわせる。もっともっと脚本を練ることが必要だったのではないかと思う。
原作が家にあったので、冒頭部分を少し読むと、原作では一人暮らしの老婦人の殺し方に明確な殺意がある。持っていたドライバーを首に刺すのである。映画はもみ合っているうちに老婦人が抵抗するために手にしたハサミが腹に刺さって死んでしまう(これは腹ではなく、首か心臓の方が良かったと思う)。盗み目的で侵入した上での殺人だから強盗殺人罪も仕方ないが、どちらかと言えば、過失致死の線が濃厚である。映画の改変は殺人者の兄に同情を持たせるためだろう。兄が強盗に入ったのは運送会社での激務で腰を痛め、仕事ができなくなったことで弟を大学に行かせられない恐れがあったため。そうした不遇な状況の中で、殺人者の家族に冷たい世間を描いていく。
「俺みたいなヤツに言われたかねえだろうけどよ、夢があるなら、簡単に諦めんなよ」。リサイクル工場の先輩である倉田(田中要次)が言う。倉田は食堂で働く由美子が直樹にクリスマスプレゼントを贈ったことで、「最近の若いやつはやることは早いんだから」などと嫌がらせをするのだが、実は倉田自身、服役経験があり、直樹の兄の手紙を見てすべてを理解する。そして家族が誇れる父親になりたいと、大検を目指していることを告白するのだ。こういう地道な話で終わっても良かったのではないかと思う。直樹は「夢をあきらめるな」というアドバイスに従って工場をやめ、お笑いの道を友人の寺尾祐輔(尾上寛之)とともに目指すことになる。そこからの描写が安っぽい上にリアリティに欠け、映画はしばらく停滞してしまう。それが復調するのはお笑いをやめ、秋葉原の電気店で働く直樹が埼玉の倉庫へ左遷させられる場面から。倉庫を訪れた会社の会長(杉浦直樹)は「差別があるのは当然だ」と話す。「しかし、君は差別のない場所を探すんじゃない。ここで生きていくんだ」と言う杉浦直樹の言葉は力強く、直樹に言葉をかけた理由が由美子からの手紙だったことが胸を打つ。由美子自身、父親が多額の借金を背負って逃げ回った過去があるが、「私はもう逃げへん」と決意しているのである。その由美子の決意はたった一人の肉親を大事にするべきだという前記のセリフに表れている。
こうした細部のエピソードは非常にうまい部分もあるのに、ぎくしゃくした感じが映画にはつきまとい、そこがとても残念だ。生野慈朗監督はテレビのベテランディレクターで、映画としては「いこかもどろか」(1988年)「どっちもどっち」(1990年)の2本が既にある(「いこかもどろか」は公開当時、映画評論家の山田宏一が絶賛していたが、見ていない)。描写がテレビドラマ的というのは短絡だけれど、お笑いの場面はテレビドラマを超えるものではなかったと思う。ついでに言えば、沢尻エリカが途中で眼鏡を外すのもよく分からない。最後まで眼鏡の方が良かった。「電車男」でも思ったが、山田孝之は男から見ても好感度がある。玉山鉄二は「逆境ナイン」とは全然違う役柄をうまく演じていて、これまた好感が持てる。
2006/10/30(月)「父親たちの星条旗」
 一枚の完璧な構図の写真を巡る物語。硫黄島の摺鉢山に星条旗を立てた6人の兵士のうち、生き残った3人が英雄としてもてはやされ、戦時国債を売るための広告塔の役目を強要される。しかし、3人が立てた星条旗は2番目のものであり、6人の中には実際には加わっていない兵士もいた。いわば3人は虚飾のヒーローだったわけである。無名の兵士がばたばたと死んでいく硫黄島の凄惨な激戦と3人の揺れる心情が時間軸を前後して交互に描かれ、「戦争に英雄などいない」「国家は人間を簡単に使い捨てる」というテーマを浮き彫りにしていく。戦場シーンはスケールも悲惨さも際だっており、色彩を落とした映像が効果を上げている。虚飾に耐えきれず、酒に溺れるようになったアメリカ先住民の兵士など「昨日のヒーロー」となった3人のその後も深い余韻を与える。もちろんクリント・イーストウッド監督作品だから水準以上の出来なのだが、個人的にはもう少し上層部への明確な批判があっても良かったような気がする。
一枚の完璧な構図の写真を巡る物語。硫黄島の摺鉢山に星条旗を立てた6人の兵士のうち、生き残った3人が英雄としてもてはやされ、戦時国債を売るための広告塔の役目を強要される。しかし、3人が立てた星条旗は2番目のものであり、6人の中には実際には加わっていない兵士もいた。いわば3人は虚飾のヒーローだったわけである。無名の兵士がばたばたと死んでいく硫黄島の凄惨な激戦と3人の揺れる心情が時間軸を前後して交互に描かれ、「戦争に英雄などいない」「国家は人間を簡単に使い捨てる」というテーマを浮き彫りにしていく。戦場シーンはスケールも悲惨さも際だっており、色彩を落とした映像が効果を上げている。虚飾に耐えきれず、酒に溺れるようになったアメリカ先住民の兵士など「昨日のヒーロー」となった3人のその後も深い余韻を与える。もちろんクリント・イーストウッド監督作品だから水準以上の出来なのだが、個人的にはもう少し上層部への明確な批判があっても良かったような気がする。
国家が人間を使い捨てるのなら、このテーマの行き着く先は国家そのものの批判だろう。それが鋭くならないのはハリウッド・メジャー作品の限界か。日本やドイツのような敗戦国は終戦時にいったん国家体制がリセットされたために、戦争中の軍国主義やナチズムの批判が当たり前で、戦争映画にはその視点がたいてい出てくる。アメリカの戦争映画に非人間的な軍隊への批判はあっても国家そのものの批判が少ないのはアメリカは第2次大戦後もずっと戦争を続けているからではないかと思う。第2次大戦時も今も基本的には変わらないのである。当時の体制を批判することは今の体制批判にもつながる。この映画を見ている時に感じたもやもや感は批判の矛先があいまいな部分から生じているように思う。
死んでいく兵士たちは自分たちを戦場に送った国への恨み言も口にしないし、国を論評することもない。それどころか、日本兵を罵ることもない(これは興行上の戦略だろう)。彼らはただただ何も言わずに銃撃され、爆撃で体を無惨に吹き飛ばされて唐突に死んでいく。彼らはいったい何を思って死んでいったのか。そこを映画はすくい上げるべきではなかったか。
例えば、笠原和夫脚本の「大日本帝国」にはこんなセリフがある。この映画は以前も書いたが、「二百三高地」のヒットに気をよくしたプロデューサーが太平洋戦争の勝ったところばかりピックアップしてつなぐという企画を出したのに対して、笠原和夫は逆にシンガポール、サイパン、フィリピンと激戦地ばかりをつないで脚本を書いたものである。映画の中で終戦後に東南アジアで軍事裁判にかけられた西郷輝彦の腹の底から振り絞るような口調のセリフ。
「大元帥陛下が我々を見殺しにするはずはなかでしょ。我々は天皇陛下の御楯になれと言われてきたとです。そう命じられた方がアメリカと手を結んで我々を見捨てるなんちゅう事は絶対にありません。日本政府はポツダム宣言を受諾したとしても、天皇陛下はたとえお一人になられたとしても、必ずわたしらを助けにきてくださるはずです。こげな、いかさまみたいな裁判で死刑にされて浮かばれますか」。
不当に死んでいく者の恨みつらみというのはこういうセリフのことを言う。「父親たちの星条旗」の主人公で衛生兵のジョン・ブラッドリーは戦後、家族に硫黄島のことを何も言わないまま死んでいったという。その無言の姿勢を戦争批判につなげたい意図は分かるのだが、時として具体的なセリフがあった方が映画は効果を上げる。脚本のポール・ハギスは映画の冒頭でブラッドリーに「戦争を知っているというバカ者。戦場の事実を何も知らない」と言わせているけれど、この映画に必要なのはそうした一般論ではない。この映画には死んでいく兵士たちの肉声が欠落しており、それが高い技術に感心させられながらも絶賛できない要因になっている。
日本側視点で描く「硫黄島からの手紙」には兵士の思いを入れやすいはずだ。捲土重来を期待したい。
2006/10/22(日)「ブラック・ダリア」
 ジェームズ・エルロイの原作をブライアン・デ・パルマ監督が映画化。原作は本棚を探したら、11年前に買った文庫本があったが、読んでいない。映画はブラック・ダリアことエリザベス・ショートの切断死体が発見される場面の長いワンカットとか、刑事の一人が階段から落ちて死ぬ場面の撮り方とか、突然一人称になるカメラとかデ・パルマらしい場面があるが、全体としてはそうした撮り方が浮き上がって見えないのが大きな利点。場面のアクセントにはなっても、そこだけを取り上げてどうこう言う映画ではない(しかし、言いたくなる。あの違うエピソードに連なるワンカット! あのヒッチコックを思わせる転落場面!)。全体として1940年代のロサンゼルスを描いて、面白い映画になったと思う。
ジェームズ・エルロイの原作をブライアン・デ・パルマ監督が映画化。原作は本棚を探したら、11年前に買った文庫本があったが、読んでいない。映画はブラック・ダリアことエリザベス・ショートの切断死体が発見される場面の長いワンカットとか、刑事の一人が階段から落ちて死ぬ場面の撮り方とか、突然一人称になるカメラとかデ・パルマらしい場面があるが、全体としてはそうした撮り方が浮き上がって見えないのが大きな利点。場面のアクセントにはなっても、そこだけを取り上げてどうこう言う映画ではない(しかし、言いたくなる。あの違うエピソードに連なるワンカット! あのヒッチコックを思わせる転落場面!)。全体として1940年代のロサンゼルスを描いて、面白い映画になったと思う。
不満は事件が解決してしまうこと。ブラック・ダリア事件はもちろん、迷宮入りした有名な事件だが、それがこういうロス・マクドナルドを思わせるような解決の仕方をされると、なんだかがっかりした気分になるのだ。それはエルロイの原作に沿っているのだから当然の措置なのだけれど、終盤に明らかにされる真相や主人公の刑事がミッキー・スピレーン的な決着をつけることがちょっと残念なのである。1940年代の時代風俗と暗黒社会と善悪に揺れる人間たちを活写して魅力的な映画であり、所々に引き込まれる描写はあるのだけれど、少し話が入り組みすぎたきらいもあり、同じエルロイのLA4部作の映画化ならカーティス・ハンソン「L.A.コンフィデンシャル」の方が単純に面白かったと思う。
映画のパンフレットを読むと、実際のブラック・ダリア事件でエリザベス・ショートは3日間にわたって拷問を受け、胃の中には排泄物があったという。つまり拷問の過程で排泄物を食わされたらしい。映画はそこまでではなく、同じ切断死体でも殺され方は少し異なる。原作は事件にかかわる人間の暗い情念を描くことが狙いのようなので、映画もまず、主人公の刑事バッキー・ブライカート(ジョシュ・ハートネット)と同僚のリー・ブランチャード(アーロン・エッカート)とのボクシングでの対決で幕を開ける。火と氷と称される2人は警察予算獲得をアピールするための試合を行う。バッキーは年老いた父親をホームに入れるための金欲しさに八百長で負けるが、警察では特捜課に迎えられ、リーと組んで事件を担当する。リーには美しい恋人のケイ・レイク(スカーレット・ヨハンソン)がおり、3人は毎週、夕食をともにするようになる。
バッキーにとっては最高に幸福な時間だったが、それも長くは続かない。凶悪犯レイモンド・ナッシュを追う過程で、2人は銃撃戦に巻き込まれ、リーはタレ込み屋のフィッチを銃殺。その直後、というか、カメラはこの前にエリザベス・ショート(ミア・カーシュナー)の死体が発見される場面を遠景でとらえ、そのまま大きく移動して女と通りを歩いているフィッチをとらえる。ここが絶妙のワンカットである。そして銃撃戦が終わった後で、ブラック・ダリア事件が始まるのだ。リーはなぜか、ナッシュの事件に目もくれず、ブラック・ダリア事件に夢中になる。ケイは間もなく出所してくる銀行強盗犯ボビー・デウィト(リチャード・ブレイク)に脅える。ケイはかつてデウィトの女だった。バッキーはブラック・ダリア事件を捜査するうちに富豪の娘マデリン・リンスコット(ヒラリー・スワンク)が関係していることを突き止める。
暗黒社会と富豪とブラック・ダリアと刑事たち。それが複雑に交錯していくが、そうした多数の登場人物たちの群像がロスの暗黒を強烈に浮かび上がらせるまでには至っていない。主人公のバッキーに重点を置いた作劇のためか(ジョシュ・ハートネットの陰のないキャラクターも影響しているだろう)、事件の真相でスケールダウンした気分になってくる。エリザベス・ショートの殺され方は明らかに快楽殺人のそれだが、この事件の犯人はそれに合致しないタイプなのも気になった。
2006/10/21(土)「16ブロック」
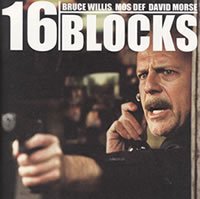 主人公のニューヨーク市警の刑事ジャック・モーズリー(ブルース・ウィリス)が16ブロック離れた裁判所まで護送することになった囚人で証人のエディ・バンカー(モス・デフ)は、こそ泥などをやっているチンピラで、人生の半分ぐらいは刑務所に入っているという男だが、なぜか大事にノートを抱えている。そのノートの内容が襲撃からの逃亡の中でエディが時々言っていた「人間は変われる」という言葉の裏付けとなる。エディは今の自分とは変わって果たしたい夢を持っており、ジャックがエディの夢を信用し、自分も「変わる」決意を固めることで、幸福感あふれるラストへとつながっていくことになる。ジャックもまた変わりたい、過去に決着をつけたいという考えは持っていたのだ。
主人公のニューヨーク市警の刑事ジャック・モーズリー(ブルース・ウィリス)が16ブロック離れた裁判所まで護送することになった囚人で証人のエディ・バンカー(モス・デフ)は、こそ泥などをやっているチンピラで、人生の半分ぐらいは刑務所に入っているという男だが、なぜか大事にノートを抱えている。そのノートの内容が襲撃からの逃亡の中でエディが時々言っていた「人間は変われる」という言葉の裏付けとなる。エディは今の自分とは変わって果たしたい夢を持っており、ジャックがエディの夢を信用し、自分も「変わる」決意を固めることで、幸福感あふれるラストへとつながっていくことになる。ジャックもまた変わりたい、過去に決着をつけたいという考えは持っていたのだ。
タイトなアクション映画として見始めて、それほど際だったアイデアもないので、かつてよくあったようなB級アクションと結論づけるところだったが、このラストで印象が随分変わった。リチャード・ドナーが描きたかったのはアクションよりもこちらの方だろう。ジャックがなぜ酒浸りの日々を送っていたのかもクライマックスで分かる仕掛けで、それをセリフにしない脚本(リチャード・ウェンク)は良い出来だ。見終わってじわじわ効いてくる映画である。最近、不振が続いていた、というよりも作品そのものが少なかったドナーにとって久しぶりに会心の出来ではないか。
ジャック・モーズリーは殺人現場でもウィスキーを飲むような酒浸りの刑事である。ジャックは非番の日に上司から証人を午前10時までに裁判所へ護送する任務を頼まれる。担当の刑事が渋滞で間に合わなかったのだ。いやいや引き受けたジャックは仮釈放中に悪事を犯したというエディを護送することになる。途中、酒店に寄ったところで、何者かが銃撃してくる。一人を撃ち殺したジャックとエディは車を捨てて逃げ、分署に連絡する。通報を受けて駆けつけたのは20年来の友人の刑事フランク・ニュージェント(デヴィッド・モース)とその同僚刑事。しかし、フランクはエディを「まずい現場を見ている」として殺そうとする。エディは悪徳警官の不正を暴くための証人だったのだ。ジャックは刑事の1人を撃って、エディと逃げる。フランクは仲間の刑事たちを指揮し、2人を追い詰める。ジャックとエディは警官を撃ったとしてニューヨーク市警全体を敵に回すことになる。タイムリミットの午前10時まで1時間半。果たして間に合うのか。
フランクは長年のつきあいでジャックの立ち回り先を熟知しており、裏をかこうとする2人の駆け引きがなかなか面白いが、アクションに関してそれほど感心する部分はない。うまいのはキャラクターの設定でジャックはよくある刑事物に出てくる刑事のように単純な正義感で動いているわけではない。悩みながら行動しているのだ。ジャックとエディは行動をともにするうちにお互いに影響し合う。この2人の男が影響しあって変わっていくというのはドナーの「リーサル・ウェポン」にもあった。主人公のメル・ギブソンは妻に死なれて自殺願望を持つ刑事だったが、相棒のダニー・グローバーとの行動の中でそれを克服していった。この2作目以降にはなくなった設定(パロディとしては出てきた)が映画を異色のものにしていたと思う。「16ブロック」はその変奏曲とも言えるだろう。
2006/10/10(火)「ローズ・イン・タイドランド」
テリー・ギリアム監督の前作「ブラザーズ・グリム」はいつものようにトラブルに見舞われたためか、中途半端な出来だった。トラブルで製作が中断していた間に撮ったのがこの映画。ギリアムが本領を発揮した映画になっているかと思ったが、残念ながら本領は発揮していてもそれほど面白さは感じなかった。
「不思議の国のアリス」をモチーフにした映画なのでファンタジーかと思ってしまうが、悲惨な現実を空想好きの少女の視点から描いた映画なのである。視点はダークファンタジー、物語は現実で、ファンタジー色が薄いのが一番の不満(これを見た後に「レディ・イン・ザ・ウォーター」を見たら、すっきりとしたファンタジーになっていたので、余計に点が甘くなった部分はある)。小品レベルのダークな作品であり、「バンデットQ]「未来世紀ブラジル」「バロン」「12モンキーズ」あたりと比べると、破天荒な描写がない分、物足りない。
原作はミッチ・カリン。カリンはギリアムのファンでオビに推薦文を欲しくて本を送ったそうだ。主人公の10歳の少女ジェライザ=ローズ(ジョデル・フェルランド)の両親は2人ともドラッグ中毒。母親(ジェニファー・ティリー)はドラッグの打ちすぎで死に、ローズは父親(ジェフ・ブリッジス)とともに祖母の家へ向かう。草原の真ん中にある家はボロボロで、既に祖母の姿はなかった。近所には家にたくさんの剥製があるデル(ジャネット・マクティア)とディキンズ(ブレンダン・フレッチャー)姉弟が住んでいた。ある日、父親もドラッグを打って椅子に座ったまま目をさまさなくなった。徐々に腐敗し、悪臭を発するようになるが、ローズは父親が眠っていると思っている。ローズは4体の人形の首と一緒に空想の世界に遊び、ディキンズと親しくなる。ディキンズはてんかんの発作の手術を受けており、10歳ぐらいの知能しかない。デルはローズの家に来て、死んでいる父親を見て剥製にする。父親とは以前からの知り合いだったようだ。
姉弟のキャラクターはまるでサイコで、密かに連続殺人を犯していてもおかしくない雰囲気。そういう描写がギリアムらしいところか。ただし、ブラックな味わいが以前の作品ではユーモアに転化した部分があったが、この映画、ブラックはブラックなままでグロテスクな感じがつきまとう。後半にあるセクシャルな雰囲気などもそうで、ここはもっと強調すれば、映画は別の意味で特異な作品になったのかもしれないが、ロリコン描写に規制が厳しい欧米ではこれぐらいが限界だろう。人間関係が今ひとつすっきりしないのも難点で、父親とデルの関係など明確にしたいところ。原作もこういう話のようだ。ギリアム、この話のどこに惹かれたのだろう。
主人公を演じるジョデル・フェルランドは出ずっぱりで好演と思う。それにしてもこのローズ、少しも自分を不幸とは思っていない。現実が不幸すぎるから空想の世界に遊ぶようになったのだろうが、そうした精神分析的な視点が加わると、映画はもっと面白くなったのかもしれない。ギリアムのイメージ自体は楽しめるけれども、もっと文学的な味わいがあればと思えてくる作品だった。