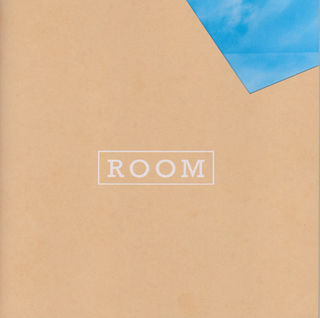2016/11/20(日)「白鯨との闘い」の本筋
なぜ今ごろ、「白鯨」のような話を映画化するのか疑問で、劇場公開時には見逃した。Netflixで見て後半の展開に驚いた。なるほど、こちらが本筋なのか。
ナサニエル・フィルブリックのノンフィクション「復讐する海 捕鯨船エセックス号の悲劇」をロン・ハワード監督が映画化。2003年に邦訳された原作は映画公開に合わせて昨年、「白鯨との闘い」のタイトルで集英社文庫に入った。映画はハーマン・メルヴィルが新作を書くためにかつての捕鯨船乗組員に話を聞くという設定で始まる。新作とはもちろん「白鯨」のことだが、フィルブリックの原作はマッコウクジラによって船を壊された乗組員の漂流がメインのようで、白いクジラを出したのは映画の脚色らしい。原題はIn the Heart of The Sea。
前半は邦題通りに、“海の悪魔”と言われる白鯨との闘いが描かれるが、後半は一転、乗組員たちの過酷な漂流の話になる。「ライフ・オブ・パイ トラと漂流した227日」が比喩的に描いたカニバリズムの話も出てくる。飢えと渇きと疲労で衰弱しきった乗組員たちがくじ引きで誰を食料にするかを決める場面があるのだ。しかし、さすがロン・ハワード、キワモノにはしていない。ハワードは古き良きハリウッド映画の伝統を守り抜いている監督なので、感動的な決着を用意している。夫の悲惨な漂流の実際を初めて知った妻が「それを知っていても私はあなたのそばにいたわ」と話す場面など、ハワードらしい在り方だ。
僕はハワードの直球ど真ん中という演出が好きなのだが、この映画、アメリカでは評価が高くない。ロッテン・トマトで肯定的評価は43%、IMDbの採点は6.9。後半のダークな部分が受けなかったのかもしれない。主演はハワードの前作「ラッシュ プライドと友情」に続いてクリス・ヘムズワース。
2016/11/13(日)「トランボ ハリウッドに最も嫌われた男」 主張備えたエンタテインメント
ダルトン・トランボの名前を知ったのは監督作の「ジョニーは戦場へ行った」(1971年)が公開された時。当時はドルトン・トランボという表記だった。赤狩りによって投獄された“ハリウッド・テン”の一人であり、「ローマの休日」を匿名で書いた脚本家であることはその頃、既に知られていた。終戦後、脚本家として活躍していたトランボ(ブライアン・クランストン)は非米活動委員会に召還され、証言を拒否したために投獄される。映画はそこから復権までの道のりを仲間や家族の描写を織り込みながら描いていく。監督のジェイ・ローチはこれまでコメディの多かった人。それが功を奏したのか、ガチガチの社会派映画にはせず、きっちりと主張を備えたエンタテインメントに仕上げた。

刑務所から出たものの、トランボに以前のような仕事はない。「ローマの休日」は友人のイアン・マクラレン・ハンター(アラン・テュディック)の名義で映画会社に売り込み、アカデミー原案賞を受賞するが、当然のことながら仕事の依頼が来るわけではなかった。トランボはB級映画を量産しているフランク・キング(ジョン・グッドマン)の会社から安いギャラで仕事を請け負う。偽名で脚本を書いたほか、請け負った仕事は脚本家仲間に回し、それをキングが気に入らなかった場合はトランボが書き直す契約。トランボが優れた脚本を書けた理由は映画からは分からないのだが、仕事に追いまくられてバスタブにタイプライターを持ち込み、3日で1本の脚本を仕上げる姿からは一流の職人のような人だったのだなとうかがえる。そうやって書いたロバート・リッチ名義の「黒い牡牛」(1956年)もアカデミー原案賞を得た。
映画が唾棄すべき人物として描いているのは元女優でコラムニストのヘッダ・ホッパー(ヘレン・ミレン)。ホッパーは非米活動委員会の手先のような言動と振る舞いをしてトランボたちを苦しめる。一方でトランボの実力を認めて「スパルタカス」の仕事を依頼するカーク・ダグラス(ディーン・オゴーマン)や「栄光への脱出」監督のオットー・プレミンジャー(クリスチャン・ベルケル)がいるし、ラジオからは非米活動委員会の活動に疑問を呈するグレゴリー・ペックやルシル・ボールの声も聞こえてくる。「アメリカの理想を守るための映画同盟」に所属していたジョン・ウェイン(デヴィッド・ジェームズ・エリオット)もホッパーに比べれば悪い男としては描かれていない。
トランボたちを支援していた俳優のエドワード・G・ロビンソン(マイケル・スタールバーグ)は仕事を干され、非米活動委員会で証言してしまう。かつて支援してもらった金を返しに来たトランボとロビンソンが対峙する場面が印象的だ。匿名でも仕事ができる脚本家と違って、俳優は顔を隠して仕事はできない。ロビンソンは苦渋に満ちた表情でそう話すのだ。
見ていて思うのは寛容と非寛容ということだ。自分とは異なる他人の思想・信条を全面否定し、平気で踏みにじる。赤狩りで行われたのはそういうことだった。一方的な攻撃・弾圧がまかり通る社会は間違っている。トランボは確かに共産党に所属していたが、重視したのは言論の自由を守ることであり、合衆国憲法修正第一条に明記されている言論の自由が封殺される状況に強く反発していた。映画が描いたことはハリウッドの異常な一時期、過去の話に終わるものではなく、今に通じる。
トランボを支える妻クレオ役をダイアン・レイン、長女のニコラをエル・ファニングが好演している。ニコラが公民権運動に参加する描写などはしっかり父親の血を受け継いでいるのだなと思わずにはいられない。庭に池がある大きな家を売って、小さな家に引っ越す一家のホームドラマとしての側面が映画の幅を広げている。
2016/10/09(日)「ある天文学者の恋文」 中盤以降が単調
予備知識一切なしで見たので、最初のクレジットを見て初めてジュゼッペ・トルナトーレの監督作であることを知った。トルナトーレにしては、というか、トルナトーレだからなのか、ツイストが決定的に足りない。死んだ恋人から手紙やメール、ビデオレターが届き続けるという設定だけで話が発展していかないのだ。だから中盤以降が単調に感じられる。
初老の天文学者エド(ジェレミー・アイアンズ)と教え子エイミー(オルガ・キュリレンコ)は恋人関係にあった。ある日突然、エイミーはエドが死んだことを知らされる。ちょうどメールが届いたばかりだったため、エイミーはなかなかエドの死を受け入れられない。彼女の元にはその後もエドからの手紙やメールや贈り物が届き続ける。エイミーはエドが残した謎を解き明かそうと、彼が暮らしていたスコットランド・エジンバラや、2人で過ごしたイタリアのサンジュリオ島を訪ねる。
エイミーには自分が運転していた車に同乗していた父親を事故で亡くした過去がある(ファザコン気味だから初老の教授と恋愛関係になったのだろう)。学生の傍ら、危険なスタントウーマンのアルバイトを続けているのも父親の死の責任を感じ、死の願望を密かに抱いているからなのかもしれない。父親の死以来、母親とは疎遠になっている。届き続ける手紙の意図は母親との関係を修復させることにあるのかと思わせるが、そのあたりの描写はあっさりしたものだ。となると、手紙の意図が分からなくなる。死んでからも恋人を束縛し続けるだけとしか思えないのだ。さまざまな場面を想定して、こんなに何通もの手紙を用意しておくにはかなりの時間がかかったはず。恋人への思いがさせたことであったにしても、この教授、実はとんでもなく偏執的な男に違いない。ある意味、気味の悪いキャラクターだ。
描写も感傷過多で、見ていてうんざり。はいはい、ご勝手にどうぞと思えてくる。撮影当時、妊娠4カ月だったというオルガ・キュリレンコは悪くないが、36歳で大学院生役というのは少し無理がある。20代の女優の方が良かったのではないか。古風な響きがある邦題に対して、原題はCorrespondence(文通、通信)。現代的な通信方法は即物的なのであまりロマンティックにはならないなと思う。
教授のマニアックさはトルナトーレ自身に共通する部分がある。個人的にトルナトーレの映画に心底から感心した作品がないのはマニアックな部分が人物造型に向けられていて、話に向かっていないからだと思う。
【amazonビデオ】ジュゼッペ・トルナトーレの監督作品
2016/08/24(水)「エクス・マキナ」 ヴィキャンデルが大きな魅力

タイトルは「デウス・エクス・マキナ」(機械仕掛けの神)に由来するのだろう。設定はSFだが、展開はミステリーの趣向が強い。舞台は人里離れた山あいの邸宅、主要キャストは4人。こうくれば、ミステリーにしてもおかしくはない。ただ、中盤までは人間とAI(人工知能)をめぐる思索的なセリフがあり、主人公が次第に混乱して自分をアンドロイドではないかと疑う場面は「アンドロイドは電機羊の夢を見るか」(「ブレードランナー」原作)などフィリップ・K・ディックのSFを思わせる。AIを搭載する女性型アンドロイドのエヴァに扮するアリシア・ヴィキャンデルが映画の大きな魅力で、このキャスティングが成功の要因の一つになっている。
世界最大の検索エンジン会社ブルーブックに勤めるプログラマー、ケイレブ(ドーナル・グリーソン)が社内の抽選に当たり、CEOネイサン(オスカー・アイザック)の邸宅に招かれる。ヘリで送られた邸宅は雄大な自然の中にあり、秘密保持のため堅固なセキュリティーが防備されていた。ネイサンの狙いは自分が開発した女性型アンドロイドに搭載したAIのチューリング・テストだった。チューリング・テストとは「イミテーションゲーム」で描かれた天才数学者アラン・チューリングが1950年に考案したテスト。ある機械が知的かどうかを判定するために判定者が機械に話しかけ、その受け答えが本物の人間とまったく区別がつかなければ、知能を持つと判定する。ネイサンはその判定者の役割をケイレブに託した。
エヴァは顔の前面だけに人間のような皮膚を持ち、あとは機械の骨格が透けて見えるデザイン。ガラス越しにエヴァと対面したケイレブは会話をしていくうちに、エヴァに惹かれていく。エヴァが洋服を身につけると、人間と見分けが付かなかった。ネイサンによると、エヴァは性行為もできるように作られているという。停電でカメラの監視が途切れた短い時間にエヴァは「ネイサンを信用しないで」と話す。停電はエヴァが起こしていた。ケイレブはエヴァがネイサン以外で初めて会う人間の男で、エヴァはケイレブの微小表情を読み取り、ケイレブが自分に好意を持っていることを知る。エヴァもケイレブに好意を感じているようだった。エヴァに魅了されたケイレブはエヴァを部屋の外に出すためにある計画を実行しようとする。
邸宅にはもう一人、ネイサンの世話をする日本人のキョウコ(ソノヤ・ミズノ)がいるが、英語を話せない。次第に接近するケイレブとエヴァの関係を見ると、「her 世界でひとつの彼女」のように人間と機械の恋愛感情を描くのかと思ってしまうが、映画は終盤、ケイレブとエヴァとネイサンのそれぞれの思惑によってストーリーが意外な方向に展開していく。
映画は第88回アカデミー賞で「マッドマックス 怒りのデス・ロード」「オデッセイ」「レヴェナント 蘇えりし者」「スター・ウォーズ フォースの覚醒」を抑えて視覚効果賞を受賞した。アンドロイドの造型が大変優れていて、受賞も納得できるのだが、終盤にあるヴィキャンデルの全裸もVFXなのではないかと思えてくる。あれだけ完璧なアンドロイドを描けるのなら、女性のヌードのVFXぐらい簡単だろう。自分がアンドロイドではないかと疑い、カミソリで腕を切る主人公と同じく、観客もどれがVFXでどれが本物か疑心暗鬼になるのだ。
現代的な装飾をはぎ取ってみると、基本的なプロットは「フランケンシュタイン」から連なるマッドサイエンティストものと言うことができるだろう。脚本・監督は「28日後…」「わたしを離さないで」などの脚本で知られるアレックス・ガーランド。これが初監督作だが、静謐なタッチと的確な演出を見せている。
2016/05/28(土)「ルーム」
狭い部屋に7年間監禁された母親ジョイ(ブリー・ラーソン)とその子どもジャック(ジェイコブ・トレンブレイ)。ジャックは5歳になったばかりだ。ジョイはこの部屋でジャックを産んだ。ジャックの父親はジョイを拉致した犯人でオールド・ニック(ショーン・ブリジャース)と呼ばれる(本名は分からない)。部屋の中で物語が進行する前半を見ながら思ったのは、この状況は暴力的な夫から支配され、逃れられない母子と容易に置き換えられるということ。そして、部屋の中が世界のすべてと思っている子どもはSFにありそうな存在だということだ。
エマ・ドナヒューの原作は部屋の中を描く「インサイド」と脱出後を描く「アウトサイド」の構成になっているそうだ(この原作、2014年に文庫が出たが、現在絶版で読めない。映画公開に合わせて復刊できないのは出版不況のためか)。ブッカー賞の候補になったという原作が面白いのだろうが、この構成を踏襲した映画も見ていて前のめりになるぐらい面白い。前半と後半で面白さの質も異なる。
部屋は3.3平方メートルしかないらしい。トイレと浴槽、台所設備はあるが、窓は空しか見えない天窓だけ。ドアは暗証番号を入れないと開かない。閉所恐怖症の人には耐えられないような狭さだ(ジョイが大声で叫ぶ場面がある)。外の世界を知らないジャックはテレビの内容を本物ではないと思っている(そう教えられている)。本物なのは自分と母親だけ。ジョイはそんなジャックを頼みにして「モンテ・クリスト伯」を参考に脱出計画を立てる。
この中盤の場面がとてもスリリングで感動的だ。高熱を出した(ふりをした)後、オールド・ニックに死んだと思わせたジャックは絨毯にぐるぐる巻きにされてピックアップトラックに乗せられる。走り始めて3回目に一時停止したところでトラックを飛び降りるが、オールド・ニックに気づかれ、捕まってしまう。そこに通報を受けた警官がやって来る。女性警官パーカー(アマンダ・ブルーゲル)はジャックの話を根気よく聞いて、母親が監禁されているらしい場所の手がかりを得るのだ。
ここから映画は社会に復帰した母子を描く。ジョイの両親(ウィリアム・H・メイシー、ジョーン・アレン)は離婚し、母親は別の男と暮らしていた。17歳で拉致され、社会と隔絶された7年間を過ごしたジョイは徐々に精神的にまいっていく。ジャックは初めて知る世界の大きさを少しずつ理解し始める。ジョイの父親は犯人の子どもであるジャックをまともに見られない。ジョイは7年間を耐えられたのはジャックがいたからこそで、ジャックに父親はいないと思っている。映画がキワモノにならず、心を揺さぶる作品に仕上がったのは母子を見つめ続ける視点に揺るぎがないからだ。
「ショート・ターム」(2013年)で注目されたブリー・ラーソンはこの映画でアカデミー主演女優賞を受賞した。確かに好演しているが、同賞にノミネートされた「キャロル」のケイト・ブランシェットや「さざなみ」のシャーロット・ランプリングに比べて演技的に際立って優れたところはないように思う。映画の出来がとても良かったことが受賞につながったのではないか。ラーソンよりもジャックを演じたジェイコブ・トレンブレイの方が映画を支えている感じだ。監督はこれが長編5作目のレニー・アブラハムソン。脚本に原作者が加わったことも功を奏したのだろう。